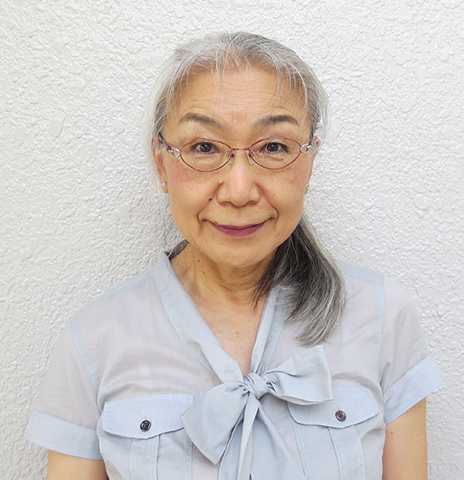感染症の歴史と現在問題になっている感染症
新型コロナウイルス感染症パンデミックのおよそ100年前、20世紀スペイン・インフルエンザの全流行期を通じての致死率は2%程度だったそうです。21世紀に出現した重症急性呼吸器症候群(SARS)が約10%、中東呼吸器症候群(MERS)が30%程度の致死率なので、比べても格段に低い数値です。致死率2%でも感染者が非常に多かったので、死者も爆発的に多かったそうです。世界人口の3分の1から半数近くが感染し、死者数は5000万以上、 最大で1億人という説もあるそうです。以前、日経新聞にも取り上げられたとおり、広く知られた事実です。
歴史学者のアルフレッド・W・クロスビーは「概して我々は、死亡率は低いが、やがて自分たちが関わることになるはずの現実的な病気より、自分たちがほとんど罹りそうにもない高い死亡率を持つ病気の方にずっと恐怖を抱くものである」と言っています。「日本を襲ったスペイン・インフルエンザ」を著した経済学者の速水融氏は「驚くべきことに、このスペイン・インフルエンザについて日本ではそれをタイトルとした一冊の著書もなく、論文すらごく少数あるに過ぎない」としています。人々は、当時は大変な思いをするけれども、集団としての教訓を残さないと忘れてしまいます。果たしてコロナの教訓はどうだったでしょうか。確かにコロナ禍が始まった頃は致死率が高かったけれども、特にわが国でも2021年から主流となったオミクロン株以降は致死率が急激に下がりました。しかし、この後も2023年5月まで全数把握は続いたのです。
コロナ禍については2つ参考になる報告があり、これはネット上で読むことが出来ます。尾身茂氏、脇田隆字氏監修の「新型コロナウイルス感染症対応記録」これによりますと、今世紀の最も深刻な公衆衛生上の危機であり、わが国の新型コロナウイルス対策は、感染者数をなるべく抑えて、医療へのアクセスを確保し、死亡者数をなるべく抑える<感染抑制>を目的とした対策であった。人口10万あたりの死亡者数は諸外国に比べて比較的低く抑えられた一方で、様々な課題があったということで、多くの公衆衛生関係者が次のパンデミックに備えるために共同執筆した記録です。私が思うに、これは結論ではなく、出発点であると考えます。これでよかったのだろうか、次はどうすべきなのかという議論を起こす必要があると思います。
また、日本医師会総合政策研究機構の日医総研ワーキングペーパーによりますと、これは各国の平時の医療提供体制と新興感染症へのレスポンスをまとめたものなのですが、辛い症状があってもなかなか医療機関で診てもらえなかった、薬ももらえなかったという事実がありますよね。これはどうしてなのかということを分析した文章です。次のパンデミックも必ず来ると言われています。コロナ禍の経験を生かさないといけないのではないでしょうか。
ウイルス感染症だけではありません。加えて、多剤耐性菌(抗生剤の効かない細菌)の脅威も進行しています。これは目に見えませんが、大変脅威となっている事象です。自然界から人の健康まで「ワンヘルス」という考え方があり、この概念も普及が必要です。現在では、ウイルス性疾患に抗生剤を使わなくなったことはよく知られています。ヒトと動物、それを取り巻く環境(生態系)は相互につながっていると包括的に捉え、ヒトと動物の健康と環境の保全を担う関係者が緊密な協力関係を構築し、分野横断的な課題の解決のために活動していこうという考え方です。人獣共通感染症対策や薬剤耐性対策などでワンヘルス・アプローチも必要です。このこともご理解いただければと思います。
現代を生きる私たちが注意するべきこと
国はコロナ禍の後で、今後、個別計画強化で対応しようとしています。「保健所における健康危機対処計画」というものを策定しました。一方では、危機が何であれ、どのような規模であれ、現実に即して対応できるようにする「オールハザードアプローチ」というのも必要ではないかなと思います。これは現実に即して、現場から国の中枢まで繋がるアプローチのことです。
基本を抑えて柔軟に対応できるようにする必要があるのではないかと思います。まだ覚えていますか?3密回避、換気、マスクと手洗い、うがい。住民の方は、感染症流行の有無に関わらず、普段からの手洗い、飛沫感染、必要時には空気感染までの注意をしていただけるといいと思います。ワクチン接種ができる方々へのアプローチも大切です。
今、何をすればいいのか、うまく保健所を頼るというのも1つの方法です。保健所は出前講座などを行っているところもあります。市町村にも多くの情報があり、たくさんの情報をホームページで見ることができます。ポイントは行政の発信を見て、行政も住民もお互いに信頼できて近い良好な関係を築くのがいいのではないかと思います。ニュースや広報、ホームページが大変参考になります。私たちはフェイクニュースに警戒し、誤ったSNS情報の拡散にも加担しないで欲しいと思います。