子供の防災学習には「楽しむ」という要素が欠かせない。
災害をイメージしよう
災害はいつ起こるか分からない。今後30年以内に首都直下地震や海底を震源とする巨大地震が発生する危険性が高まっている。政府の中央防災会議は首都直下地震が発生した場合、最悪で死者が1万1千人を超えるとの被害想定を発表している。
災害への備えは災害を想像することから始まる。災害が起きた後、自分がどのような状況に置かれるのか、そのために今何をしておくべきなのかなど、災害をイメージして具体的な対策を練る必要がある。政府ではこうした甚大な被害を軽減するための国民運動を推進していく方針だが、その中でゲームなど子供にも魅力的な形で、わかりやすく正しい災害の知識を提供していくとしている。そこで今回は、楽しみながらゲーム感覚で災害に備えるグッズを紹介する。
カードの指示で頭を守るポーズ
日本損保協会が作成した「ぼうさいダック!」は、大人と子供で遊ぶ幼稚園児から小学校低学年が対象のカードゲーム。大人がカードに描かれた地震や台風などの災害を見せ、裏側の動物がとっているポーズを子供がまねて体を動かすことで安全に対する意識を育てる。たとえば「地震」のカードの場合、裏側には身体を丸めて頭を守るアヒルのポーズが描かれており、子供はそれを真似することで、身を守るための最初の行動を身に付けていくことができる。 カードゲームはB4版(500円)とトランプ版(300円)の2種類。17分の解説ビデオは別売り(1890円)。
防災を生活に密着させる

京都大学防災研究所の矢守克也助教授と慶応大学の吉川肇子助教授らが作成した「大ナマジン 防災すごろく」(1600円)は、子供からお年寄りまで家族で災害への備えを遊びながら確認できるゲーム。1月を振り出しに、12カ月の各月ごとのマスには、ガスの元栓や電気ブレーカーの場所を確認(2月)、非常食の賞味期限の点検(6月)、海水浴場で地震が来た場合の行動を確認(8月)など季節の行事と関連した災害への備えが書いてある。
マス目に書いてある「アクション」に当たった場合、その指令に従って行動する。たとえば、2月のテーマは「通電火災」で、「7」は家のブレーカーの位置を確認しに行く。「5」はガスの元栓の位置を確認しに行ってから進む。ブレーカーがどこにあるのか分からない場合は1回休み。12月は年末の大掃除の機会に家の安全を点検するのがテーマ。「5」か「6」は家の中で高いところに置いてあるものを片付ける。このように参加者が季節を意識した行動を取ることで、生活と防災を密着させるのが狙い。
「ぼうさい駅伝」は沿道からの応援も
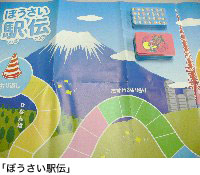
市民防災研究所の防災ゲーム研究会が考案した「ぼうさい駅伝」(1890円)は、小学生から大人までを対象としたクイズとすごろくの組み合わせ。2人1組のチームを作り、4人でプレーする。先行チームの一人がランナー役になり、「たすき」をかける。残りの一人がサイコロを振る。別のチームは100問以上ある問題カードを引いて問題を出す。クイズに正解しないとゴールを目指して前進できない。「沿道から応援」というカードを引くと、サイコロを振った人と協力してクイズに答えることができる。
クイズ問題にはたとえば、「災害時、意外と役に立つラップフィルム! 次の使い方で間違っているものは」という問題で、1)お皿にかぶせる 2)けがの手当て 3)くつの代わり という選択肢がある。問題を出すチームは、「ラップフィルムはお皿にかぶせて使えば、お皿を洗う必要がなくなるし、傷口にガーゼを当てた上から使えば、包帯の代わりにもなる」という解説を読み上げることで、参加者全員が勉強できる。
学校や家族で遊びながら学ぶ
成人を対象とした災害対策や防災用品は数多くあるが、子供を対象としたものは多いとはいえない。少子高齢化が進んでいる中で、子供の命を守る重要さは一層増している。災害について幼い頃から意識付けをしていくことは大人の重要な役目だ。「教える、教えられる」という関係でなく、大人も子供と一緒に意識を高めるという視点があってもいい。一緒に楽しみ、学び、考えることが防災対策では欠かせないように思える。学校では総合教育や防災学習の取り組みとして、またクリスマスやお正月など家族がそろう機会に防災ゲームで家庭の防災対策を考えるきっかけとして取り入れてみてはいかがだろう。
(文・レスキューナウ危機管理情報センター専門員 大川義弘)
copyright © レスキューナウ 記事の無断転用を禁じます。


