2011年11月9日
例年、この季節になるとインフルエンザの感染予防ワクチンを打つ方も多いと思うが、今年(2011年)はRSウイルスにも警戒が必要だ。
RSウイルス感染症、例年にない感染者数
国立感染症研究所によると、例年であれば冬に流行するRSウイルス感染症の患者数が今年(2011年)は6月下旬から増え、以降も感染者が増え続けている。統計が開始された2004年以降で最大の流行となっている。
RSウイルス感染症とは、RSウイルスに感染することで気道の細胞がくっついてしまう感染症のことである。「RS」のRは「Respiratory(呼吸器)」、Sは「Respiratory(細胞を集める)」という意味がある。特に生後6ヶ月未満の赤ちゃんや高齢者の場合は、重い肺炎や気管支炎になることがあるため、咳・鼻水・発熱といった初期症状があらわれた場合には経過をよく観察する必要がある。通常であれば1週間ほどで症状がおさまるが、重症化すると細気管支炎や肺炎になり呼吸困難に陥ることがある。初期症状が改善せず、咳やゼイゼイ・ヒューヒューといった呼吸になった場合は、すぐに医師の診察を受け、適切な治療を受けることが重要だ。
予防策はあるのか

残念ながらRSウイルス感染症については、インフルエンザのように予防ワクチンはない。そのため、インフルエンザ同様の感染予防策を着実に実行することが大切だ。なお、重症化の危険性が高い子供については、ウイルスの増殖を防ぐために「抗体製剤パリビズマブ」を予防的に接種することがある。 ≪感染予防策≫
□手洗いの励行
□うがい
□洗顔
□マスクの着用
□栄養バランスのとれた食生活
□十分な休息
流行状況を常に把握
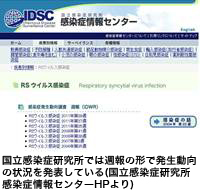
近年、インフルエンザ以外にも「手足口病」・「マイコプラズマ肺炎」といった感染症が流行しているというニュースをよく耳にする。また、今年のRSウイルス感染症のように、例年の流行時期よりも早く感染者が増えるケースもある。そのため、国立感染症研究所が1週間おきに発表している「感染症発生動向調査 週報」(1週間の1医療機関当たりへの受診患者数)の情報を日頃から確認し、流行状況を常に把握しておく必要がある。また、学校や幼稚園・保育園における保護者間での情報交換も予防や対策を行う上で参考となるだろう。
(文・レスキューナウ危機管理情報センター)
copyright © レスキューナウ 記事の無断転用を禁じます。


