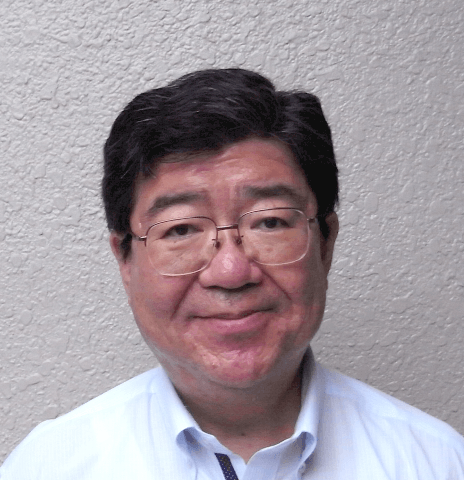プロフィール
以前国土交通省に勤めており、東日本大震災が起きた時は復興担当の課長を務めていました。震災が落ち着いた頃、この番組で復興の話をさせていただいた記憶があります。その後、仕事が大きく変わり内閣官房というところで、環太平洋パートナーシップ(TPP)協定という外交交渉の仕事に8年間携わり、2020年9月からは外務省でチリ駐在の特命全権大使として3年2ヶ月間務め、2023年11月に帰ってきました。
チリという国
チリという国は南アメリカのちょうど日本と反対にあります。日本からチリに行くには、アメリカ経由で24時間ぐらい飛行機に乗らなければならないのでとても遠いのですが、日本列島を縦に2つ並べたような形・大きさです。世界で1番細長い国と言われていて人口は約2,000万人です。日本と同じで地震が多く火山の噴火それから津波もあります。
日本とチリとの関係
日本とチリの外交関係としては、1897年に「修好通商航海条約」というものを結んでいて126年の歴史があります。親日的で、お互いに自然災害で切っても切れない関係にあります。チリの西側は太平洋に面しています。日本列島の東側には日本海溝という海溝がありそれが津波を引き起こしたりしますが、チリも同じように西の太平洋側にチリ海溝という海溝があり、その向きがなんと日本の方を向いています。ですから、チリで大きな海溝型の地震が起きますと津波が日本を直撃するという関係にあります。
1960年にチリで大きな地震があり日本の東北地方を津波が襲う「チリ地震津波」と呼ばれている災害が発生しました。東日本大震災でも大きな被害を受けた今の宮城県の南三陸町などは、この津波で大きな被害を受けましたが、その後もチリとの交流が続き1991年にイースター島のモアイ像のレプリカが贈られています。
しかし、2011年の東日本大震災で流されてしまったので、イースター島の人たちが新しいモアイ像を贈ろうと島の石を切り出して新しく作り南三陸町にプレゼントしました。イースター島の石を使って掘られたモアイ像が島の外に出たのは初めてだったということで、これだけ日本とチリの関係が深く、しかもお互いに災害というものをきっかけとしていろんな付き合いがあるというのは、ぜひ皆さんに知っておいていただきたいと思います。
チリの酪農への支援
チリはサーモン養殖の大国で日本にもサーモンをたくさん輸出していますが、この養殖についても日本の水産庁の技術指導が大きく関わっています。もう1つ、実は酪農大国でもあり乳製品がよく作られているのですが、こちらも日本と深い関係があります。
1960年に発生した大きな地震の影響で、酪農を大規模に行っていたチリ南部の牧草地が沼だらけになってしまい、今まで大規模な落農をしていたところを小規模な狭い土地でやらなければならなくなりました。実は、日本も狭い国土や厳しい条件の中で酪農をしているわけですから、この技術をチリに技術協力として支援を行いチリは日本の技術を使って洛農のふるさとになりました。災害を契機に、このような面でも日本とチリのお付き合いがあるということです。
キズナPROJECT
このような関係もあり、チリを防災関係の人材育成をする拠点にしようということで、2015年から2020年までの5年間、日本のJICAという組織が音頭を取って「KIZUNAプロジェクト」が実施されました。このプロジェクトは中南米地域の防災に関わる専門家を集め、日本の専門家が研修を行い人材育成するという取り組みです。2020年にプロジェクトは終了しましたが、卒業した5,000人以上の専門家は中南米各地で今も活躍しています。他国よりも優れた防災の専門家がたくさん育ったということで、チリではこの「KIZUNAプロジェクト」が日本の技術協力の中でも大変有名な成功事例となっています。
津波への備え
2020年9月、私がチリに到着した時に地震や津波の警報が突然流れました。テレビをつけると海沿いにいた人たちが高台に避難していました。結果的には誤報だったのですが、印象に残ったのは、非常に多くの人が警報を受けてすぐに避難行動を取っているということ。そして、結果的に誤報だということが明らかになっても誰もそれを非難しないこと。「誤報で良かったね」という感覚があり、チリの人たちはすごくいいなと、個人的に思った次第です。
チリ海軍に、日本と同じようなやり方で津波を検知する専門の部局があり、迅速に警報を流しています。こちらについても日本の指導があり、世界でも有数の津波検知に成功している国だと思います。