春本番になり観光地もにぎわいをみせているが、美しい景観の中には過去の災害によって生み出されたものもある。
城の不思議な立地条件

麓には一面に咲き誇る桃の花、目を転ずれば残雪をいただく南アルプスの山々。山国の春の清々しい空気に触れようとこの時期、甲府盆地を旅する方も多いことだろう。
山梨県といえば、信玄に代表される武田氏の遺構をめぐる旅も魅力の一つである。武田氏の城跡は県内に多数残っているが、その一つに新府城(韮崎市)がある。信玄の息子である勝頼によって築かれたこの城は、西を釜無川、東を塩川といういずれも富士川の支流に挟まれた高低差100mほどの台地上に位置し、まさに天然の要害という言葉が相応しい。
実際に現地に赴くと、城郭はその台地よりもさらに100mほど高い丘の上に築かれていたことが分かる。そして、周囲を見渡すと同じような大きさの小高い丘がいくつも点在していることが分かる。このような景観はどのようにして作られたのだろうか。
想像を絶する大崩壊「岩屑流(がんせつりゅう)」
その謎を解く鍵は、新府城の北方にそびえる八ヶ岳にある。
八ヶ岳はその名のごとく多くの峰々からなる総称であるが、古くは富士山型の巨大な火山であった。その火山が約30万年前に大崩壊を起こし、崩壊物は南の甲府方面へと流れ下った。新府城のある台地は、この時の崩壊物が積ったものである。また、同じ八ヶ岳山麓の有名な観光地である清里の緩やかな高原も、同じ崩壊によって作られたものである。
このように火山が噴火や地震をきっかけにして大規模に崩壊し、その火山を構成する溶岩や火山灰などが山麓を急速に流れ下る現象を「岩屑流」と呼んでいる。その崩壊量は膨大で、八ヶ岳の場合、直径が数百mにも及ぶ溶岩の塊も流れてきたと推測されている。先に述べた新府城の城郭を乗せる小高い丘も、こうした巨大な溶岩の塊を核とした火山噴出物によって構成されると考えられている。
多くの犠牲者を出す岩屑流災害
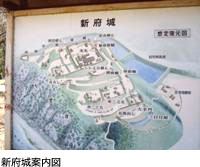
岩屑流は過去に何度も起きており、多くの犠牲者を出している。
江戸時代中期の1792年5月には長崎県島原半島の雲仙岳で、山麓の眉山(まゆやま)が地震をきっかけに崩壊した。崩壊物は岩屑流となって麓の島原城下を飲み込んだあと有明海に流れ込み、ここで津波を発生させて対岸の肥後(熊本県)を襲った。この岩屑流は「山体崩壊」とも呼ばれ、「島原大変肥後迷惑」として後世に伝えられている。この災害による犠牲者は15,000人以上とも言われる。
また、1888(明治21)年7月15日には、福島県会津地方の磐梯山で水蒸気爆発をきっかけに北斜面が崩壊し、この大崩壊で461人が亡くなった。北側の裏磐梯から見ると山の形が変わるほどであった。今でこそ、その風光明媚な景観が観光客を呼ぶ裏磐梯の桧原湖や秋元湖は、この時の岩屑流によって山麓に運ばれた磐梯山の崩壊物が川をせき止めてできたものである。
観光資源と災害は表裏一体
岩屑流の特徴は、流れるスピードが非常に速い点にある。その速さは、記録が残る磐梯山のケースで時速45~77km、速いものではおおよそ時速360kmと新幹線を上回る場合もあるという。いずれにしても、こうしたスピードでは岩屑流が発生してから避難することは極めて難しい。このため、噴火予報・警報といった事前の火山活動情報に留意し、火山活動による被害の危険性が高い区域には立ち入らないようにすることがまず求められよう。
魅力ある景観は災害の賜物
八ヶ岳、雲仙岳、そして磐梯山とここまで紹介した場所がどこもそうであるように、火山活動によって生じた地形はその激しさ故に観光資源として人々を惹きつける魅力をも秘めている。折しも春の観光シーズンとなり、こうした場所へ旅する方も多いことと思うが、景観の美しさを味わうと同時に、その地形を生む活動の激しさにも思いを馳せてみてはいかがであろうか。
(文・レスキューナウ危機管理情報センター専門員 水上崇)
copyright © レスキューナウ 記事の無断転用を禁じます。


