地震に備えた対策についてはよく聞いたことがある方も多いと思う。一方で、新型インフルエンザに備えた対策にはどのようなものがあるのだろうか。
今回は、地震と新型インフルエンザの発生による影響の違いを紹介しながら、新型インフルエンザ対策のポイントについてみていきたいと思う。
影響の違いを知る
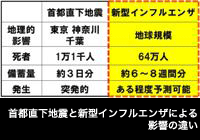
地震と新型インフルエンザとでは、発生によってどのような影響の違いが出てくるのだろうか。
【地理的な影響】
地震の場合であれば、震源に近い地域に限定された被害となるが、新型インフルエンザの場合は感染症であるため、その影響範囲は広範囲にわたる。グローバル化された現代社会においては、飛行機や鉄道などの交通網が発達したことにより、国境を越えた地球規模での感染爆発が懸念される。つまり、世界的な大流行(パンデミック)が発生した場合には、地震が発生した後のような「外部からの支援」に頼ることができなくなる可能性が出てくるのだ。
【備蓄の量】
何よりも頭を悩ませるのが「備蓄の量」。
地震の場合であれば、外部からなどの支援物資が届くことを想定して3日分の備蓄量が望ましいとされているが、新型インフルエンザの場合は流行が続くとされる約6~8週間分、最低でも2週間分の備蓄を確保しなくてはならないとされている。これは、感染の拡大や防止のため、屋内にとどまることを余儀なくされるためである。
このように、新型インフルエンザ対策というものは、地震対策とは全く異なるものであると理解できる。つまり、来るべき新型インフルエンザの大流行に対して、独自の対策を立てる必要があるのだ。
ひとりひとりの行動にかかっている
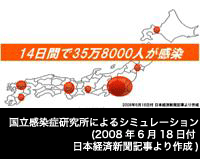
「感染しない・させない」ためには、何よりも「外出しない」ということが重要なポイントとなる。
1918年に発生したスペインかぜの際、米・セントルイス市では、市内で最初の患者が出てから2日後に、市長が緊急事態宣言を行い、学校や劇場といった人の集まる施設への外出などを禁止しました。この判断が功を奏し、セントルイス市では被害を最小限に抑えることができ、医療サービスや社会機能を維持できたのである。
一方、同じ米国でもフィラデルフィア市では市内で患者が出てから2週間、何の対策もとられることなく、市内ではパレードも開催された。その結果、死者数がセントルイス市の2倍にまで膨れあがり、医療・社会機能に大きなダメージを与えた。
つまり、被害を最小限に抑えるためのポイントは、人間の移動をどれだけ抑えることができるのかにかかっているのだ。
感染したことによって体調が悪くなった場合、近所の病院で診察してもらおうと考えるのが一般的であるが、新型インフルエンザが流行している状況下では「病院へ行く」という行為が逆に、感染を拡大させてしまうことにつながりかねない。感染が疑われる症状が出た場合は、お住まいの地域の保健所に連絡のうえ、保健所からの指示に従って行動することを徹底することが重要だ。
【ポイントチェック】
□ 新型インフルエンザの対策は、地震対策と全く異なる。
□ 広範囲にわたって大流行となった場合、外部からの支援物資は望めない可能性も。
□ 新型インフルエンザが発生すると、感染予防のために屋内にとどまることを余儀なくされる。
□ 屋内にとどまることを想定して、流行が続くとされる約6~8週間分の備蓄準備が必要。
□ 不要不急の外出を極力避けることが、「新型インフルエンザに感染しない・させない」ことにつながる。
次回は、個人で行う新型インフルエンザ対策について紹介する。
(文・レスキューナウ危機管理情報センター専門員 三澤裕一)
copyright © レスキューナウ 記事の無断転用を禁じます。


