2011年12月07日
2011年12月1日、国民生活センターは「急増するスマートフォンのトラブル」について発表した。
増えるスマートフォンに関する相談件数
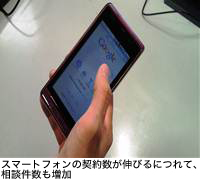
株式会社MM総研が発表した「スマートフォン市場規模の推移・予測」(2011年7月7日)によると、2011年3月末のスマートフォン契約数は955万件となり、端末総契約数1億912万件に対するスマートフォン契約比率は8.8%となったという。外出先でもパソコンのようにウェブサイトを閲覧でき、様々なアプリケーションソフトをダウンロードして機能を追加できるという利便性から、契約数は今後も伸びることが予想されている。 アプリケーションソフトには以前に本コラムで紹介した通り、ニュース・緊急地震速報・地震情報・地震計・気象情報・火山情報など、災害時の情報収集にも役立つものがある。中にはオフラインでも使用できるものもあり、東日本大震災の発生を受け、スマートフォンを災害時に役立てようと考えているユーザーもいることだろう。 しかし、国民生活センターによると、スマートフォンの特性についての情報が消費者に十分行き渡っていないなかで、従来の携帯電話の延長線上で利用され、トラブルが生じているという。
故障・不具合が多い
スマートフォンの契約者数が伸びるにつれて、その相談件数も増加している。国民生活センター等に寄せられた相談件数は、2009年度で564件だったのが、2011年度では1,789件(10月31日時点)と年々増加傾向にある。相談件数で最も多いのが解約に関する相談であるが、その要因となっているのが、スマートフォンの故障や不具合である。相談内容の上位20位をみると、3位:早期故障(28.1%)、6位:故障頻発(17.4%)、7位:機能故障(14.1%)、12位:作動不良(8.6%)となっている。
電池の消耗が早い
スマートフォン利用者からよく聞かれるのが、電池の消耗が早いという声だ。スマートフォン購入の際にパンフレット等で、連続待受時間や連続通話時間が記されているが、国民生活センターによれば、使用環境や利用頻度等条件によって異なるとはいえ、パンフレット等の表記とのあまりの違いに苦情が寄せられているとしている。 一方で、携帯電話会社の各ショップでは無料で充電サービスを行っているところもある。さらに電池の技術が進化すれば電池消費も抑えられるであろうが、購入する場合には、こうした現状があることを認識する必要もあるだろう。
消費者側も確認を
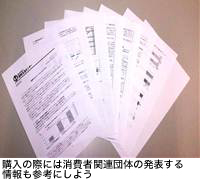
国民生活センターによれば、「メールやインターネットをあまり利用していないのに、パケット料金が上限額になる」・「通信制限があり動画が見られない」といった相談も寄せられているという。要因としては、スマートフォンの特性についての情報が消費者に十分行き渡っていなことをあげている。このことから、国民生活センターでは以下の通り消費者に呼びかけている。
- テレビコマーシャルなどの広告のイメージだけで判断せず、機能の特徴を十分ふまえて自分の利用目的にあった商品選択をしてほしい。
- 不具合がおきた場合には、どのようなときに症状がおこったのかを確認しておく。
- アプリケーションソフトの内容をよく理解しないまま、むやみにダウンロードしない。
- 海外に持っていく場合には、必ず日本国内で事前に設定方法や課金の方法を確認しておくこと。
- トラブルにあったら、最寄りの消費生活センターに相談を。
スマートフォンの歴史はまだ浅い。購入の際には、従来の携帯電話と機能や特徴が大きく異なることを、消費者側も十分に理解・確認することが必要となってくる。
(文・レスキューナウ危機管理情報センター)
copyright © レスキューナウ 記事の無断転用を禁じます。


