2009年8月11日午前5時7分、駿河湾を震源とするM.6.5の地震があり、静岡県内では最大震度6弱の強い揺れに見舞われた。この地震を受け、気象庁は想定されている東海地震との関連性についてデータの精査を行い、その結果を「東海地震観測情報」として発表した。
なぜ「想定される東海地震」が注目されたのか
地震発生直後から報道でよく見聞きする「想定される東海地震」とは何なのか。
内閣府中央防災会議の資料によると「想定される東海地震」とは、ユーラシアプレート(大陸側)にフィリピン海プレート(太平洋側)がもぐり込むことによって発生する「海溝型の地震」としている。この地震の震源域は駿河湾内を中心としたエリアで、マグニチュード8の地震が発生し、静岡県内の広い地域で震度7~6弱の強い揺れになるとされている。
仮にこの地震が、今回の地震と同じ午前5時に発生した場合、約7,900人~約9,200人が地震による揺れや火災、津波、崖崩れなどで死亡すると推計されている。
つまり、今回の地震で「東海地震」という言葉がクローズアップされた理由は、想定されていた駿河湾内で発生した大きな地震であったためなのである。
想定される東海地震ではない ―気象庁―
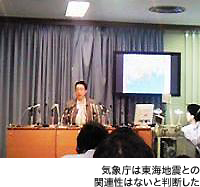
2009年8月11日午前6時45分過ぎ、気象庁は記者会見を行い、記者からの質問に対し関田康雄氏(気象庁地震津波監視課長)と横田崇氏(気象庁地震予知情報課長)は次のように述べた。(要旨)
Q.東海地震との関連性は?
A.想定される東海地震の規模と比べると今回の地震は小さい。また、発生のメカニズムも異なるため、想定される東海地震ではないと思われる。(関田氏)
Q.地震発生前にデータの異常はみられなかったのか。
A.データの異常はみられなかった。(関田氏)
Q.前回、静岡県内で震度6以上の地震があったのはいつか。
A.前回は1944年(昭和19年)の東南海地震である。(関田氏)
Q.地域住民はどのような点に注意すればいいか。
A.身の回りの点検などを行う必要はあるが、通常通りの生活を送ってほしい。(横田氏)
また、気象庁は史上初となる「東海地震観測情報」を7時15分、9時10分、11時20分の3回にわたって発表し、今回の地震及びそれに伴う地殻変動は、想定される東海地震に結びつくものではないと最終的に判断した。
なお、「東海地震観測情報」とは、観測された現象が東海地震の前兆現象であると直ちに判断できない場合や、前兆現象とは関係がないとわかった場合に気象庁から発表される情報である。
前兆現象が確認されたら…
東海地震は唯一、予知ができる可能性がある地震である。そのため、気象庁から東海地震に関する情報が発表され場合、国や自治体はその情報に沿った対応を行うことになっている。今回の地震を契機に、東海地震発生の予兆が確認された場合の各方面の動きなどについて確認することが、私たちには求められる。
| 1.東海地震観測情報が発表 | |
|---|---|
| (東海地震観測情報) | 観測された現象が東海地震の前兆現象であると直ちに判断できない場合や、前兆現象とは関係がないとわかった場合に気象庁から発表される情報 |
| 【行政】 | 情報収集連絡態勢がとられる |
| 【住民】 | 日常通りの生活を送る。(テレビやラジオなどの情報には注意する) |
| 2.東海地震注意情報が発表 | |
| (東海地震注意情報) | 観測された現象が前兆現象である可能性が高まった場合に気象庁から発表される情報。 |
| 【気象庁】 | 東海地震の発生につながるかどうかを検討する判定会を開催。 |
| 【行政】 | 救助部隊、救急部隊、消火部隊、医療関係者等の派遣準備の実施、住民に対する適切な広報。 |
| 【住民】 | テレビやラジオの情報に注意し、政府や自治体からの呼びかけや自治体の防災計画に従って行動。 |
| 3.東海地震予知情報が発表 | |
| (東海地震予知情報) | 東海地震の発生のおそれがあると判断した場合に気象庁から発表される情報。 |
| 【政府】 | 内閣総理大臣が警戒宣言を発表し、地震災害警戒本部が設置。 |
| 【行政】 | 津波や崖崩れの危険地域から住民避難や交通規制の実施、百貨店等の営業中止などの対策を実施。 |
| 【住民】 | テレビやラジオの情報に注意し、東海地震の発生に十分警戒する。内閣総理大臣の「警戒宣言」や自治体等の防災計画に従って行動。 |
家庭内の防災対策を確認!
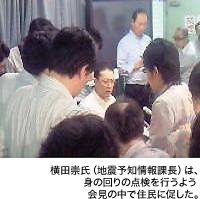
今回の地震では、多くの家屋で屋根瓦がずれ落ちたり、ブロック塀が倒れるといった被害が出たものの、最大震度6弱の地震にしては大きな被害が発生しなかった。この背景には何があるのだろうか。
2006年度、静岡県が県民に対して行った調査によると、「東海地震に関心がある」と答えた人は約95%にも及んだ。また、家具類の固定について「固定している」と答えた人は約63%となっており、地震に備える家庭が多いことが分かる。
こうした地震への関心の高さが、防災意識を高めることにつながり、今回の地震においても大きな被害が出なかった要因のひとつと考えられる。
まもなく9月1日の「防災の日」を迎える。今回の地震をきっかけに、家族の中でも防災対策について議論してみてはどうだろうか。
(文・レスキューナウ危機管理情報センター 三澤裕一)
copyright © レスキューナウ 記事の無断転用を禁じます。


