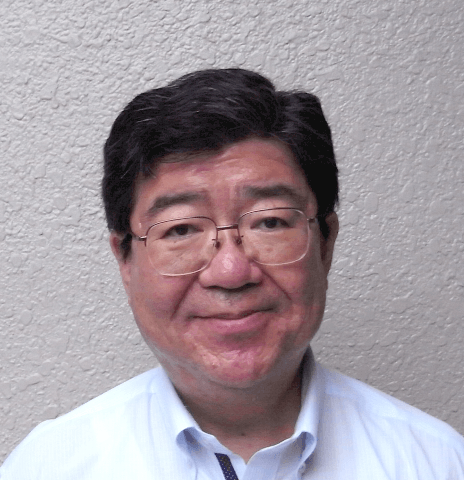チリの津波警報
チリのバルパライソという港町に津波の警報を出すセンターがあり視察に行きました。ちょうど、オペレーションルームを視察している最中に本当の地震がありました。実際にオペレーションしている様子を見ていましたが、地震を検知してから5分以内に、警報を出すか出さないか決断をして、警報を出したらそれが本当に正しい警報だったかどうかを判断します。5分以内に全て終わらせるというルールになっていて、非常にテキパキと対応されていました。結果的には、大きな地震が起きたけれども津波の心配はないという結論を出して、その判断で問題なさそうだという確認までを5分間で行っていました。
最初に大きな地震を検知して、彼らがシミュレーションでどのぐらいの津波が来るか予測をし、心配がなければ警報を出さないし、その後5分以内に観測をして30センチ以上の津波が3回観測されなければ「安全」だと判断し、警報を解除する仕組みになっているそうです。日本の防災の研究者と一緒に視察していたのですが、日本の防災の先生方は3回30センチの津波が来なかっただけで解除してしまって大丈夫なのかと質問されていましたが、チリの海軍の人たちの返事は非常に明快で、津波警報が出ている間は緊急車両も走れないルールになっていて、警報が出ていると救助活動もできなくなってしまうので、もちろんその後に想定外の津波が来る可能性はあるけれども、合理的に判断するのだということでした。実際にやってみてうまくいかなければルールを変えればいいという考えのようです。
津波警報の誤報があり人々は逃げたけれども、誤報でも誰も非難しなかったというお話をさせていただきましたが、合理的な考え方をするチリ人の人たちは面白いなという風に感じました。日本では、やはり心配なのでなかなか警報が解除されません。それはそれで安全ですが、逆に警報が出ている間身動きが取れないという問題があるので、この辺は日本も検討に値する話じゃないかなと思います。
濱口梧陵国際賞
江戸時代に安政南海地震が起きた時に、和歌山県の広川町というところで「津波が来るぞ」と言って濱口梧陵さんが稲の俵を積み重ねたものに火をつけて住民たちを高台に誘導したという逸話があります。この濱口梧陵さんを記念して、濱口梧陵国際賞というのがあるのですが、2023年11月5日の国連で決められた津波防災の日にチリの自然災害管理総合研究センター(CIGIDEN)という組織が濱口梧陵国際賞を受賞しました。
この自然災害管理総合研究センター(CIGIDEN)は、チリ・カトリカ大学など複数の大学の津波の若手研究者からなる組織で、人々にどうやって防災意識を持ってもらうかということを集まって共同研究しています。日本にはこのような組織がなかなかなくてユニークだなと思いました。リスクコミュニケーションと言いますが、一般の人たちに津波の恐ろしさ、どうやって避難行動に移すかということを粘り強くいろんな教材や漫画を作って啓発活動を行っている組織です。この活動が評価されて濱口梧陵国際賞を受賞したのですが、これは世界でもなかなか受賞者が少ない賞です。受賞記念パーティーが開催された時は、私もまだチリに滞在していたので参加させていただきました。皆さん、大変喜んでおられました。
日本の国土強靭化
チリには内務省の下に危機管理室というのがあります。これは1960年の大地震を契機に作られましたが、日本の内閣府の防災担当部局と同じようなところです。2010年の地震発生時の対応が不十分だったということで、緊急対応はきちんと出来ていましたが、発生前の防災や予防というところに重点を置くべきだということで、2023年に防災緊急対応サービス庁という風に大幅な組織替えを行いました。緊急対応だけではなく、町づくりや平常時の政策にこの防災を生かすという、まさに日本の内閣府でも防災に対する組織を作ってそのような対応をしているので、チリも同じ様な流れになってきたのだと思います。
日本は2012年に国土強靭化推進室というものを作り、2013年に国土強靭化基本法という法律が出来たのですが、これは東日本大震災を経て、これまでもある程度の災害を想定してそれに対して防潮堤や防波堤で防ぐという対応をしていたのですが、東日本大震災のような想定を超えるような大きな災害が起きた時にどうするのか、それを全部ハードな施設で防ぐのは難しいので、避難や住み方・町づくりなどから含めて変えていこうというのが国土強靭化の考え方です。
強靭というのはレジリエンスと言いますが、竹は風が吹くとしなります。しなるけれどもまた元に戻ります。風が吹いてもびくともしないような固い木でも、想定以上の風が吹くとぽきっと折れてしまいます。折れたらおしまいなので、折れないように、しなる。本当に大きな津波が来た時は防潮堤を超えて水に浸かってしまうかもしれないけれど、それでも命だけは絶対守る別な対策をとるというような、我々の防災の考え方もだいぶ変わってきています。チリも同じような変化をしてきているというのを見届けてとても印象的でした。