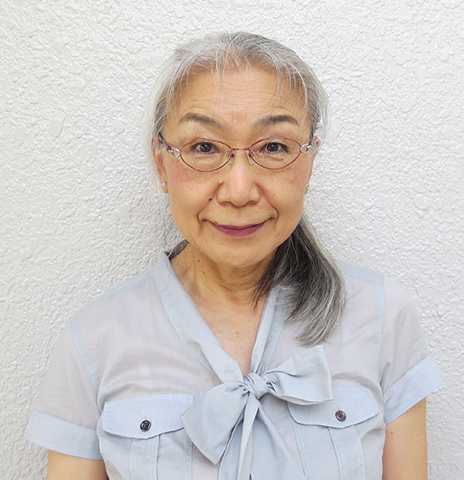感染症に対して保健所は何をする?
皆さんは様々な感染症、例えば普通の風邪や急性胃腸炎、季節性インフルエンザなどに罹ると医療機関に診療してもらいますね。症状が良くなれば、個人としてはよかったねと終わりになりますが、その感染症が実は地域に広がると困るというような場合には、診療した医師から保健所に届け出をもらって、保健所は地域に広がらないようにする役割があります。
社会への影響度などに応じて全数把握感染症と定点把握感染症に分類されています。例えば人に感染させる結核に罹った人を発見すると、その人の治療と経過観察、きちんと内服を見届けるというような手法をとったことで、結核は治療の進歩とともにこの疫学調査と拡大予防の施策によって早期発見すれば死ぬ病気ではなくなり罹る人も少なくなりました。
新型コロナウイルス感染症は、まさに感染拡大対応業務を毎日、直ちに、しかも長期間に渡り行わなければならない疾患でした。皆さんにとっても、保健所にとっても未曾有の過酷な体験でした。わが国では2020年冬の始まりに比べると致死率が30分の1以下に下がり、昨年5月には感染症法5類に分類される疾患となりましたが、当初から幾度も繰り返される感染の波がありました。その最中には、毎日大勢の患者の届け出を受け、全員の病状、持病の有無、家族や生活環境などを聞き取り、療養方法を決め、受診先を調整し、 ホテル療養先や受診先に自力で行けない人を送り届ける、濃厚接触者の範囲も判断するなど、たくさんの仕事がありました。
送迎は、この他にもタクシーで医療機関にかかった人がコロナと判明して自宅まで送ってくれとか、県外の空港ホテルまで迎えに行ってくれとか、大変な送迎業務もありました。自宅療養の人は療養期間中病状を確認します。中には連絡が取れなくなる人がいて深夜に安否確認に出向きます。診察してくれる医療機関が見つからない中、息苦しいと訴える人には血中酸素飽和度測定器を持って出向きます。ここで酸素飽和度が低いと分かればやっと入院させてもらえます。食べるものがない、解熱剤がないと訴える自宅療養者に食料や薬を運んだこともよくあります。
具合の良くない患者さんは時には不機嫌で、対応する保健師にきつい言葉で当たる人もいましたが、保健師はじっと耐えました。全数把握し報道発表するため、夕方に1日の集計が合わないと集計が合うまで、遅くまで確認作業が続きます。多くのクラスターも経験しました。これが感染の波が繰り返すたびに3年以上と続きました。
患者さんが亡くなった情報も届き、とても残念で悲しい気持ちになります。感染して良くなった方々にとっても、とても大変な体験だったと思います。保健所スタッフも感染者と共に耐え抜いた3年半でした。感染者への対応はもちろん、濃厚接触者が出歩くなどの苦情やあらゆる方面から対応への不備を指摘され怒られ、感染不安から何度も電話してくる方々など、朝から夜まで電話は鳴り止むことはありませんでした。
感染者の数が増える波を繰り返す度に、他部署の職員を臨時でお願いしたり、新たに雇用したり、人材派遣を依頼したり、あらゆる方法で人員を調整しました。しかし、中核となる職員をどうしても増やすことができず、苦しい思いはずっと続きました。
公衆衛生最前線の保健所は本来何をすべきか
感染の大きな波の最中には、中核となる保健所スタッフ数人は睡眠も生活時間も取れなくなりました。健康とは程遠い食生活です。スタッフの中には、シャンプーが切れて仕方なく容器を水でゆすいで使ったなど、笑えるような笑えない話もありました。
全国保健所のスタッフの中には体調を崩す者、離職した者もいたそうです。自治労の調べによると過労死ラインとなる80時間以上の時間外勤務は23%、200時間を超える人も1%いたとのことで、80時間を超える半数以上にうつ症状が見られたそうです。コロナ前からギリギリの人員配置であったことに多大なコロナ対応業務が加わり、過労死ラインを超える長時間労働をせざるを得なくなったとしています。
全国保健所長会協力の調査研究事業で「健康危機管理業務における自治体職員の健康確保に向けた提言」がなされました。それによると過重な労働時間の是正、労働衛生、職員が誇りを持って活動できる指針、ストレスを和らげる方策、保健所が担う業務範囲の確認、危機管理対応における指揮調整の徹底を挙げています。私が思うに、責任はあるが人事権がない状況での業務は大変きついと思います。
全国保健所長会のホームページには、2022年秋の総会でこの課題を取り上げ、どのように危機を乗り越えたかというシンポジウムの記録があります。また、保健所は多くの方々の協力を得て、持てる力で精一杯やってコロナ禍を乗り越えた事実と教訓は次の感染症危機にきっと活きるはず、希望となるはずと信じます。辛い記憶を封印せずに、向き合って次に活かすことがとても大切だと思います。
全国のどの保健所でも経験したことと思いますが、学校やその学校の寮、あるいは障がい者・高齢者の施設、病院などでもたくさんのクラスターが発生しました。当時は夢中でしたが、医師の専門家や看護師、事務の方も含めた県のチームと協力し、現地にも出向いて、クラスター対策として施設の方と一緒に予防・拡大防止の業務をいたしました。