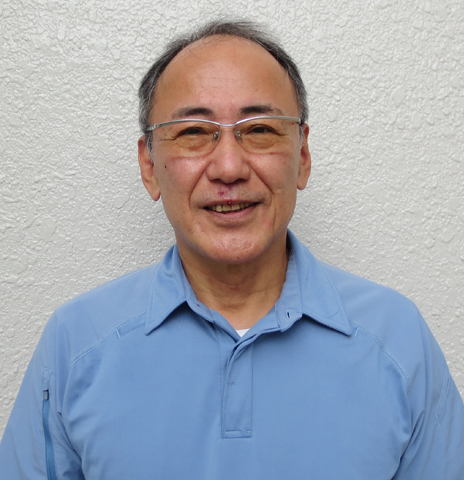安全基準
様々な企業や自治会での困りごとをよく聞くのですが、その中の1つとして「自分たちの建物が大丈夫なのかな」という質問があります。災害直後に荷物を取りに帰ってもいいのかどうか、その時の基準がなくて困っているとのことです。例えば鉄筋コンクリート造のビルの例を申し上げますと、壁にはっきりとXの形をした亀裂が入っている場合は倒壊の危険性があります。速やかにそこから退避して、消防や警察、自衛隊に託すなどの基準を作ることが大事です。基礎はしっかり残っていて、壁の亀裂や配管の損傷、窓ガラスが割れている程度ならば、救助のために短時間進入は可能などと予め決めておき、現実の現場に合わせて判断する必要があります。
無線機の活用
救助や災害対応として無線機を購入されている企業や自治会も多いと思います。購入されたら何度も何度も練習して、本番の時に使えるようにしておくことをお勧めします。訓練のお手伝いをした際など、正直言ってまともに無線機を使える方を見たことがありません。無線機を使っている時に、だらだら喋る方、何を言っているのか分からない方が結構おられます。きちんと使える方は元自衛隊員、消防士、警察官や警備業務、ビル管理、イベント関係のお仕事の方々です。地区や社内に居られるのであれば、相談して有効な無線の取り扱いを学ばれると良いでしょう。
また、無線機の練習をするときは軍や消防が使用するフォネティックコードも一緒に勉強すると良いでしょう。無線通話などにおいて重要な文字・数字を正確に伝達するために定められた独特な言い回しや言い方になります。
無線では、「A」と発音しても「D」に聞こえたり、「1」を「7」と聞き間違えたりします。そこで「A」はアルファ、「B」はブラボー、「C」はチャーリーといった具合に話す事により、正確な情報通信が確立します。
ゾーニング
無線で負傷者の位置を教える際に、相手がその場所に詳しいとは限りません。そんな時は、事業所やオフィスの配置図、地域の地図を用意していただき、縦横に何本か格子状の線を引いて、細かく区切ります。そして、縦ラインと横ラインにアルファベットと数字を付与します。そうすると、「C-4に負傷者あり」などと伝えることができ、2秒もかからずに場所を共有する事が出来ます。
無線通信も長くならずに効率よく活動を行えるようになりますので、ぜひ練習の際に使っていただきたいと思います。
東急スタートキット
災害対応で一番にやるべきなのは災害対策本部などの本部機能の立ち上げです。とはいえ、何をどうしたらいいのかと悩まれている企業、団体があることも理解できます。どこかの真似をするのも良いことですが、違う地区、違う企業では上手く動けないとの声も聞きます。
FMサルースを運営されているイッツコムの親会社である東急さんでは、事業モデルが多岐に渡り色々とご苦労されてきたようで、そこからシンプルだけど効果的で、これから始める方のスキルもアップされる災害対策本部を立ち上げるためのキットを開発されました。
初動を間違えたら大変ですが、東急さんのスタートキットは必須・共通部分は事前に作り込まれているので、最終的には楽しくみんなを巻き込んでともに学び考え、最適な災害対策本部の立ち上げを可能としてくれます。ご興味のある方は東急さんへお問い合わせをされてもよいかも知れません。
備蓄物の見直しと防災への意識改革
災害に向けて、包帯やガーゼ、マスクなどを備蓄されている方も多いと思います。しかし、これらは未来永劫使えるものではありません。例えば、滅菌ガーゼというものがたくさん売れていて、大きな箱で備蓄されていますが、実際に開けてみると「何年前のものですか?」というようなことが見受けられます。メーカーによって異なりますが、一般的に滅菌ガーゼや絆創膏などは概ね3年程度しか持たないと言われています。N95や防塵マスクも保存期限は大体5年と言われています。それを過ぎてしまうと性能が落ちたり様々な問題も起きてしまいますので、ぜひ1度備蓄の見直しをしていただきたいと思います。
先日、ある工場にお邪魔して応急箱を見たのですが、包帯がボロボロになっていて黄ばんでいるようなものがありました。それが現実なのだと感じているところですが、皆さんのご家庭やオフィスの備蓄品を定期的に確認していただいて、期限が過ぎているものを見直していただくということも大事なポイントです。いざという時に使えないものを持っていてもゴミでしかありません。
3.11東日本大震災の時に国土交通省東北地方整備局が「備えていたことしか役には立たなかった。備えていただけでは十分ではなかった。」という言葉を残されています。これを教訓として、普段から準備をしっかりしていただき、細かいことにもちょっと気を付けていただければ、それほどお金も労力もかけずに改善できていきますので、ぜひみんなで見直していただきたいと思います。
1つお願いしたいのは、災害や防災に関して、よく企業などでは誰か1人に丸投げしてしまって、その人だけが苦労しているという場面をよく目にします。また、予算をつけてもらえないという話もよく聞きます。それを1度やめていただき、これは投資であると考えを改め、自分たちの企業を守るもしくは地域を守るということに、私たちの防災の能力を、このようなラジオ番組を通じて学んでいただきたいと思います。
もし、もっと勉強したいなと思われる方がおられましたら、2011年の12月に出演された東京大学生産技術研究所の沼田先生のところでスタートされているDMTC災害対策トレーニングセンターというところがあります。そこでは、ちゃんと正しい知識を持っていただくことが可能で、さらに搬送の技術、血を止める技術なども教えてくれます。さらに上級までいくと、誰かに教えることもできるようになっていきますので、ぜひご興味のある方はコンタクトをとってみてください。皆さんの役に立てればいいなという風に思います。