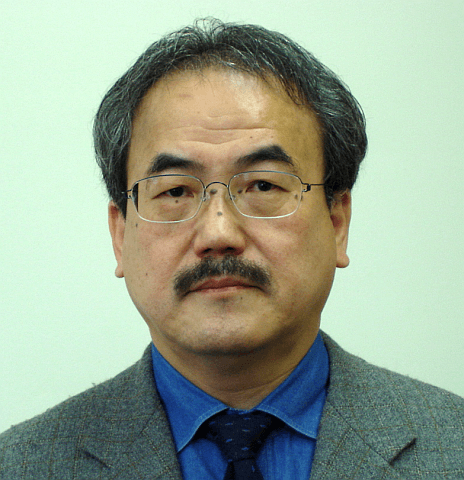巨大都市における特徴的な被害
東京のような巨大都市で特徴的な被害の1つは、実は通勤にかかわる人間の行動そのものの被害というのがあります。阪神大震災は早朝5時46分の地震でした。勤め人も学生さんも皆、家にいて被害を受けました。電車は止まり、道路は壊れ、交通は全部ストップしました。結局その地震があった日には出勤が非常に困難で、職場まで行けた人は1割とも2割とも3割とも言われています。
では、もし地震が夕方の6時ごろに起きていたらどうなっていたか。例えば東京の千代田区というのは、夜間人口は3万人ぐらいしかいない。昼間は120万人がいます。この120万人が、さあそろそろ仕事が終わって帰ろうというときに地震が起きた。大きな地震が起きますと、鉄道はすべて止まります。被害があるかどうかを確認するまでは再開しません。そうすると地下鉄もJRも高速鉄道も全部止まってしまいます。もちろん道路は緊急車両以外、通行禁止になりますからバスも走りません。交通がすべて止まる状態の中で、家に帰れなくなる人がたくさん都心に発生するわけです。これは同じ大都市でも神戸では発生しなかった事態です。つまり、神戸で発生した「出勤困難」の裏返しで、出勤した人が家に帰れないという事態が発生する。これを「帰宅困難者」と言います。

阪神大震災の後は帰宅難民という言い方もされていますが、東京都の被害想定では、東京23区で約400万人が、家に帰れなくてうろうろするということになります。このうちの大部分が実は会社の就業者、仕事をしている人です。それ以外に学生さんとか、あるいは買い物その他で街に出ていた人も含まれています。しかし、400万人というのはすごい数です。横浜市の全人口ぐらいが家に帰れなくて、東京をうろうろする。その大部分が都心、副都心にいます。災害時の様子をイメージすると、都心、副都心を取り巻いて木造の密集した市街地が東京にはありますので、木造密集市街地で火災が発生して燃える。それに取り込まれるような形で、都心あるいは副都心には300万人もの家に帰れない人が残ってしまう、そういう被害の状況というものは、本当に東京のような大都市でないと発生しない、非常に特徴的な都市災害と言えると思います。
それだけであればまだいいのですが、それ以上に自宅が近くにある徒歩帰宅者が多数いるのです。それらの人が一斉に建物から避難する、路上にあふれると、最も怖いのはパニックです。人が不安に陥る結果として、とんでもない、予想もしないような行動を起こしたりしてしまうことがあります。それが非常に怖い現象です。大部分の人が会社の従業員だとすると、実は帰宅困難者問題というのは企業の防災問題なのです。企業で従業員に、災害の後も落ち着いて行動してもらうような対策があれば、帰宅困難になってもパニックにならない。しかし帰宅困難者にとっては、もう1つ、「我が家は大丈夫か」というのが大きな不安になります。これに対してどう応えるかも大きな課題です。
災害時のパニックを回避するには
パニックの原因というのはいろいろありますが、帰宅困難者という立場で被災してしまうと、まず家のことが心配になると思います。家族の安否を確かめたい。家族も同様にお父さんの安否を確かめたいということになります。今は携帯電話の時代なのですが、みんなが一斉に携帯をかけると、それだけで電話はパニックになります。そうなると携帯は、もうつながりません。そこで、阪神大震災の後にNTTでは、災害伝言ダイヤルというシステムをつくっています。これは、この後の東海水害などでも活用されたシステムで、171という番号だけを覚えておけばいいと思います。災害伝言ダイヤルが開設されましたということになったら、電話で「171」を入れると、音声ガイドで、メッセージを入れたりメッセージを聞いたりすることができるようになります。これを使って家族間の安否確認ができるので、むやみに携帯をかけまくらないで171を使ってください。

もう1つは、家族の安否が直接分からなくても、自分の住んでいる地域がどんな被害になっているのか、安全なのか、これが分かると非常にいいです。このFMサルースもそうですが、現在は各地にコミュニティーFMができてきていますので、こういうコミュニティーFMがネットワークを結んで、それぞれの地域で防災情報を流していくと、自分の住んでいる街がどういう状況かというのが分かりますから、これも安心につながる、パニックを避けることにつながっていくということです。
それから、実はもっと大事なのは「どんな地震がきても我が家は大丈夫」というくらい、我が家の防災をしておくということです。「転ばぬ先の杖」という言い方もありますが、常日ごろから「我が家は大丈夫だ」と思っていない人は、どんな情報を聞いてもパニックになります。「どうみても我が家は隣よりも先に壊れる」ということであれば、どうにもなりませんので、一人ひとりが耐震診断をして、自分の家を大切に、耐震補強することが必要です。
それから家族間の連絡の取り方ですとか、あるいは災害の後の生活のための準備をしておく。そういう「防災達人家族」というのを、それぞれ家族全員で工夫して作っていくと、災害時に慌てなくて済むと思います。これが一番大事なことかもしれません。
災害に強い街づくり
災害に強い街とはどのような街かを考えていきたいと思います。地震災害が発生すると、実際には被害が出た街と、出ない街という差が出ます。同じ揺れでも全部一様に被害が出るかというと、必ずしもそうでもない。それから災害の後、どういうふうに回復していくか、あるいは災害にどう対応していくかというところでも、「災害の後すぐにみんなで助け合って、被害を乗り越えていく街」と、「災害後にうろうろしているだけで皆で助け合うこともできない街」があると思います。災害に強い街というのは、2つの意味があります。1つは同じ強さの地震がきても、被害が少なくなる街、被害を出さない街、これは災害に強い街です。もう1つは、被害が出ても、それにうまく地域の人たちが対応して、すぐにみんなで助け合って災害を乗り越えていく街。これも実は災害に強い街です。

そういう災害に強い街をつくるためには、実は2つの取り組みが必要です。1つは被害を減らすために、街の弱点を直して強くしていくという「防災街づくり」の取り組みです。多くの場合、それは建物を地震の揺れに対して強くするとか、火災が発生してもすぐには燃え広がらないように燃えにくい街にするとか、あるいはブロック塀を生け垣に直して、大きく揺れても倒れないような、そんな街に改善していく。これが被害を軽減するための防災街づくりということになります。しかし、これからの街づくりは木造住宅を全部作り替えるという時代ではないと、お話しいたしましたが、そうすると、どんなに被害軽減を頑張っても、少しは被害が出てしまうだろうと思わなければいけません。ですから、出た被害に対してはみんなで取り組んで被害の拡大を防ぎ、被害に負けないで、みんなで被害を乗り越えていく、そんな街です。そのためには実は準備が一番大事です。災害が発生した後、どのように対応するかという準備です。もっと悪い事態になると、避難も必要になるかもしれません。しかし、これから高齢化時代に入っていきますと、避難といっても、実はすぐに避難できない人がたくさん地域に増えてきます。その中で何が必要かというと、みんなで助け合って街を守るということが大事になります。そういう人と人との関係とか、人と人の取り組みによって災害を乗り越えていく、そういうコミュニティーづくりにつながるような街づくりも、災害に強い街づくりとして非常に重要になってきます。よく、ハード、ソフトという言い方をしますが、建物を強くするとか道路を造るというのは、いわばハードの防災街づくりになります。しかし近隣での人と人との関係をつくるとか、社会の仕組みを災害に強くするというのはソフトの防災街づくりですが、これからの高齢化時代を考えると、このソフトの街づくりというのも、非常に大事になってくると思います。