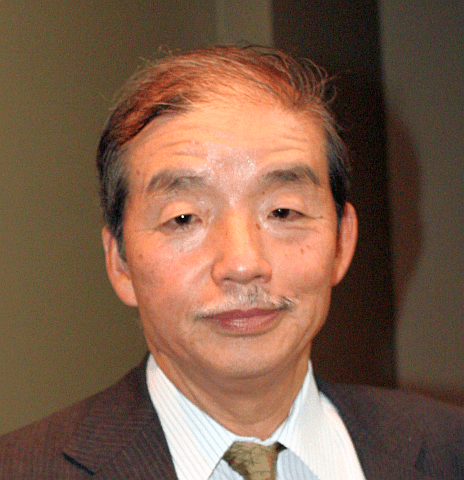最近の地震災害の特徴
最近の地震災害
阪神淡路大震災では、都市災害のすべての特徴が出ました。その後の中越地震では中山間地の災害です。複合災害でもありました。地震の数日前に雨が降り、地盤が緩んでいる状況での地震被災です。中越地域は非常に地滑りが起こりやすく地盤の弱いところの被害は大きくなります。山古志村に代表されたコミュニティー力が注目されました。その後、2005年に福岡西方沖の地震があり、マンションの被災、ビルの外壁の落下、窓枠の落下などが注目されましたし、マンション住人がドアが開けられない状況が発生しました。中越沖地震では刈羽原子力発電所の被災があり、リスクマネジメントがきちんとできていたのかが問われました。さいわい、原子炉は自動停止し、安全上の問題はありませんでした。地震と原子力汚染の複合災害とならないように徹底した対策が進められています。また、岩手宮城内陸地震が発生し、山間地で大きな被害を受けています。
| 地震被害 | 特徴 |
|---|---|
| 1994年阪神・淡路大震災 震度7、死者6433人 |
都市直下型災害、老朽家屋の倒壊、家屋家具倒壊被害、火災一斉発生、大量避難者、瓦礫処理、仮設住宅問題、孤独死、コミュニティ崩壊、ボランティア元年、生活インフラ被災、避難所問題、復興長期化 |
| 2004年新潟県中越地震 震度7、大規模余震続発、死者46人 |
中間山地被害、山村孤立、雪害等複合災害、地盤災害、地すべり災害、情報課題、地域防災計画未整備、耐震補強確認、コミュニティ力、広域支援、避難所問題 |
| 2005年福岡西方沖地震 震度6弱 死者1人 |
想定外活断層地震、玄海島被災、マンション被災、ビル外壁・窓被害 |
| 2007年能登半島地震 震度6強、死者1人 |
インフラ被害、能登有料道路決壊、孤立集落発生、地盤悪い地区の家屋倒壊高い |
| 2007年中越沖地震 震度6強、死者14人 |
刈羽原子力発電所被災、リスクマネジメント、耐震設計見直し、豪雨との複合災害、老朽家屋の倒壊 |
| 2008年岩手・宮城内陸地震6強、死者22人 | 火山帯山地被害、過去最高の強震動、山崩れ、大規模土石流、土砂ダム、集落孤立、建物被害少ない |
地震災害等から学ぶこと
大規模災害は被害状況把握に時間がかかる

大規模な災害になるほど被害状況の把握は遅れます。被害の規模が分からないと、どうしても対応は遅れます、早朝や夜間の場合は、なおさらです。阪神・淡路大震災では、午前5時45分に起こり、死者・行方不明者数の状況は、発災後6時間まではほとんど把握できなかった。24時間後には約6割が判明します。倒壊家屋の被災情報も同様に大体6時間後から入ってくるのですが、人的被災情報とその救出対応を優先し、建物被害の状況把握は遅くなるのです。3日後で人的被害の約7割がようやく把握される状況です。しかし、建物被害は、1割程度でしか分りません。
新潟県中越地震は、午後5時56分発災し、暗がりで被災が広域に及微、道路が寸断され、被災状況の把握は、さらに遅くなりました。1日経って、死者・行方不明者の把握は全体の半分以下、全壊家屋の倒壊状況の把握は、1%にも満たない。3日後で、人的被害はほぼ9割が判明する。しかし、全壊家屋は14%、公共施設建物被害の判明は4%でしかない。被害の実態が判明するのは、倒壊家屋が1ヵ月後、公共施設等の被害の実態は、3ヶ月かかりました。
公助の限界と自助・共助の認識
倒壊家屋や倒れた家具の下敷きになった人の救出は、緊急を要します。時間の経過とともに生存率が急激に低下する。心臓停止後約3分で50%が死亡し、水分が取れなければ72時間が限度です。阪神・淡路大震災では、自治体職員の参集ができず、救急救出ができず、多くの人命が奪われた。
これが教訓となり、政府は、防災対策の見直しを行い、公的な救助の限界と自助、共助の重要性が認識され、「減災」の考えのもとに市民と地域の関係者の協働による「共助」を中心とする方針に変換したわけです。「今後の防災対策は、住民・企業が自らを災害から守る「自助」と、地域社会が互いに助け合う「共助」と、国、地方公共団体等行政による施策「公助」との適切な役割分担に基づき、住民、企業、地域コミュニティ・NPO及び行政それぞれが相応しい役割を果たすことが必要である。」(平成14年度防災白書)
イマジネーション能力の向上
大規模災害への備えとして、各自の災害イマジネーション能力の向上が必要です。過去の災害教訓を学び、そこで起こりうる災害の状況を想像し、防災行動を起こすことが必要です。
平成16年の近畿・北陸豪雨時には、堤防が決壊するなど、大きな被害に見舞われました。降雨量は、三条市で2日間で431mmを記録しています。とんでもない雨量で、住民は、浸水を想定していました。
当時の三条市など地域住民の避難行動の意識をみると、20~40%の人は、2階に避難しています。浸水しても避難所よりも自宅の2階に避難すれば問題なしという意識があります。
| 被災地 (降水量) |
事前の防災行動 | 避難勧告 入手率 |
避難行動 | 避難しない理由 |
|---|---|---|---|---|
| 三条市 (431mm/2日) |
何もしない66% 家財移動25% |
21% | 2階避難37% 避難所10% |
2階に逃げれば助かる41% |
| 福井市 (285mm/2日) |
TV情報46% 家財移動42% |
28% | 2階避難21% 避難所21% |
- |
| 豊岡市 (298mm/3日) |
TV情報収集40% 家財移動29% |
87% | 2階避難40% 避難所15% |
2階に逃げれば助かる51% |
これらの地域は、水害常襲地域で、堤防の破壊もあったところです。住民は、浸水には慣れており、住民は自分たちで状況を判断し、行動してきたのです。しかし、大半の住民は、破堤を経験していません。行政も破堤の可能性は考えていなかったと思われます。そのため、避難勧告に破堤の可能性は伝えていません。破堤すれば、2階以上に達する浸水が予想されます。木造住宅では、破堤すれば、倒壊の危険性が高くなります。
災害状況は、時間経過とともに進化し、悪化することをイメージすることが必要です。自分だけは被害に遭わないという意識が妨げにもなっています。災害に対する想像力の問題、行政・住民・専門家それぞれのイメージギャップなどが、避難勧告が発令されても、避難行動をしない理由となっています。