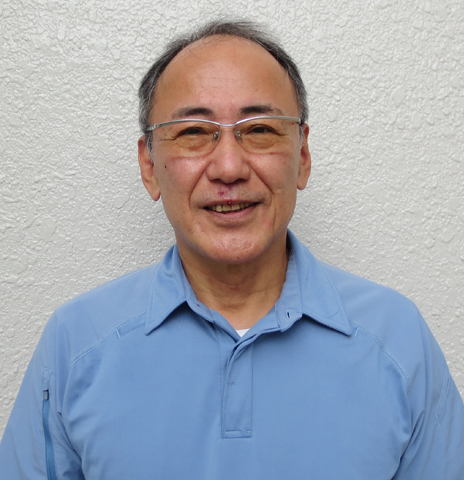スキルを身に着けよう
防災について考えていく上で、皆さんにぜひスキルを身に着けていただきたいと考えています。実際に危機管理行動をするといっても、知っているだけではカラダは動きません。現在は、様々な団体やいろんな方々が一生懸命に防災や危機管理について啓発活動をされているので、みなさんは「知らない」から「知っている」という段階であると考えています。災害時に、生き残るためまた仲間を助けたいという時のために、「知っているからやれる」と基本的な知識とスキルを身に着け、実際に行動出来るというレベルになると良いと思います。もし可能であれば、「やれる」からさらに一歩進んで「教えられる」というところまで行っていただけると、みんながハッピーになるだろうと考えています。
例えば、地震や災害が発生して、家族や同僚などが建物内に閉じ込められてしまったと想定して考えてみましょう。その際に、「大変だ!助けなきゃ!」と、すぐにドアを開けて救出しようとするのが普通のことだと思います。もしも中で火災が発生している状況だったとしたら、ドアを開けたことによって空気が入ってしまい爆発してしまう可能性があります。屋内火災が発生しているかなどの簡単な確認方法がありますので、ぜひ知っておいていただき、出来ればいざという時にやれるようになっておいて欲しいです。
屋内火災の確認は非常に簡単で、手袋をして、利き手ではない方の手の甲でドアや壁を、床側から天井側に向かってゆっくりと動かしていきます。熱さを感じる、または床側は熱さを感じないけれども天井側は熱いとなると、中で何かが燃えている可能性があります。さらに、ドアを少し開けて様子を見る時にも利き手ではない方でドア開けます。入口正面にいると爆発に巻き込まれてしまう可能性がありますので、扉の蝶番の方で腰をかがめて小さくなります。空気を少しずつ入れて様子を見て、問題がなければゆっくりドアを開けて全開にします。
このような方法を普段から知っていても、災害時には忘れていたり、頭が真っ白になってしまうこともありますので、体が自動的に動くようになるまで練習していただくことが大事だと思います。平時に出来ない事は、有事にも出来ないことは明白です。知識とスキルは誰かに盗まれるものでもなく自分の財産になります。ぜひ周りの人に伝えていただいて、みんなで強くなっていただきたいなと願っています。
災害時のメンタルヘルス(高強度なストレス)
災害時に私たちがつい見逃してしまうのが心の問題です。災害現場で血を流したり怪我をすることは考えられますが、実は同じように心も怪我をしてしまうということが分かっています。心を怪我した時に、適切な対応をしないと取り返しのつかない病気、PTSDと言われるような精神上の問題を抱えてしまい社会復帰が出来なくなってしまったり、場合によっては自殺をしてしまうことも考えられます。
私たちにできることは、仲間を良く見てあげておかしいなと思ったらプロのお医者様や行政機関につないであげることです。災害現場で普段は見ることのないような怪我を見たり、声を聞いたりすると心が反応します。それを急性ストレス反応と言って、熱いやかんに触れると「あちっ!」となるように、ほぼ全ての人がなります。その急性ストレス反応をそのまま放置すると、今度は惨事ストレス障害(ASD)と言われる心が深く傷つけられている状態になっていきます。その状態が1か月以上継続してしまうと、今度は心的外傷後ストレス障害(PTSD)という、非常に厄介な心の病に向かっていってしまいます。
ここで大事なことなのですが、心のケアについて理解していない方にとっては、何が自分にとっておかしいのかということが分かりません。周りにいる方がよく見てあげて、おかしいなと思ったら行政機関や各地域の精神保健福祉センターなどへ繋いでいただくことが必要です。災害派遣精神医療チーム DPAT(ディーパット)という組織もありますので、どのような活動をするのかなどぜひ知っておいていただきたいなと思います。
もう1つ大事なことがあります。心の弱い人を現場に入れない事です。企業や地域の防災団体などで、「部長だから、総務だから担当だからよろしくね」と、責務を押し付ける組織が散見します。心の耐性などを知って適材適所化されることをお勧めします。企業などでは安全配慮義務というものもありますので、リアルな訓練をして「これは苦手です」「血を見るのが嫌です」という方が出てきたら、法令で定められている救護班のようなところには行かないようにしてあげて、その方の心が傷つかないように守ってあげてほしいと思います。
こころの問題に対して、いくつかの耳寄りな情報もあります。こころが傷ついた方へのサポートに関しては、無料でマニュアルがダウンロードできるサイトがあります。ひとつは、心の応急手当「サイコロジカルファーストエイド」という有効なマニュアルがあります。「サイコロジカルファーストエイド」で検索していただくと、厚生労働省のサイトからWHOのとても分かりやすいマニュアルがダウンロードできます。
兵庫県こころのケアセンターのサイトからはアメリカ国立PTSDセンターの「サイコロジカルファーストエイド」のマニュアルがダウンロードできます。特に小さなお子さんをお持ちの方はマニュアルを一読されることをお勧めします。特に重要なポイントをお伝えしますと「言葉」です。例えば、お子さんを失ってしまった被災者の方に「あなたは生きていてよかったね」と言った瞬間に、「じゃあ私の子供は死んで当然だというの!」と相手をさらに傷つける事になります。言葉の使い方や態度、どのような準備をして接触すればいいのかなどを教えてくれるマニュアルです。
心のケアの問題に関してお伝えしなければいけないことはいくつかありますが、災害精神医学という分野の有名な教授も「絶対に強制してはいけません」と言われています。何を「強制しない」のかというと、「辛いね」「大変だね」「大変だったら私に話して。聞いてあげるよ」という強制アプローチです。傍目にはいい人に見えますが、やっていることは悪です。やっている本人は良かれと思ってやっていると思いますが、全く逆で最悪な事をしている状態です。ぜひ「サイコロジカルファーストエイド」を一読いただき、いざという時に自分の家族や仲間を守ることが出来るスキルを持っていただきたいと思います。