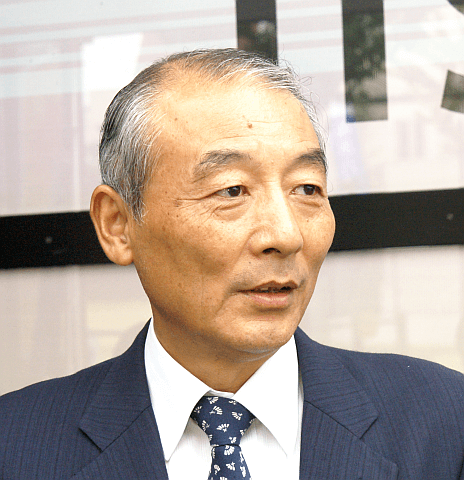防災は「まちづくり」から
防災には、まず「まちづくり」です。これは、私は平仮名で書きます。街路の街で、街づくりとおっしゃる方もいますけれども、それはハードな街づくりということなので、私は意識して平仮名で「まちづくり」と言います。この「まちづくり」ですが、防災、災害に強いまちをつくるということは、当然、広い意味でいうと「まちづくり」の一部であるということです。
まちを構成しているものは何かということになりますが、当然、ハードとしては建築物があります。建築物は「健康な建築」でなければなりません。「健康な建築」という考え方は、私の発案ではなくて、もう亡くなられましたが内井昭蔵さんという建築家が『健康な建築』という本を書かれていますので、詳しくはそちらをお読みになっていただきたいと思います。
健康な建築が集まって健康な都市になるということです。そして健康な都市に住む方は、健康な住民でなければならない、健康な市民でなければならないということです。ここで言う「健康」というのは、WHOの健康の定義で言う健康よりは、もっと広い意味で、都市に住む方が「自分にとって住みよい町だ」という思いを持っているということです。ここに何年も住み続けたいまちだという思いが、どんどん募ってくるようなまち、そのような方が住んでいるまちというのが、健康な住民が住むまちという意味なのです。
これをもう少し分かりやすく申し上げますと、健康な地域社会がなければ、いざというときの地域防災もできないでしょう、ということです。健康な地域社会でなければ、頭で分かっていても、いざというときにはなかなか対処できないでしょう、ということになるわけです。
生き生きとしたコミュニティー
健康な地域社会ということの1つの例を申し上げますと、阪神淡路大震災の時に報道されましたのでご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、神戸に真野地区というところがあります。ここは毎年正月になりますと、もちつき大会を行っておりまして、もちつき大会でついたもちを、一人暮らしで寝たきりの方の家に子どもが配達するという仕組みがあります。その背景には、自治会の役員の方が「どこに子どもがいて、その子どもがどこの家にもちを配達しなければならないか」ということを把握しているということがあります。自治会として「今年はあの家の方が寝たきりになった、一人暮らしになった」という最新の状況を把握しているというような、生き生きとしたコミュニティーがあるわけです。そういった背景があって、阪神淡路大震災の時に、とっさにバケツリレーで消火をしました。消火にどれくらい効果があったかどうかは別として、とっさに地域社会としてバケツリレーが行われたというのには、そういう健全な生き生きとした普段のまち、コミュニティーがあったということです。

防災のまちづくり ~細街路の整備~
防災はまちづくりの一部ということで、具体的にどんなことをしたかということを、私の実体験も踏まえてお話しします。1つには細街路の整備ということがあります。細街路というのは幹線道路と違いまして、日常そこに住んでいる方が使う細い路ということなので、とても大切なものです。細街路を整備するということにおいて、宮城沖地震で有名な教訓があります。地震によってブロック塀が倒れ、そのブロック塀の下敷きになって犠牲者が出たわけですが、私がここで申し上げたいのは、そういうブロック塀が両方に林立しているような地区にある細街路は、仮に犠牲者が出なくても、それが倒壊すれば避難道路として使えなくなるということです。細街路の整備というのは、普段の生活の動線を確保するということだけではなく、非常のときにも避難路を確保することにもなります。といいますのは、現在の避難の仕組みというのは、広域避難道路以外は自由避難ということで、避難路については住んでいる方が選択しなさいということになっています。一定の場所に出ますと広域避難道路があり、そこは整備するという仕組みになっていますが、細街路が整備されていなければ避難の仕組みというのは成立しない、という防災のシステムになっています。

そういう意味で細街路の整備というのは、普段、皆さんと行政と住んでいる方が、いろいろな意見を交換しながら「どこの細街路は優先的に整備しましょう」とか、「ここはやむを得ませんから拡幅しましょう」とか、あるいは「拡幅しなくても、今の広さでも細街路に沿ったブロック塀や建物が倒壊しなければいいじゃないか」とか、細街路の整備というキーワードのもとに、行政と住民の方がいろいろ話し合いをしていく必要があると思います。
実際にできた例としてお話ししますと、JR東日本の渋川という駅ですが、この駅の近くに住民の皆さんで申し合わせをし、連携してセットバックした建物があります。建物位置を後退させることで、普段、皆さんが生活できる通路を確保したり、そこにせせらぎまで流しているという立派な空間があります。これが東京でできるかどうかという話は別としまして、幹線街路ではなく、細街路に相当重点を置いて「まちづくり」として取り組む必要があるという1つの例です。
実際、東京都の古い町並みは密集しています。災害時には建前としては自由避難方式という方式を採っていますが、実際には自由避難で右に行ったら塀が倒れていた、左に行ったら建物が倒れていたということで、右に行っても左に行っても幹線の広域避難道路まで行き着かない場所があるのではないかということを、一番心配しているわけです。その時「ここは倒れる塀かもしれませんよ」というような不利益情報といいますか、行政はそういう不利な情報をきちんと地元の方にお出しする勇気が必要だと思われます。