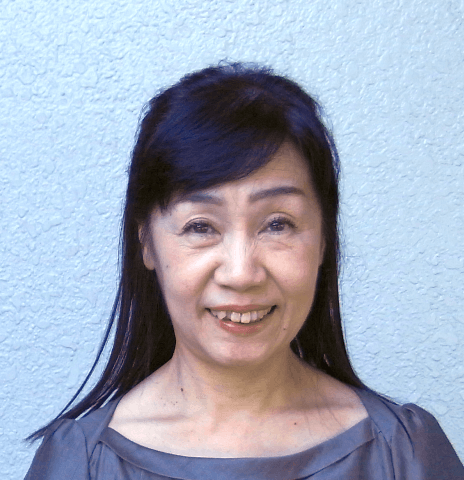被災者の住宅問題
いろいろな公的支援を受けるために、その基本になるのが、その人の家がどれくらいの被害を受けたのかということです。大変大きな被害を受けて家に住めない、もう全壊してしまったというような人もいれば、大変だったけれど、家具が倒れたり食器が割れる程度で済んだという人もいます。あるいは東北であったように、津波で根こそぎ全財産、家族の思い出もろとも流されて何一つ残らないという人もいるわけです。ですから、いろいろな公的支援をする判断材料として、住宅の被害の程度に応じて出される罹災証明書というものが必要になります。この罹災証明書を出すために、災害が起こった後に建物の被害調査を役所が実施します。この調査が一つ目の調査となります。二つ目の調査は応急危険度判定調査といいます。これはボランティアの建築士が主として調査をするのですが、応急危険度、つまり自分の家に入っても安全かどうかという面から住宅を見るという調査です。三つ目の調査は、保険会社がやる査定のための調査です。これは車の事故と同じように、保険会社が地震保険に入っていた家の調査、査定をして、支払保険金額が決まります。この他にも、さらにもう一つ調査があるのですが、ちょっと話がややこしくなってしまいますので、取りあえずこの三つとします。このように同じ建物に対して時を前後して三つの調査が行われることになります。このようなことを私たちは普段知りませんから、「入れ替わり立ち替わり、いろんな制服を着た人が調査に来ているけれども、一体これは何なんだ」とたくさんの問い合わせが市役所や区役所に入るわけです。
今言ったように、三つの調査は目的が違いますので、その結果も異なることがあり得ます。応急危険度判定調査では「お宅は危険だから」と赤い紙が貼られたのに、罹災証明書をもらったら一部損壊だった場合などは、「これは一体どういうことなんだ」ということで被災者の不満はすごく大きくなりますし、行政に対する苦情も殺到します。このような大混乱が、災害が発生するたびに起きていますので、このようなことを事前にきちんと理解しておくことも大切です。
罹災証明書のための調査と応急危険度判定調査
一つ目の罹災証明書のための調査は、行政が行う建物の被害調査です。これは役所の人たちが建物1棟1棟を見て回って調査をしますので、とても時間がかかりますし、行政職員は数が限られています。しかも避難所で食事を配ったり、いろいろな仕事をしなければならないので、今回の東日本大震災の際も、全国の行政職員が東北に行って応援しています。私も実際に仙台市の宮城野区というところで、行政の建物被害調査の現場を見せていただいて、お手伝いをしていますが、そこでは横浜市役所の職員が17週間にわたって応援派遣されています。それくらいたくさんの職員が応援に行って調査をしなければいけない大変な調査です。ですから、あまり1棟に時間をかけていられないので、建物の外から「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」という4種類の被害程度を見ていきます。これが罹災証明書につながっていきます。
「全壊」というのは、まさに全て壊れてしまって、ぺちゃんこになってしまった、あるいは津波で流されて跡形もない、とても修理のしようがない、住めないというぐらいの壊れ方です。二つ目は「大規模半壊」で、ちょっと分かりにくい言葉遣いですが、これはかなりひどく壊れていて、直そうと思えば直せるけれども全壊に近い、直すにはかなりお金が掛かるという壊れ方をしているものです。三つ目が「半壊」で、半分壊れていて、ちょっと見ると、かなり壊れているように見えるものもありますが、補修をして住み続けることが可能なものです。そして「一部損壊」というのは、大した被害はないけれども建物そのもののどこか一部に、例えば屋根瓦が落ちている、玄関の土間にひびが入っている、外壁のモルタルが剥がれているといった壊れ方をしているものです。こういう4種類の壊れ方に対して、それぞれ罹災証明書が出されます。
一方、応急危険度判定調査というのは、家の壊れ方もありますが、その建物が使っても安全かどうかという観点から見ています。隣の家が倒れ掛かっている場合は、自分の家は大して壊れていなくても隣の家が倒れたらとても危ないので、入ってはいけないということで「危険」の赤紙が貼られます。
これらの調査は目的が違いますので、「危険」の赤紙が貼られているのに建物はちゃんとしていて、出てきた罹災証明書は一部損壊だということもあり得ます。その場合には、「どういうことなんだ」ということで怒りの電話が区役所に殺到するということがたくさん起きています。それ故、災害が起きる前に、そういうことをきちんと理解して混乱を少なくしておくことも、とても大事ではないかと思っています。