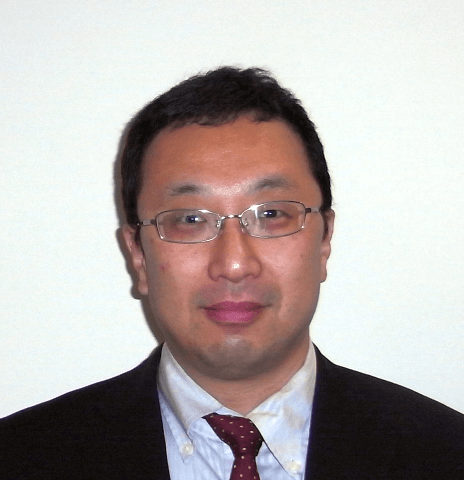災害時の帰宅
私は現在、市渋谷ヒカリエの中の防災課にいますが、これは非常に良い場所です。今日はヒカリエから、このスタジオのある市が尾まで電車に乗ってきました。日曜の朝なので電車はすいていたのですが、市が尾まで電車で約30分かかりました。多分、渋谷からここまでは約二十数?、電車では30分ですが、皆さんは歩いたことがありますか? 私は足が短いので時速4?がやっとですが、速い人ですと時速5、6?で歩いて、頑張れば半日ぐらいで20?歩くと言われています。しかし東日本大震災が起こった3月11日は、道路や国道246号線の歩道も大混雑でした。人も行列で、時速3?ぐらいでしか歩けなかったと思います。一晩中歩いた人もいたのではないでしょうか。そういう皆さんが、もし青山学院、国学院、エクセル東急、セルリアンタワー、その他いろいろな施設で休むことができるということを前から知っていれば、もしかすると様子が落ち着いてから、あるいは電車が開通してから帰ることができたのかなと思います。
今、東京都でも「やたらに歩きださないで」と言っていますが、協議会でも事前にこの施設があることを皆さんにお知らせすることが抜けていたのではないか、という反省があります。そこで、3月11日の直後、1カ月後に「渋谷区防災地図」を緊急で発行しまして、その地図の中に受け入れてもらえる施設を明記しました。これはインターネットでも見ることができます。この「渋谷区防災地図」には、いざという災害時に皆さんが避難や待機できる帰宅困難者の受け入れ施設を、現、区内で20カ所ほど表示しています。例えば、渋谷ヒカリエはもちろん、エクセル東急ホテル、セルリアンタワー東急ホテル、東武ホテル、青山学院大学、国学院大学、国立代々木競技場、また会社では日本アムウェイなどがありますが、これからもどんどん増える予定です。
3月11日の時に、他の区や市では学校で帰宅困難者を受け入れたというケースがたくさんあったと思いますが、渋谷区では基本的には学校では帰宅困難者の受け入れをお断りしていました。というのは、学校というのは地域の住民の避難所になるので、渋谷に住んでいる人と、外から来た人が一緒になってしまうと大混乱になってしまうので、しっかり分けていく必要があるからです。そのためにも、ぜひ「渋谷区防災地図」を役立てていただければと思います。これは区役所のホームページでも公開していますし、渋谷区の防災課でもお分けしています。
今、「渋谷区防災地図」についてお話ししましたが、東京急行電鉄でも「震災時安全ハンドブック」という冊子が発行されています。沿線の地図が載っており、帰宅の時にどういう道を通ったらいいのか、どこで支援を受けたらいいのか、そういう情報がたくさん載っています。渋谷区の部分については、先ほどの協議会の帰宅困難者受け入れ施設の地図を載せてもらいました。これは駅で配っているそうですが、人気があって、すぐになくなってしまい、その後、増刷したと聞いていますので、ぜひ駅で聞いてみてください。
渋谷区防災センターからの情報発信
渋谷駅周辺帰宅困難者対策協議会では、自主的な活動として、受け入れや情報連絡などもしてもらっているのですが、やはり区と民間が連携する部分というのは必要です。そのために渋谷区防災センターをヒカリエの中に新しくつくりましたので、その連携をどうやって取っているか、また区がどういった情報を集めて皆さんに発信しているのかをお話しさせていただきます。
今までは、区役所の会議室に災害対策本部を設置していたのですが、渋谷ヒカリエ8階に平成25年6月4日に渋谷区防災センターを開設させていただきました。ここでは災害対策本部となる会議室を備え、防災情報システムを投入しました。会議室の中に12面のマルチモニターがあり、ヒカリエの上、高さ180mの所に高所カメラがあります。これは災害時に渋谷区の中でどのようなことが起きているのかを、いち早くつかむことによって、対策が迅速かつ的確に行えるように設置されています。
阪神淡路大震災の時もそうですが、東日本大震災の時も、正確な情報が伝わるのに時間がかかりました。被害が大きければ大きいほど情報というのはなかなか集まってこないもので、阪神淡路の時の教訓で、逆に「情報が来ないことが重要な情報だ」という教訓もあるほどです。しかし、防災センターとして渋谷区では区民の命を守るために、いち早く情報を自分からつかみに行こう、地域から上がってくる情報を待たずにつかんでいこうということで、大規模な倒壊や火災、こういう情報をいち早くつかむために高所カメラを導入しました。まずは高所カメラなどで大づかみにし、あとはそこの地域の方と連絡を取り合って、その情報を聞いていく。やはり区役所の職員はなかなか現場に発災直後には入れないので、地域の皆さんからの情報をきちんと上げていただいて、そこの情報を共有していくことが必要だと思います。
渋谷区には、自主防災組織といって105の町会があり、その町会の皆さんそれぞれ自分たちで「わが町はわが手で守る」ということで、住民の方の手だけで初期消火、情報連絡、安否確認、避難誘導を行ったり、避難所を開設して運営をしていくなど、私たちと連携を取って、自主的に活動しています。その中で、地域の情報、安否確認などの情報が寄せられます。最初の情報は高所カメラで得ますが、やはり地域からの情報、建物がどうなっているか、道路はどうか、火事は起きていないか、そして安否確認が大切です。とりわけ渋谷区では災害時要援護者といわれるお年寄りや体に障害をお持ちの方、こういった方を全部名簿にして、個人情報の枠を超えて地域の町会長、民生委員、ボランティアである消防団の方と情報を共有しています。その名簿を基に、地域で誰が安否を確認するか、いざというときに誰が助けに行くかと、一人一人を全部決めているわけです。その情報を集めて、先ほどご紹介した防災情報システムにこれらの情報を入れて区に送る、あるいは火事や倒壊の情報や、避難所の学校に何人ぐらいが集まっているか、子どもたちは安全かなどの学校の状況を確認して、防災センターと情報を共有していきます。そして、この情報は警察や消防、ライフライン、あるいは鉄道の駅や医療関係、こういった団体と全部一緒に共有するような仕組みを今つくっているところです。
また、やはり肝となる情報である鉄道はどこが止まっていて、どこなら動くのか、道路の状況はどうなっているか、危ないから迂回したほうがいい場所や、この道は安全なので通れるというような情報も区に入ってくるので、それをしっかりと共有していくことが大事です。それで、帰宅困難者対策協議会の情報の中心となる基地と渋谷区の防災センターとも情報を共有していきます。