シェアオフィスを開業する8つの手順|費用や成功のポイントも紹介
目次
リモートワークや副業の普及に伴い、自宅以外で仕事ができる場所として「シェアオフィス」の需要が高まっています。利用者は個人事業主やフリーランスにとどまらず、コスト削減を図る企業やスタートアップからも注目されています。
ただし、シェアオフィスを開業するには、物件探しや内装工事、設備投資、運営管理の仕組みづくりなど、多くの準備が欠かせません。さらに、初期費用やランニングコストを正しく見積もらなければ、採算が合わず撤退に追い込まれるリスクもあります。
この記事では、シェアオフィスの開業手順や必要な資金の目安、成功のポイントを紹介します。これからシェアオフィスビジネスを始めたい方は、ぜひ参考にしてください。
シェアオフィスとは?

オフィスサービスの提供形態は多種多様です。事業者は自社の施設・サービス形態を「コワーキングスペース」「レンタルオフィス」「シェアオフィス」などと呼び分けます。これら柔軟に活用できるオフィスサービスの総称「フレキシブルオフィス」も便利な表現です。まずは、開業時に自社施設を何と呼ぶべきかを確認しておきましょう。
シェアオフィス
シェアオフィス(シェアードオフィス)は、複数の企業や個人が機能や区画を共有する共有型オフィスサービスの総称です。コワーキングスペース(ラウンジ)やレンタルオフィス(専有型の個室)など、1つの施設内にさまざまなオフィス形態を提供している点が特徴です。
駅構内や商業施設内の個室ブース、ホテルの空室を活用したワークスペースもシェアオフィスに含まれ、他の利用者と共有されます。オフィスサービスの形態は多岐にわたるため、「フレキシブルオフィス」として総称することもあります。
【関連記事:シェアオフィスとは?利用者に提供できる価値やユーザー層を徹底解説】
コワーキングスペース
コワーキングスペースは、異なる所属や立場の複数の利用者が1つのワークスペースを共有する共有型・協働型のオフィス空間です。一般的にはカフェのようなオープンスペースをフリーアドレスで利用し、各席にはコンセント、Wi-Fi環境、複合機などリモートワークに必要なICT環境が整っています。
基本的に全ての機能を利用者が共有し、交流を促進することが特徴です。個人事業主、フリーランスやスタートアップ企業、大企業の新規事業開発部署など、多様な利用者が集まるため、人脈形成やコラボレーションの場としても利用されます。
レンタルオフィス
レンタルオフィスは、壁やパーティションで仕切られた執務空間を、契約期間中に1社が専有できるオフィスサービスです。机・椅子などのオフィス家具やWi-Fi環境が完備された個室・半個室に入居するもので、有人受付・秘書サービスなど付加サービスが充実したものを「サービスオフィス」と呼び分けることもあります。
一般的には1か月から数年の長期契約が基本ですが、一部のサービスでは1時間単位での短期利用も可能です。どちらの場合も、一般的な賃貸オフィスと比べて低コストでの利用が可能です。このため、スタートアップやプロジェクトチームによるメインオフィスとして、また自宅での開業を避けたい士業の事務所として利用されることがあります。
シェアオフィスの開業が注目されている理由
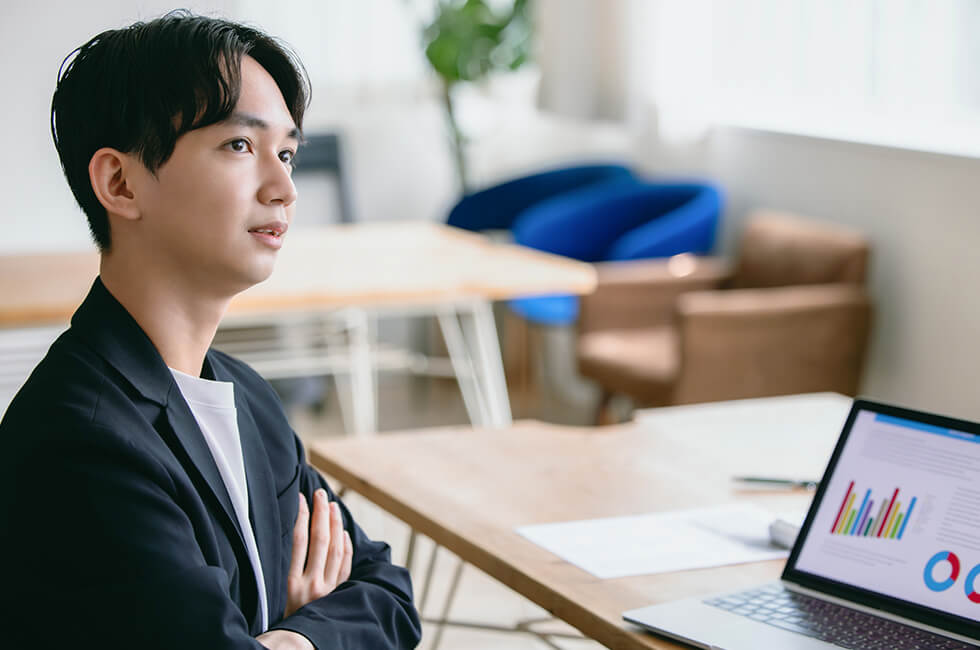
シェアオフィスは「スタートアップや一部のフリーランスが利用するサービス」というイメージを持たれることも少なくありません。ところが実際には、副業をする会社員やリモートワークを導入する企業、コスト削減を目指す中小企業まで幅広い層に利用されています。
ここでは、シェアオフィス開業が注目される理由を解説します。
フリーランスや副業人口の増加
シェアオフィスは「自宅以外に快適に仕事ができる場所が欲しい」と考える人にとって、ニーズのあるサービスといえます。特に法人登記が可能なシェアオフィスであれば、信用力を高めたい個人事業主の拠点としても適しているでしょう。
内閣府の「税制調査会第6回総会」資料によると、フリーランスの割合は1985年の14.4%から2015年には31.6%へと増加しています。さらに厚生労働省の資料では、副業者数も1992年の約75万人から2017年には128万人超へと増加しています。
こうした傾向は今後も続くと考えられ、フリーランスや副業ワーカーのニーズに応えるシェアオフィスの重要性は一層高まるでしょう。
リモートワークの普及
新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に、リモートワークは急速に普及しました。総務省の「通信利用動向調査」によれば、テレワークを導入する企業は2013年時点で13.3%にとどまっていましたが、2020年には47.5%へと急増し、2023年時点では約半数の企業が導入しています。
一方、自宅でのリモートワークには「集中できない」「オンとオフの切り替えが難しい」「通信環境が不安定」といった課題もあります。その点シェアオフィスなら、静かな環境で作業できるだけでなく、Wi-Fiや電源、会議室なども整っており、快適に仕事を進められます。
【関連記事:オフィス移転のチェックリスト!移転までに必要な作業をまとめて紹介】
企業のオフィス縮小化
従業員がフルリモートやハイブリッド勤務へ移行すると、大型オフィスを維持する必要性は薄れていきます。固定費である賃料や光熱費を削減する目的でオフィス縮小を検討する企業もあり、その受け皿としてシェアオフィスやサテライトオフィスが選ばれています。
従業員にとっても通勤負担が軽減され、自宅近くのシェアオフィスを活用することで働きやすさが向上します。企業にとっては固定費削減と従業員の生産性向上を同時に実現できる点が、シェアオフィス開業に注目が集まる理由の1つといえるでしょう。
【関連記事:サテライトオフィス勤務のメリットとは?無料で使えるオフィスも紹介!】
シェアオフィスを開業する前に確認したいこと

シェアオフィス開業を成功させるには、入念な事業計画が必要です。ターゲット・コンセプトの明確化や効果的な集客方法の検討はもちろん、利便性を高める設備・システムの整備や「有人運営か無人運営か」という運営計画も求められます。
ターゲットやコンセプト
シェアオフィスのユーザー層は幅広く、地域によっては大手の多店舗展開型など競合も多いため、ターゲティングとコンセプトの明確化は重要です。例えば、個人事業主やスタートアップの開業需要と、サテライトオフィスとしての一時的・定期的な利用需要では、最適な利用価格や区画規模が異なります。
都心の好立地・好アクセスなシェアオフィスを開業する場合、スタートアップ支援やイノベーション支援、クリエイター向けなどと、個性的なコンセプトで差別化を図ることが求められるでしょう。一方で、競合が少ない住宅地なら、地域住民が育児や家事の合間に利用できる多目的スペースとして需要が見込めるかもしれません。
集客方法
開設したシェアオフィスの認知を高め、想定ユーザー層の利用を促進するためには、効果的な集客方法を考えることが大切です。シェアオフィスはインターネットで検索・比較されることが多いため、以下のようなオンラインの広告チャネルを活用しましょう。
- Webサイトやブログを開設する
- InstagramやX(旧Twitter)などのSNSを活用する
- 予約ポータルサイトに施設情報を掲載する
施設内の雰囲気・区画・設備や利用できるサービス一覧などを、図版や写真も交えてアピールすることがポイントです。また地域特化型のシェアオフィスならば、チラシやダイレクトメールなどオフラインの広告チャネルも活用できるでしょう。
有人運営or無人運営
有人運営か無人運営かを考えることも大切です。有人型店舗は秘書サービスなど付加サービスの提供にも対応しやすい一方、人件費がかさみます。無人型店舗なら常駐スタッフも受付スペースも必要ありません。一方で、管理システムには注意が必要です。無人運営の場合、以下のような設備・システムの導入が求められます。
- スマートロック
- 入退室管理システム
- 会員管理システム
- 予約管理システム
- 請求・決済・入金管理システム
これらの設備・システムは、有人型店舗でもスタッフの業務負荷軽減に役立ちます。
シェアオフィス開業の手順

シェアオフィスを開業するには、事業計画から運営まで体系的に準備を進める必要があります。手順を誤れば、法的な問題が発生したり、利用者の信用を失ったりして、事業継続が困難になるおそれもあります。スムーズに開業するために、以下で紹介する8つの手順を押さえておきましょう。
1.事業計画の策定
シェアオフィスを開業する際は、「なぜ開業するのか」「どのようなコンセプトで誰をターゲットにするのか」を明確にし、方向性を定めましょう。例えば「フリーランス向けに低価格プランを提供する」「スタートアップ向けに法人登記や会議室利用を可能にする」といったように、ターゲット層によって必要なサービスは大きく異なります。
事業計画には、提供するサービス内容、料金体系、競合との差別化ポイント、将来的な拡張性なども盛り込みます。計画を文書化しておけば、資金調達や物件選定の場面で説得力が増し、開業後の運営においても指針となります。
2.資金調達
シェアオフィスの開業には、物件取得費、内装工事費、設備・備品の購入費用など、まとまった初期費用が必要です。自己資金で賄えない場合は、外部からの資金調達を検討しましょう。代表的な方法は、日本政策金融公庫や民間金融機関からの融資です。
さらに、国や自治体の補助金・助成金を活用できれば、返済不要の資金を確保できるため大きな助けとなります。そのほか、クラウドファンディングを通じて開業前から利用者や支援者を募る方法も有効です。必要に応じて複数の手段を組み合わせ、無理のない資金計画を立てましょう。
3.物件の選定・契約
立地は集客に直結するため、ターゲット層が通いやすいエリアを選ぶことが大切です。例えばフリーランスや副業ワーカーを狙う場合は都市部の駅近が有利であり、企業のサテライトオフィス需要を取り込む場合は郊外や住宅地の利便性が高い場所も効果的です。
さらに、物件の広さや間取りは利用者数や提供サービスに直結します。内見時には日当たり、騒音、インターネット回線の引き込み可否なども確認しましょう。契約前には賃料や管理費に加え、保証金や解約条件まで細かくチェックしてリスクを回避することが重要です。
4.内装工事
物件が決まった後は、ターゲット層に合わせた内装を整える必要があります。集中して作業できるデスクスペースを多く確保するのか、会議室やラウンジを充実させるのかによって設計は変わります。利用者が快適に過ごせるよう、照明、空調、動線設計にも配慮しましょう。
内装工事ではデザインだけでなくコストやメンテナンス性も考慮し、専門業者と入念に打ち合わせを行うことが大切です。施工中は進捗を随時確認し、当初のイメージとズレがないかをチェックしてトラブルを防ぎましょう。
5.設備・備品の導入
シェアオフィスを快適に運営するには、デスクや椅子といった基本的な家具に加え、Wi-Fi環境、プリンター、モニター、プロジェクターなどの設備も必要です。利用者が増えるほど回線速度や電源数の不足が問題になりやすいため、余裕を持った設備設計を心がけましょう。
また、セキュリティ面を考慮した入退室管理システムや監視カメラを導入しておくと安心です。コストを抑えるには、新品と中古を組み合わせる方法も有効です。
6.開業に伴う書類の提出
シェアオフィスを事業として運営するには、法的な手続きを忘れてはいけません。個人事業主であれば税務署への開業届が必要で、青色申告を希望する場合は青色申告承認申請書も提出します。法人として運営する場合は法務局で法人登記を行い、定款の作成や登記申請などを進めましょう。
さらに、オフィスによっては消防署への届出や建築基準法に関する確認が必要な場合もあります。開業前に必要書類を洗い出し、行政書士や税理士などの専門家に相談すれば、手続きをスムーズに進められます。
7.スタッフの雇用・教育
シェアオフィスの運営形態によっては、スタッフの雇用が必要になります。有人運営であれば、受付や入会手続き、利用者対応を担うスタッフを採用します。無人運営であっても、清掃や設備管理、トラブル対応を行う人材が必要になる場合があります。
採用後は利用者対応マニュアルやセキュリティルールを徹底的に教育し、サービス品質を一定に保つことが重要です。利用者にとって「安心して利用できる場所」であることが、集客力の向上につながります。
8.運営開始
準備を整えたら、シェアオフィスの運営を開始します。オープン日を設定し、SNSやWebサイト、チラシ、地域メディアなどを活用して告知しましょう。プレオープン期間を設けて限定キャンペーンや内覧会を実施すれば、認知度を高めやすくなります。
開業後は利用者の声を積極的に収集し、サービス改善に反映させることが欠かせません。競合との差別化を意識しながら、柔軟にサービスを改善・拡張していくことで、安定した利用者数を確保できるようになります。
シェアオフィス開業にかかる初期費用とランニングコスト
シェアオフィスを開業する際に必要となる初期費用は、規模や立地条件によって大きく変動します。
一般的には100万円〜1,000万円程度が目安とされますが、自社で建物を所有している場合は、内装工事や設備導入、広告宣伝費用を中心に300万円程度で始められるケースもあります。一方、広い物件を新たに借りて運営する場合は、1,000万円を超えることも珍しくありません。
ランニングコストは月20万円〜50万円が相場で、家賃、光熱費、通信費、清掃・メンテナンス費用、人件費などが含まれます。開業直後から安定した収益を得るのは難しいため、3か月分程度のランニングコストを見込んで資金を準備しておくと安心です。
シェアオフィス開業を成功させるポイント

シェアオフィスの需要は増えているものの、同時に競合も増加しています。単にスペースを提供するだけでは差別化が難しく、利用者に選ばれるためには戦略的な取り組みが必要です。ここでは、開業を成功させるために押さえておきたいポイントを紹介します。
事業再構築補助金の活用
政府や自治体が運営する補助金・助成金の中には、シェアオフィスの開業に使えるものもあります。例えば、中小企業などを対象に事業再構築を支援する「事業再構築補助金」です。
事業再構築補助金には複数の応募枠がありますが、「成長枠」と呼ばれる部分には、市場の拡大が見込まれる新規事業を対象としており、2023年度からはフレキシブルオフィスの開業も含まれるようになりました。
例えば、コロナ禍で利用客が減少した旅館の客室をコワーキングスペースへと改修し、新たに運営する場合、シェアオフィスへの業種転換が補助金の対象として認められるようになります。補助金でカバーできる主な経費は、建物の改修費やマーケティング活動にかかる費用(広告宣伝費や販売促進費)などです。
入念な競合調査
競合と差別化を図るには、徹底した競合調査が欠かせません。周辺エリアにどのようなシェアオフィスがあるのか、料金体系、提供サービス、設備、立地条件を比較することで、自社の強みを打ち出すヒントが得られます。
例えば、競合が会議室を有料提供しているなら無料で提供する、フリーランス向けが多い地域では法人登記や受付対応を重視するといった形で、差別化の方向性を見極められます。競合の「弱み」を分析することも大切ですが、同時に「強み」を学び取り入れることで、より魅力的なサービスへと進化させられます。
管理を自動化して省人化・低コスト化
管理を自動化することで省人化・低コスト化を実現でき、人件費という固定費を大きく削減できます。例えば入退室管理をICカードやスマートロックで行えば、受付スタッフを常駐させずともセキュリティを確保できます。
さらに予約や決済をオンラインシステムで完結させれば、利用者は24時間好きなタイミングで手続きでき、運営側の負担も軽減されます。清掃や設備点検といったオペレーションも、外部委託やスケジューリングシステムを活用すれば効率化が可能です。
シェアオフィス開業に必須の管理システム・Wi-Fi整備ならイッツコム!

シェアオフィスの開業に当たっては、複数の管理システムやWi-Fi環境の整備が必須です。
イッツコムは各種管理システムを一本化できる「Connected Space Share(コネクティッドスペースシェア)」、シェアオフィスの無人運営をサポートする「Connected Portal(コネクティッドポータル)」、快適なフリーWi-Fiの整備に最適な「かんたんWi-Fi」を提供しています。
ここでは、シェアオフィス成功を支援するイッツコムのサービスについて紹介します。
管理システムを一本化できる「Connected Space Share(コネクティッドスペースシェア)」
無人運営のシェアオフィスを開業する際に課題となるのが、入退室管理や予約・決済といった運用オペレーションです。「Connected Space Share(コネクティッドスペースシェア)」は、これらを一括で管理できるソリューションとして、多くの施設運営者に選ばれています。
利用者は施設のLINE公式アカウントを「友だち登録」するだけで、スマートフォンから対象スペースの予約、決済、スマートロックによる解錠までをシームレスに行えます。新たにアプリをダウンロードする必要がないため、ユーザーの利用ハードルを下げられる点も大きなメリットです。
また管理者は専用ダッシュボードを通じて、利用者情報、予約状況、入退室履歴、売上を一元的に遠隔管理でき、多拠点展開や事業拡大期にも柔軟に対応できます。
入退室の管理をスムーズにするなら「Connected Portal(コネクティッドポータル)」
シェアオフィス運営において大きなコストとなるのが「スタッフの雇用と教育」です。有人対応で運営する場合、人件費や教育にかかる工数は軽視できません。そこで役立つのが「Connected Portal(コネクティッドポータル)」です。
Connected Portal(コネクティッドポータル)は、スマートロックとゲートウェイを活用し、特定のユーザーに特定期間だけ有効な「時限式の鍵」を発行するサービスです。従来必要だった鍵の受け渡し業務が不要となり、利用者は専用アプリでスムーズに入退室できます。
管理者は遠隔で操作や監視ができるため、物理的な対応にかかる人件費を大幅に削減できます。さらに既存の予約システムとAPI連携でき、複数システムを使い分ける必要がない点も大きな特徴です。
快適なフリーWi-Fiの提供なら「かんたんWi-Fi」
シェアオフィスは壁やパーティションで区画が仕切られ、多数の利用者が同時にWi-Fi接続することもあります。電波の死角や同時接続時の接続トラブルを避けるには、施設の構造や利用人数に応じて、複数台のWi-Fiアクセスポイント(AP)を設置するとよいでしょう。
イッツコムの「かんたんWi-Fi」ならば、高性能な業務用APを低コストでレンタルできます。初期費用0円で利用でき、開業時のコスト投下を抑えられることもポイントです。
「ハイエンド6」プランのAPなら高速・安全なWi-Fi6対応で、1AP当たり100台の同時接続に対応します。ゲストWi-Fi機能も充実しており、シェアオフィス利用者に快適なフリーWi-Fiを提供することが可能です。
まとめ

シェアオフィスの市場規模は拡大を続けており、今後もサテライトオフィスとして、また個人事業主やスタートアップのワークプレイスとしての活用が期待されています。補助金を利用して、不採算の店舗を改修しシェアオフィスを開業することも1つの選択肢です。
ただし、地域によっては競合も多く存在するため、魅力的な施設環境の整備とそのアピールが必要になります。スマートロックやWi-Fi環境の整備などを行い、効率的な運営が可能なシェアオフィスの開業を目指しましょう。
イッツコムは「Connected Space Share(コネクティッドスペースシェア)」や「Connected Portal(コネクティッドポータル)」、「かんたんWi-Fi」により、シェアオフィスの無人運営や他拠点展開をサポートできます。シェアオフィスの開業をお考えの際は、必要な環境整備のトータルサポートができるイッツコムにご相談ください。






