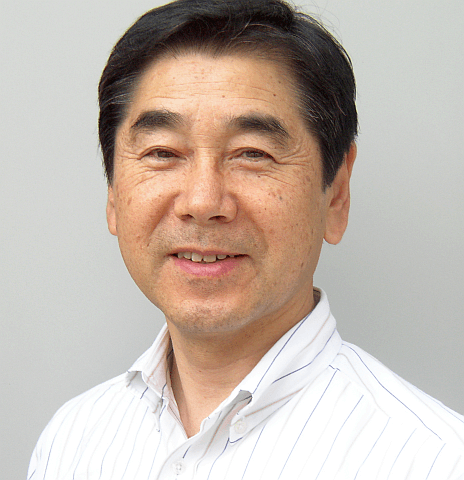プロフィール
今、私は足立区にある身体障害の方々が生活している施設の施設長をやっています。
施設には40名の障害の重い方たちと、日々バスを使って通ってくる非常に体の障害が重い28名の方がいて、総勢で68名という施設の施設長をやっています。
私は、この福祉の世界に入って、ちょうど30年を迎えたところです。しかし、もともとは直接福祉の世界に関係があったということではありません。最初、私はコンピューターのことが大好きで、大学を卒業してコンピューターのメーカーに勤めていました。そこで出会った仲間の中に、たまたま障害のある人がいて、そのことがきっかけになって福祉のことを考えるようになりました。当初、かなり高額な、何億という高いコンピューターが日本中で使われていましたが、このコンピューターを障害のある人やお年寄り、子どもたちの教育にうまく有効利用できないかということを考えて、始めた時期でした。私もちょうど30歳になるころ子どもが生まれまして、この子どもたちのために何かコンピューターを使ってできるものはないだろうか、ということを考えておりまして、我が子にもそんなことができるといいなというのは、何となくイメージとしてはありました。
コンピューターから防災へ
私が障害に関する施設に勤め始めたのは30歳の時ですが、このころに防災とも出合います。勤め先の近くに早稲田大学がありまして、ある時、早稲田大学で「ごみの組成調査」というのを行ったことがあります。たまたま私の知人が東京都の職員で、近くの清掃事務所の所長に着任しまして、その関係で、お手伝いをすることになりました。
今、東京の埋め立て地にF区最終区というのがありますが、現在のごみの量をそのまま排出すると、あと10年しか持たないと言われています。この最終区が終わってしまうと、東京湾の東京都の土地というのはなくなります。そうすると隣の千葉県から土地を分けてもらって、そこにごみを捨てていく、ということが問題になりつつありました。その時に「早稲田でいろんなことをやってみましょう」ということで、大学のキャンパスを借りて世界中に、いろいろとインターネットを配信しました。そこでは子どもの教育、福祉、あるいは震災や環境問題とか、いろいろなことを取り上げて、皆で分担しあって考えようという試みが始まりました。これがもう14年ほど前になりますが、それが1つのきっかけで仲間と出会い、現在もずっと続いているというのが防災、震災との関わりということになります。
地域と協働で町を守る
今、私の施設には68名の入所者と短期入所の方4名がいますので、合計で72名。それと日中には職員が110名ほどおりますが、夜間は何と4名しかいません。利用者は夜間は40名、職員が何と4名ということです。そうなりますと職員の4名で、もし大きな災害があったときに40人を助けるということは多分不可能だと思います。こうしたときに、どうしたらいいか、ということを以前からずっと考えていました。
今は夫婦共働きの方・家族が非常に多いので、昼間は町に若い人がいない状況です。しかし夜になると帰って来ますので、老弱男女たくさんの人がいます。そこで地域の町会にお願いしまして、夜は町の皆さんに助けていただく、その代わり昼間は職員がたくさんいますので、私たちが何かあったときには町に出て応援しますということで、協働ができないか、というお話をさせていただきました。今、着々とそれをやりつつあります。
そして地域の皆さんと土曜日、日曜日に避難訓練を何遍も一緒にやって、その中で幾つか大切なことが改善されてきました。一般的には一時避難場所というのは、多くが地域の小中学校の体育館になっています。しかし、そこに設けられているトイレはいまだに昔ながらの和便器になりますので、洋便器でないと足腰の弱い高齢者、障害者はまず使うことができません。そこで我々が知恵を出して、ポータブルトイレを体育館の隅、あるいは空き教室に予備として置いておくことにしました。そうすれば高齢者も障害者も使えるわけです。
少ない人数だからできないと考えるのではなく、知恵を出し合って、お互いに助け合いながら、その力を補いながら何かをするということで、大きなエネルギーが生まれるということを、地域と協働でやっています。そのためにも地域との防災、避難訓練が大切ですので、私どもの施設では毎月必ず、こういった訓練をしています。当施設では職員は全員ヘルメット、利用者さんは防災頭巾が用意されておりますので、即座にそれを出して、かぶって逃げるという訓練を行っています。また逃げるパターンも幾つかありますので、その都度その都度、工夫をしながら避難訓練をやっています。