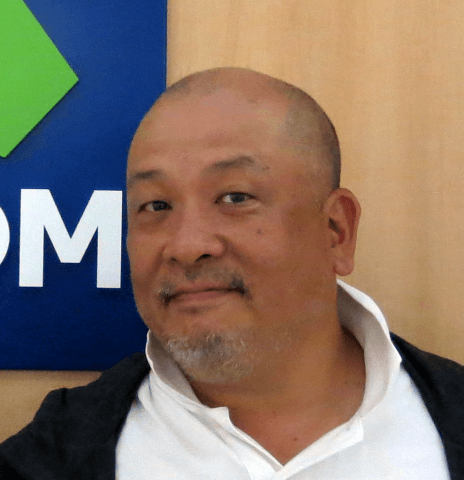楽しく学ぶ「防災」
実は「防災」というのは、働き盛りと子育て盛りの時期などに、一生に一回徹底的にやれば、あとはちょっとマイナーチェンジしていけば、一生楽しく過ごすための準備ができるので、それこそが「防災」だと僕は思います。ですので、働き盛りの方やお母さん方にやってほしいと、今ではすごく思っています。おじいちゃん、おばあちゃんの手から、自治会長の座を奪い、若い人たちが防災グループをつくっていかないといけないと思います。あるいは、町内会とは別に防災グループをつくっていく必要があるかもしれません。その若い世代が、子どもたちとめちゃくちゃ楽しいイベントをどうやって行っていくのかということを今徹底的に考え始めています。若い世代が中心になって、一生に一回でいいので、「防災」をしっかりと学んでいくことが大切です。
「防災かあさん」で、みんなで学ぶ防災
「防災かあさん」は僕がプロデュースした本で、全部で90問の設問があります。それをお母さんと家族が一緒に考えて、答えを出していくという形式になっています。非常に分かりやすい言葉で、かわいいイラストで読み進められるようになっています。子育て世代で忙しいお母さん方も、1ページに1問入っていて、家族で楽しんでいただける内容になっていますので、1日1問でもいいから時間をつくり出していただければと思います。
「防災かあさん」という本は、すごく見やすくて解説が載っています。まず頭に「避難所は都道府県が運営をするものではありません」とテーマがあって、アンサーがあって、解説がされているのですが、すごく分かりやすく、難しく字ばかり羅列されている本ではないので読みやすいと思います。
ただ、これはほんの入り口です。いわゆる一般的な防災の知識の入り口だと思ってください。事実、防災というのは、自分のお家、お父さんが働いている地域、子どもが通っている学校、とにかく家族が生き残っていくという、ローカライズ、いわゆる自分の地域に合わせて家族が考えるものだと思っています。それで、家族で防災会議をやるためのシートが付いています。一番後ろに、「家族防災宣言」というのがありまして、これを家族みんなで相談しながらやると、いざ起きたときにどこに何があって、どこに逃げて、何をしなければいけなくて、もし携帯電話がつながらなくても、どこに行ったら会えるというような約束事とかが、全てできるようになっています。わが家の備蓄品チェック、避難バックの中身チェック、家、学校、仕事場、周りのリスク、わが家の中の危ない場所とかメモを書き込むようになっていて、家族が共通認識として「これは危ない」「こういう時はこうしよう」というのが分かるようになっています。
また最近では、家庭での備蓄は1週間分が望ましいというのがあります。例えば、レトルト食品とかカップ麺とか水とかが、だんだん古くなっていくじゃないですか。その時には、9月1日の防災の日と、3月11日の東日本大震災の日に、古くなったものを家庭でパーティをしながら入れ替えて行くという作業ができれば、もう防災はばっちりだと思います。東京のことを考えると、人口が大変多いということもあって、避難所が実を言うと全員が入れず、3分の1くらいしか入れませんし、消防車や警察や自衛隊の方が助けに来てくれるまでに、ちょっと時間がかかってしまうと思われます。それで、家族で1週間生き延びられるための準備をしてほしいと思っています。