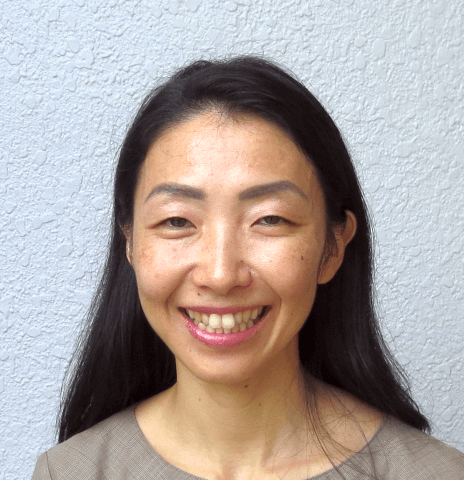プロフィール
私は、産婦人科医としてずっと勤めながら、1人目をドイツで、また4人目をアメリカ留学中に出産しまして、今は5人の母親として、上は10歳から下は1歳まで、毎日元気な子どもたちと過ごしています。そんな私が産婦人科医の道から災害医療、防災の道に進むようになったきっかけは、2011年3月11日の東日本大震災の際に、居ても立ってもいられず被災地の避難所に駆けつけたことから始まりました。私はそれまで災害医療や防災とは全く関係がなかったのですが、自分自身がその当時、生後半年になる4人目の子どもを抱えていたこともあって、災害直後や避難所暮らしの中で「きっと困っているお母さん、妊婦さん、赤ちゃんがいるんじゃないか」と思いまして、日本プライマリ・ケア連合学会から派遣をしていただいて、自分の母親としての直感、確信を頼りに宮城県石巻市、南三陸などを車で回りました。「被災地の母子はどうなっているんだろう」「何か助けること、なにか手伝えることがあるんじゃないか」と思って駆けつけたところ、避難所には震災後2カ月、3カ月たっていても、まだ妊婦さんや乳幼児の姿が見られました。その方々はご自分もとってもつらい立場にありながら、気遣いといいますか、周りに迷惑を掛けまいとして、つらいこと、困っていること、なかなか声を上げられずにいました。被災地を回ってみて、困っている人ほど病院にはたどり着けない、困っている人ほど「助けて」と声を上げられないということに気が付きました。私はそれまでは病院の中で産婦人科医として、患者さんを助けるという立場におりましたが、これは自分たちのサービスを出前して回るような姿勢がなければ、震災後のお母さん、赤ちゃん、妊婦さんには本当に必要としているものが届けられないのではないかと思いまして、2012年から国立保健医療科学院で、研修、研究、教育などをしています。
産婦人科医として、母として
私が最初に産婦人科医として聖路加国際病院で研修を始めた際に、まず「患者さまの立場に立って、患者さまの声を聴いて、寄り添って、想いを慮って」という医者としての姿勢を叩き込まれたことがとてもよかったと思います。その後博士号を取得して、結婚して夫とともにドイツに留学しました。そこで1人目を授かったのが、私にとっては本当に目から鱗が落ちるような体験でした。それまでは、無事に安全なお産を迎えられれば、私たちの仕事は満点だ、合格点だと思っていたのですが、生まれてからの子育てや母親の気持ち、家族の気持ち、そういうものが見えるようになったのが、自分が子どもを授かってよかったなと思うことです。また、その後日本に帰ってきて臨床を始めて、日本にはすごくいいところもたくさんあるけれども、どうしても産婦人科医が足りないし、女性医師がなかなか働き続けられないという現状を何とかしたいと思いました。どうやったら女性が楽しく働き続けられるのか、女性医師が子育てをしながらも、生き生きと患者さまのお役に立てるには、どんなスキルが必要なのかと思ったことがきっかけで、2008年にアメリカのハーバード大学公衆衛生大学院に留学をいたしました。このように、医者として、母として、研究者としてキャリアを積ませていただいているのも、たくさんの方に支えていただいたおかげだと思っています。
東日本大震災で見えてきたこと
私は、東日本大震災の前までは、産婦人科医師として自分が災害や防災の世界に関わるとは思っておりませんでしたが、東日本大震災の際に「自分にもなにかできることがあるのでは」と駆けつけた時に気が付いたことがありました。それは、ついハード面、インフラの面での災害対応や防災を考えがちですが、本当はそこに住む人や次世代の方、その地域の現状に合わせたソフト面にも目を当てて、防災のこと、災害対応のことを考えないといけないということでした。
私は、自分自身も母親であり、産婦人科医でもありますが、まず気が付いたのは、母親、妊婦さん、子ども、こういう人たちを誰が責任を持って災害の時に守るのか、所在を把握して安否確認をして、誰が安全な所に避難させるのかということにおいて、この「誰が」というところが、日本中あちこちで抜け落ちていたような気がします。東日本大震災では、災害時要援護者、要配慮者の方への対応がちょっと足りなかったという意見が聞かれましたが、私は、その中でも一番のマイノリティーである妊婦さん、赤ちゃんへの対応が一番なおざりになっていたのではないかと思いました。いろいろな組織の方が「これは自分の仕事じゃないから」ということで、妊婦さんのことや子どもさんのことをなんとなく、他人事にしていたような気がします。
その理由の一つとして、日本は世界で一番少子化であり、妊婦さん、赤ちゃんが全人口の0.8%しかいないような状態にあって、ある意味、人数が多い人から先に助けよう、妊婦さん、赤ちゃんは後回しになってもしょうがないというようなことがあるのではないかと思いますし、医療が責任を持つのか、行政が責任を持つのか、地域の人たちで責任を持たないといけないのかということが分からず、そのどこにも入らないような形で、組織の中の、あるいは分野、領域の中の隙間に落ちてしまったのが、妊婦さん、赤ちゃんなんだなと私は感じました。
災害に対応する先生方は、外科の先生、救急医の先生が多いですし、産科のこと、小児科のことが苦手だと思う方もいらっしゃるとは思います。また、地域の方や行政の方も、なんとなく妊婦さんに対しては、家族の中のプライベートな部分には口を挟みにくいような雰囲気もあるのかもしれません。もうひとつ、妊娠した方はいろいろなリスクを背負っていますし、とても大事な存在なのですが、実際には9カ月、10カ月で妊婦さんではなくなってしまいますので、要配慮者リストに載せたり、自治体できめ細やかにフォローするということも難しいのではないかなとは思いました。
私は自分自身が産婦人科医ということもあって、妊婦さんは2つの命を抱えるとても大事な存在だと思っていますし、妊婦さんと生まれてくる赤ちゃんの先に、この土地を将来支える命が脈々と樹形図のように広がっているということを感じています。その意味においても、赤ちゃんや妊婦さんの命はとても貴重で、その人たちの健康や安全、幸せを、もうちょっと優先してもいいのではないかと、私は大震災を通して思いました。