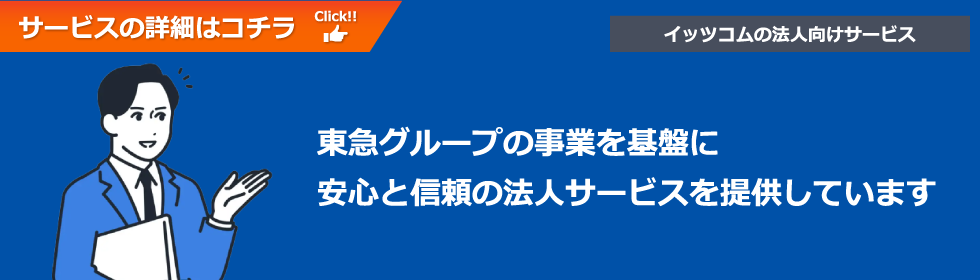入退室管理システムを導入するメリットは?機能や料金目安、導入方法
目次
オフィスや施設のセキュリティ強化、従業員の出退勤管理の効率化を図りたい企業から注目されているのが「入退室管理システム」です。従来の物理鍵では管理が煩雑になりやすく、誰がいつ出入りしたかを手作業で記録するには限界があります。
一方、入退室管理システムを導入すれば、ICカードや暗証番号、指紋・顔認証など多様な方法で入退室をコントロールでき、記録も自動で管理できます。
この記事では、入退室管理システムの主な機能、料金の目安、導入方法を解説します。これから導入を検討している企業や施設管理者の方は、自社に最適なシステムを選ぶための参考として、ぜひ最後までご覧ください。
入退室管理システムとは

入退室管理とは、誰がいつ入室し、いつ退室したのかを記録・管理することです。従来は物理的な鍵の貸し出しや紙の台帳による記録が一般的でしたが、紛失や不正利用のリスクが高く、管理者の負担も大きい点が課題とされていました。
こうした課題を解決するために登場したのが「入退室管理システム」です。入退室管理システムは、ICカードや暗証番号、指紋認証、顔認証などを活用し、電子的にドアを開閉するとともに、ログを自動で記録するシステムです。
単に出入りを管理するだけでなく、セキュリティレベルの向上や労務管理との連携、さらに利用者の利便性向上まで実現できる点が注目されています。
入退室管理システムを導入するメリット

入退室管理システムの導入は、企業や施設に多くのメリットをもたらします。従業員や利用者にとって安全で快適な環境を整えられるだけでなく、管理側にとっても業務負担の軽減やコスト削減につながる点が大きな利点です。
以下では、入退室管理システムを導入する主なメリットを詳しく見ていきましょう。
セキュリティ強化
従来の物理鍵は紛失やコピーが容易で、不正侵入のリスクがありました。しかし、ICカードや生体認証を利用する入退室管理システムでは、登録された本人しか扉を開けられないため、第三者による侵入を防ぐことが可能です。
また、誰が・いつ・どの部屋に入ったかを自動で記録できるため、不正アクセスが発生した際の追跡も容易になります。特に研究所や医療機関、情報を扱う企業では、重要データの流出防止に直結します。
さらに、セキュリティレベルを場所ごとに設定できるため、役職や部署に応じて入室可能なエリアを限定できるのも大きなメリットです。
業務効率の向上
入退室管理システムを導入すれば、物理的な鍵の貸し出しや返却、紛失対応といった煩雑な作業が不要になります。管理者はICカードやアカウントの権限を付与・停止するだけで、従業員の入退室権限を柔軟に管理可能です。
また、勤怠管理システムと連携すれば、入退室のログをそのまま出退勤データとして活用でき、打刻の手間や入力ミスを削減できます。結果として、管理部門の工数削減だけでなく、全社的な生産性向上にもつながります。
利便性アップ
入退室管理システムは、利用者の利便性向上にも大きく貢献します。従来のように鍵を持ち歩く必要がなく、ICカードや社員証をかざすだけでドアが開くため、入退室がスムーズです。スマートフォンアプリを鍵代わりに利用できるシステムも普及しており、カードを忘れた場合でも安心です。
また、スマートロックにオートロック機能が備わっていれば、施錠忘れによるリスクも防止できます。さらに、来訪者に一時的な入室権限を付与できる機能を備えたシステムもあり、受付対応の効率化にもつながります。
入退室管理システムの認証方法

入退室管理システムでは、「誰が正しい利用者なのか」を判別するために、さまざまな認証方法が用意されています。導入にあたっては、利用シーンや求められるセキュリティレベル、利用者の利便性を考慮し、最適な認証方法を選ぶことが大切です。
ここでは、代表的な認証方法を4つ紹介します。
生体認証
生体認証は、指紋・顔・虹彩・静脈など、個人の身体的特徴を利用して本人確認を行う方法です。鍵やカードを持ち歩く必要がなく、本人の「体そのもの」が認証手段となるため、なりすましや紛失のリスクが低い点が大きなメリットです。
特に指紋認証や顔認証はスマートフォンで広く普及しており、利用者にとって抵抗感が少なくスムーズに導入できます。さらに、管理側にとってもカードの発行や回収が不要なため、運用コストの削減につながります。
ICカード
社員証や専用カードをかざすだけで解錠でき、利用者にとって直感的で分かりやすい点が特徴です。カードを複数人で共有することも可能ですが、基本的には1人1枚を割り当てます。万が一カードを紛失しても、管理システムから権限を停止できるため、不正利用のリスクを最小限に抑えられます。
また、既存の社員証や交通系ICカードをそのまま利用できるシステムもあり、導入コストを抑えやすい点も魅力です。さらに、ICカードは認証スピードが速いため、利用者が多いオフィスや施設でもスムーズな入退室を実現できます。
ただし、カードの持ち歩きが必要であることや、盗難・貸し借りによる不正利用の可能性がゼロではない点には注意が必要です。
暗証番号
暗証番号方式は、扉に設置されたテンキーに数字のパスコードを入力して解錠する仕組みです。カードや端末を持ち歩く必要がなく、忘れ物や紛失の心配もありません。特に少人数のオフィスや店舗、一時的な利用が想定される場合に有効です。
また、番号を定期的に変更することでセキュリティを維持でき、カード発行や管理にかかるコストも不要です。一方で、番号が第三者に知られると不正侵入を許す恐れがあるため、利用者が番号を適切に管理することが求められます。
スマートフォン
専用アプリやクラウドサービスと連携し、無線通信やスマートフォンをかざすことでドアを解錠する方法です。この認証方法では、従業員は物理的なカードや鍵を持つ必要がなく、普段使用しているスマートフォン1つでスムーズに入退室が行えます。
また、管理者側にとってもリアルタイムで権限の付与・停止が可能なため、緊急時の対応を迅速に行える点も魅力です。さらに、一時的に利用できる「デジタルキー」を発行し、来客や清掃業者に付与することで、受付業務の効率化にもつながります。
入退室管理システムの主な機能

入退室管理システムには、セキュリティを強化するものから利便性を高めるものまで、多様な機能が搭載されています。ただし、全てのシステムに同じ機能が備わっているわけではないため、施設の規模や利用目的に応じて導入機能を選定することが重要です。
ここでは、入退室管理システムに搭載される代表的な機能を紹介します。
アンチパスバック
アンチパスバックは、「入室した履歴がある人しか退室できない」というルールを自動的に適用する不正利用防止機能です。例えば、1枚のカードを複数人で共有して侵入する「共連れ」のリスクを軽減する際に有効です。特にセキュリティを重視する研究施設やサーバルームなどに適した機能といえるでしょう。
インターロック
インターロック機能とは、複数の出入口を同時に開けられないよう制御する仕組みです。例えば、セキュリティルームやクリーンルームなどで、一度に1つの扉しか開けられないよう設定することで、不正侵入や外気の流入を防ぎます。
インターロックは、片方の扉を閉めない限りもう片方を開けられないため、侵入者が複数人で一度に入るのを防ぐ「セキュリティゲート」としての役割も果たします。
アクセスレベル設定
アクセスレベル設定は、従業員や利用者ごとに入退室可能なエリアを細かく制御できる機能です。例えば、一般従業員はオフィスエリアまで、管理職や研究員はサーバルームや研究室まで入室可能といったように、立場や役割に応じて権限を設定できます。
この機能を活用すれば、重要情報を扱う場所や高額な設備のあるエリアへのアクセスを最小限に抑え、情報漏えいや設備の不正使用を防止できます。
動線管理
動線管理は、移動ルート(動線)をシステム側で限定・制御する機能です。例えば、特定の部屋に入る際に、あらかじめ設定された順路を経由しなければ入室できないよう制限できます。正しいルートを通らず直接入室しようとした場合は認証が無効化されるため、複数の入口を持つ部屋や施設でも高いセキュリティを維持できます。
複数名(2名)照合
複数名照合機能は、特定エリアへの入室時に2人以上の認証を同時に求める機能です。例えば、1人がカードをかざすだけでは扉が開かず、もう1人のカード認証や生体認証を行うことで初めて解錠されます。重要施設への単独侵入を防ぎ、不正アクセスのリスクを低減します。
優先ID
優先IDは、特定の人物が在室している場合にのみ他の利用者の入室を許可する機能です。例えば、管理責任者や指導者といった「優先権を持つ人」が部屋にいるときのみ、他の従業員や利用者が入室できるよう設定できます。責任者不在時の無関係者の立ち入りを防ぎ、施設のセキュリティ強化に役立ちます。
時限ルート
時限ルートは、あらかじめ設定した条件に基づき、「一定時間だけ利用可能な通行経路」を制御できる機能です。例えば、特定のカードリーダーを操作した際に、同一グループに属する扉の開閉を一定時間のみ許可または禁止することが可能です。
時限ルート機能を活用すれば、利用者の滞在時間を制限でき、長時間の不正滞在や無断利用を防止できます。
入退室管理システムの料金目安
入退室管理システムの導入には、初期費用と月額費用が発生します。一般的な目安としては、小規模〜中規模企業向けで「1扉あたり月額5,000円〜1万円」、中規模〜大規模企業向けでは「1扉あたり月額1万円〜」程度です。
初期費用はシステムの種類や導入方法によって差があります。無料で始められるものもありますが、工事や機器費用を含めると5万円〜10万円ほどかかるケースが多い傾向にあります。また、料金は導入する扉の数や認証方式(カード認証・指紋認証・顔認証など)、鍵の種類(電気錠・スマートロック)によっても変動します。
例えば、複数の扉をまとめて導入する場合はスケールメリットが働き、1扉あたりの月額費用を約2,000円以下に抑えられるケースもあります。
入退室管理システムの導入パターン

入退室管理システムは、企業や施設の状況に応じて導入方法が大きく異なります。例えば「賃貸オフィスで大掛かりな工事ができない」「すでに自動ドアや電気錠を設置している」「セキュリティレベルを最大限高めたい」といったニーズごとに適した方法があります。
導入パターンによって工事の有無や費用、セキュリティ強度に差があるため、自社の状況に合った方法を選びましょう。
既存の物理鍵に後付けする
手軽に導入できるのが「既存の物理鍵に後付けするタイプ」です。ドアを取り換える必要がなく、専用デバイスをサムターン部分に貼り付けるだけで利用できます。工事が不要なため、短期間かつ低コストで導入できる点が大きなメリットです。原状回復も容易で、賃貸オフィスやシェアオフィス、短期利用施設に適しています。
一方で、ドア形状やサムターンのサイズによっては取り付けられない場合もあり、強度面では専門設置型に比べて劣る点に注意が必要です。強固なセキュリティを求める本社オフィスや研究施設には不向きですが、「まずは低コストで入退室管理を試してみたい」という企業にとっては有効な選択肢といえるでしょう。
【関連記事:スマートロックとは?導入メリット・注意点やおすすめの選び方を解説】
既存の自動ドア・電気錠に後付け
すでに自動ドアや電気錠を導入している施設では、既存の配線に専用コントローラーや認証端末を追加することで、入退室管理機能を後付けする方法があります。工事業者による配線作業や設定は必要ですが、扉の取り換えを伴わないため、比較的短期間で導入できる点がメリットです。
この方法は、中規模以上のオフィスや工場、学校、医療施設などに適しています。ただし、既存設備との相性やメーカー仕様によっては対応が難しい場合もあり、追加工事費用が発生する点はデメリットです。
扉の鍵ごと変更する
既存の錠前を取り外し、指紋認証・顔認証・テンキー入力に対応した電気錠やスマートロックへ完全に交換する方法です。この方法では、物理鍵を廃止し、最新のセキュリティシステムを導入できます。反応速度が速く、認証の確実性も高い点が特徴で、サーバルームや研究所、金融機関など高レベルのセキュリティが求められる場所におすすめです。
また、専門業者による施工のため強度面・耐久性への不安が少ない点もメリットです。一方で、導入コストが高いことや、ドアの規格によっては工事ができない場合がある点がデメリットです。
入退室管理システムの導入前に整理したいこと

入退室管理システムは、セキュリティ強化や労務管理の効率化に役立ちますが、やみくもに導入するとコストがかさんだり、運用に手間がかかったりするおそれがあります。
スムーズに最適なシステムを選ぶためには、まず「何のために導入するのか」「どのように使うのか」といった基本条件を明確にしておくことが重要です。ここでは、導入前に整理しておきたいポイントを解説します。
本当に入退室管理システムが必要なのか
まず、入退室管理システムが必要な理由を整理しましょう。例えば、企業秘密や顧客情報などの重要データを扱う場合は、不正侵入を防ぐために高いセキュリティレベルの入退室管理が欠かせません。
一方で「タイムカード代わりに使いたい」「誰が・いつ入退室したかを簡単に記録したい」といった勤怠管理を目的とするケースもあります。
このように、目的がセキュリティ強化なのか勤怠管理の効率化なのかを整理することで、必要な機能や認証方法(ICカード、指紋認証、顔認証など)を明確にできます。また、コストパフォーマンスの観点から、すぐに導入する必要がない場合もあるでしょう。
入退室者の数はどれくらいか
適切な認証方法や機能を選定するには、入退室者の規模を把握することが大切です。少人数の小規模オフィスであれば、スマートフォン連携や暗証番号入力などのシンプルな仕組みでも十分に対応できます。
一方で、数百人規模の従業員が出入りする大企業や、外部業者・来訪者の出入りが多い施設では、ICカードや顔認証など多数の利用者に対応できる認証方式が必要です。
また、入退室のログ管理やアクセス権限の設定も欠かせません。例えば「役員フロアには限られた人しか入れない」「サーバルームは情報システム部だけが入れる」といった制御を行うには、利用者数に応じて柔軟に管理できるシステムを選ぶことが求められます。
どこに設置するのか
「使い勝手が悪かった」といった導入後の失敗を防ぐためにも、設置環境を事前に整理しておきましょう。導入対象がオフィスの出入口なのか、サーバルームや倉庫といった限定スペースなのかによって、最適なシステムは異なります。
例えば、一般的なオフィスの出入口にはドアに直接取り付けるスマートロック型が適しています。一方、空港や研究所など多数の人が通過する施設では、ウォークスルー型ゲートや改札機タイプの入退室管理が効果的です。
さらに、ビル全体で統合管理を行う場合には、各扉やフロアのアクセス権限を一元的に管理できるクラウド型システムが有効です。
スムーズな入退室を実現!スマートロックの導入は「イッツコム」

スマートロックを導入し、入退室管理を効率化したい場合は、イッツコムが提供する「Connected Portal(コネクティッドポータル)」「Connected Space Share(コネクティッドスペースシェア)」の利用がおすすめです。
ここでは、それぞれのサービスの特徴を紹介します。
店舗・施設の無人運営も可能にする「Connected Portal(コネクティッドポータル)」
「Connected Portal(コネクティッドポータル)」は、特定のユーザーに特定期間だけ利用できる「時限キー」を発行するサービスです。これまで必要だった「鍵の受け渡し」を不要にし、専用アプリとスマートロックを活用して遠隔から解錠・施錠を操作できます。
ICカードや暗証番号を解錠ツールとして設定できるほか、曜日や時間帯ごとに利用制限をかけることも可能です。
さらに、API連携を利用すれば、既存の予約システムや業務アプリとの統合もスムーズに行えます。
レンタルスペースやコワーキングスペース、パーソナルジム、民泊施設、オフィスなど、幅広いシーンで活用できます。
LINEで手軽に施設予約「Connected Space Share(コネクティッドスペースシェア)」
「Connected Space Share(コネクティッドスペースシェア)」は、LINEを活用した施設予約サービスです。専用アプリをダウンロードする必要がなく、利用者は施設のLINE公式アカウントを「友だち追加」するだけで、予約から決済、そしてスマートロックの解錠操作までをLINE上で完結できます。
すでに普及しているLINEをそのまま利用できるため、新規ユーザーでも直感的に操作でき、導入ハードルが低い点が魅力です。
管理者にとってもメリットは大きく、スマートロックと連動した入退室管理をシンプルに運用できます。さらに、IoTデバイスとの連携にも対応しており、カメラやセンサー、家電コントローラーなどとシームレスにつなげられることで、施設全体の運営を効率化できます。
まとめ

入退室管理システムは、企業や施設のセキュリティ強化だけでなく、鍵の受け渡しや利用者対応といった日々の管理業務を大きく効率化できる仕組みです。導入方法には、後付け型の手軽なタイプや、本格的に錠前を取り換える方法があり、自社の規模や利用目的に応じて選択することが重要です。
イッツコムでは、鍵の受け渡しを不要にし、施設の無人運営や効率化を可能にする「Connected Portal(コネクティッドポータル)」、LINEだけで予約から解錠・決済までを完結できる「Connected Space Share(コネクティッドスペースシェア)」という2つのサービスを扱っています。「入退室管理の仕組みを導入したい」という方は、ぜひご利用ください。