生成AIの活用事例7選!生産性向上などビジネス課題解決のヒント
目次
人手不足や生産性向上などのビジネス課題を抱えた多くの企業が、ChatGPTなどの生成AIを上手に活用して課題解決につなげています。さまざまな業界・職種の活用事例から、自社に応用できるアイデアが見つかることもあるでしょう。
この記事では、生成AIの活用シーンや活用事例を解説します。ビジネスシーンで注意したいリスクと対策も知り、生成AIを快適・安全に使いこなしましょう。
生成AIとは?主な種類と活用シーン

生成AI(Generative AI)とは、AI(人工知能)の一種で、学習データに基づき新たなコンテンツを生成する能力を持つものです。文章生成・画像生成・音声生成・動画生成などに特化したタイプが存在し、それぞれの領域で多様なサービスがリリースされています。
ここでは、4種類の生成AIについて、主なサービスと活用シーンを解説します。
文章生成AI(テキスト生成AI)
文章生成AI(テキスト生成AI)とは、高度な自然言語処理技術を駆使し、人間が書いたような自然な文章を生成するAIの総称です。主な文章生成AIには、ChatGPT・Gemini・Microsoft Copilot・Claudeなどがあります。
文章作成・翻訳・要約・アイデア出し・プログラミング・データ分析など、ユーザーが与えるプロンプト次第で多彩な出力に対応可能です。画像ファイルやPDFファイルを分析させ、テキストとして結果を出力することもできます。
また、著名な文章生成AIの機能を組み込んだサービスも数多く登場しています。例えば、Copilot for Microsoft 365やGemini for Google Cloud、GPTモデルを利用できるAzure OpenAI Serviceなどが挙げられます。
画像生成AI
画像生成AIとは、テキストによる指示に基づき、画像を自動で生成するAIの総称です。主な画像生成AIとして、Stable Diffusion・Midjourney・DALL-E・Bing Image Creator・Adobe Fireflyなどがあります。
専門的なデザインスキルがなくても、プロンプト次第で高品質な画像を素早く生成できるのが特徴です。既存の画像を編集・加工したり、複数の画像を組み合わせて新たな画像を生成したりすることも可能です。ビジネスシーンでは広告素材・商品デザイン案・ロゴ・アイコンなどの作成に、医療分野では病状診断や治療シミュレーションへの応用にも広がっています。
音声生成AI
音声生成AIとは、ユーザーからの入力に基づき、人間が話しているような音声を生成できるAIの総称です。主な音声生成AIには、わずか3秒の音声サンプルから話者の声色・抑揚・感情表現を再現するVALL-Eや、テキストデータを自然で人間らしい音声に変換するGoogle Cloud Text-to-Speechなどがあります。
ビジネスシーンでは、YouTube動画のナレーション作成、コールセンターでの自動応答システム、オンライン学習教材・社内研修資料・プレゼン資料の音声化や多言語対応といった用途で活用されています。
動画生成AI
動画生成AIとは、入力文に沿って動画を生成したり、既存の画像や動画をもとに新たな映像を作成したりできるAIの総称です。主な動画生成AIには、Sora・Veo3・Runway・Canvaなどがあります。
専門的な知識やスキル、機材がなくても簡単に動画を作成できる点が特徴で、撮影や編集にかかる時間やコストを大幅に削減できます。既存の動画を素早く編集することも可能です。
ビジネス活用としては、マーケティング領域におけるターゲット層別のプロモーション動画の生成、教育領域での学習教材や解説動画の作成などが挙げられます。
生成AIの活用事例7選

生成AIはアイデア次第で、さまざまなシーン・目的に活用できます。例えば、従業員向けの生成AIアシスタントによる生産性向上や、コールセンター業務を自動化する生成AIサービスによる応対業務の効率化・品質改善などが挙げられます。
他にも、パッケージデザイン・品質マネジメント・リバースエンジニアリング・校務DXなど、さまざまな分野で応用されています。ここでは、生成AIの活用事例7選を解説します。
従業員専用の生成AIアシスタントに活用した事例
SMBCグループは、「Azure OpenAI Service」のリリースからわずか4か月後の2023年7月、従業員専用の生成AIアシスタント「SMBC-GAI」の利用を開始しました。自社向けにカスタマイズしたChatGPTの機能を、セキュアなAzure OpenAI Serviceを通じて、従業員が日々利用しやすいMicrosoft Teamsに組み込み、チャットボット形式で社内全体に展開しています。
SMBC-GAIは、専門用語の検索やメールの下書き作成、議事録や記事の要約・翻訳、ソースコードの自動生成など、あらゆる業務で活用され、生産性向上に寄与しています。他にも、「Oracle Cloud ERP」によって経理業務の大半を自動化するなど、グループ全体でAI活用を促進しています。
マーケティング部門の時間創出や戦略立案
キリンホールディングス株式会社は、2024年から生成AI活用プロジェクト「KIRIN BuddyAI Project」を推進しています。2025年5月からは、国内従業員約1万5,000人に向けて、自社構築の生成AIツール「BuddyAI」の展開を始めました。機能改良やユーザー教育が進んだ結果、マーケティング部門では約3万9,000時間の時間創出効果が見込まれています。
さらに2025年7月には、専門性を要求する業務のために「ChatGPT Enterprise」を導入しました。キリングループの戦略立案・企画系、研究開発、マーケティングの各部門の一部において、高度な検索・推論機能を活用し、単なる効率化にとどまらず、生産性向上と価値創造の強力な推進を目指しています。
コールセンターの応対業務の効率化・品質改善
慢性的な人手不足が課題となっているコールセンターに向けて、IT大手各社が生成AIを活用したサービスの開発を進めています。
例えば、ソフトバンク株式会社の完全子会社であるGen-AX(ジェナックス)株式会社は、問い合わせ情報をデータ化・蓄積し、オペレーションを効率化する「X-Boost(クロスブースト)」や、ユーザーに適した回答を自律思考型AIが音声で行う「X-Ghost(クロスゴースト)」を開発しました。
これらのサービスは、応対業務の品質の平準化や継続的な改善に加え、人為的ミスの削減による顧客体験の向上を支援します。
新規カテゴリ商品のパッケージデザイン
育児・マタニティ・介護用品などの製造・販売を行うピジョン株式会社は、2025年5月に子ども向け新商品を発売するにあたり、同社にとって全く新しいジャンルの商品であったことから、パッケージデザインに特化した生成AIを活用しました。
人手によるデザイン提案は、通常2週間で5案程度ですが、生成AIを活用することで、さまざまな方向性から100案以上を作成することができました。ヒートマップや好感度予測スコアなどもAIが分析し、精度高くデザイン案を絞り込むことで、商品開発期間の大幅な短縮とコスト削減につながっています。
他にもDX施策の一環として、社内で日常的に利用するGoogle Workspaceと親和性の高いGeminiを導入し、2024年秋からピジョングループ全体で運用を開始しました。Geminiは、データ検索・文章作成・翻訳・アイデア出しなど多岐にわたる業務を支援し、業務効率化の効果が実感されています。
製造業における品質マネジメントの強化
日本精工株式会社は、2023年から生成AIを文章作成や情報検索に活用してきました。2024年10月には、同社の専門的な業務・領域に対応する独自生成AIアプリの開発に着手し、機能設計からわずか半年で、生成AIを活用した品質トラブル参照アプリを導入しています。
約4,000件の品質トラブルデータを集約したこのアプリは、設計・製造・品証メンバーを中心とした国内5,000名以上の従業員に提供されています。製品開発時のリスク要因を調べる際などに、グラフによる可視化と生成AIによる要約文を得ることができ、従業員の知識レベルに関係なく、調べたいデータに素早くアクセスできる点が特徴です。
今後は、営業・物流メンバーなど製品ライフサイクルに関わるさまざまな分野の従業員にも提供範囲を広げ、品質マネジメントのさらなる強化を図る見込みです。
運用困難なシステムのリバースエンジニアリング
東芝デジタルエンジニアリング株式会社は、顧客から「長年にわたるシステム改修や保守運用担当者の退職により、ソースコードが複雑化・ブラックボックス化している」「システムのバージョンアップやクラウド移行を検討しているが、設計書が最新化されていない」といった相談を受けていました。
こうした課題を解決するため、ソースコードから設計情報を復元するリバースエンジニアリングに取り組んでいましたが、全てを人手で行う場合、大量のエンジニアが多大な工数をかける必要があります。
そこで、エンジニアの補助として生成AIの活用を決定し、「Azure OpenAI Service」によってソースコードや運用手順書を解析する仕組みを導入しました。この取り組みにより、担当するエンジニアの少人数化や作業期間の大幅な短縮が可能となり、生産性向上に貢献しています。
自治体・小中学校における校務DX
小中学校の教員の長時間労働が深刻な問題となり、校務DXによる教員の負担軽減が求められる中、全国の自治体で生成AIの活用が模索されています。
例えば大阪府枚方市は、2024年に「校務生成AI実証事業」を実施し、小中学校10校の教員が生成AIを校務に活用しました。活用前後を比較すると、平均40分かかっていた事務作業を平均24分に短縮、授業準備は平均50分から平均20分まで短縮でき、業務の効率化や負担軽減を実感できる結果となりました。
また兵庫県三田市教育委員会が大阪教育大学と共同で進める「MIRAIノートプロジェクト」は、生成AIを活用したキャラクターと子どもたちが気軽に相談・対話できる環境を提供し、生徒指導の課題の複雑化や不登校児童・生徒の増加といった問題の解決を目指しています。
生成AIをビジネス活用する際の注意点

生成AIはさまざまな業界・業種の課題解決に役立つ一方、いくつかの注意点もあります。ビジネス活用の際は、適切なリスク対策を講じることが大切です。主に、情報漏えいや著作権侵害のセキュリティ対策、生成AIに特有のハルシネーションの対策が求められます。
情報漏えいや著作権侵害のセキュリティ対策
どのような生成AIであっても、機械学習・ディープラーニングの技術を用いるため、大量のデータを学習させることで出力結果の精度を高めています。
利用するサービスによっては、ユーザーからの入力が学習データとして活用されることがあり、それが機密情報や個人情報の漏えいにつながる恐れがあります。また、出力結果が学習元のデータと同一または類似している場合、著作権侵害のリスクも生じます。
生成AIを安全に利用するための基本的対策としては、サービスの利用規約を精査することに加え、プロンプトに関する注意事項や出力結果の確認方法を社内で共有することが重要です。
生成AIに特有のハルシネーションの対策
生成AIに特有の現象として、事実とは異なる情報を、あたかも真実であるかのように生成してしまう「ハルシネーション(幻覚)」が挙げられます。出力結果は体裁が整い、人間が作成したように自然に見える場合でも、あくまで機械がプログラムに基づいて生成したものです。
そのため、出力結果をそのまま業務に使用することにはリスクがあり、ファクトチェックの徹底など適切な確認作業が求められます。
生成AI活用を快適・安全にする通信環境整備ならイッツコム!
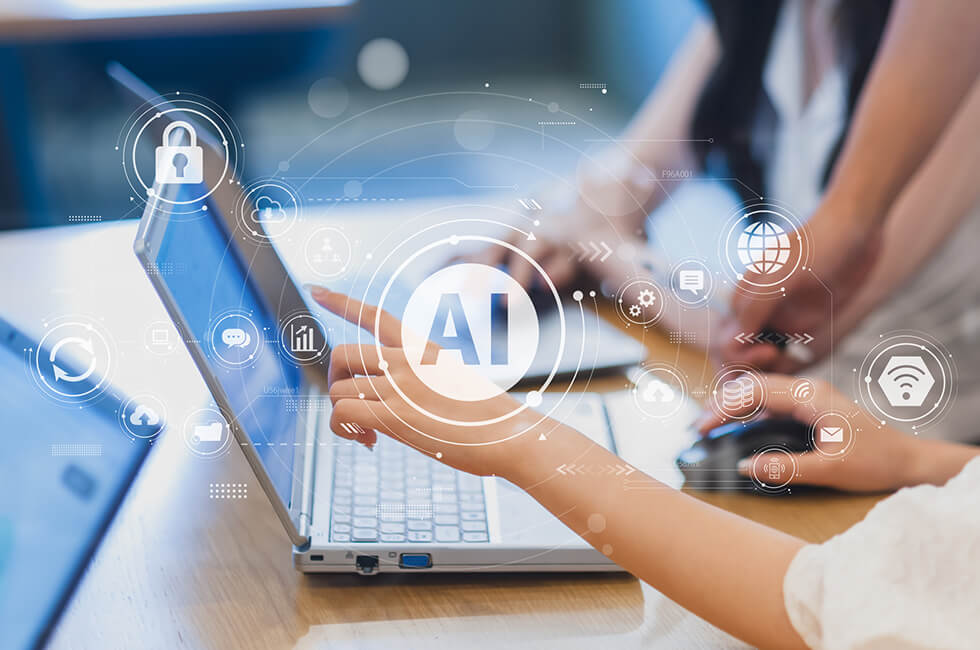
生成AIをビジネスシーンで快適・安全に活用する基盤として、通信環境の整備は重要です。イッツコムなら、「かんたんWi-Fi」でオフィス内のWi-Fi・インターネット通信を安定化でき、「モバイル閉域接続」でリモートワーカーにもセキュアな通信環境を提供できます。
「かんたんWi-Fi」でオフィス内の生成AI利用時の通信を安定化
フリーアドレス制を導入しているオフィスなどでは、PCやモバイルデバイスから社内LANやインターネットに接続する際、Wi-Fi経由で通信を行うことも多いでしょう。オフィス内で生成AIの利用が活発化すると、Wi-Fi経由でインターネット通信をするデバイス数やデータ量が増え、通信の遅延や途絶を起こす恐れがあります。
通信の安定性は、要所に業務用Wi-Fiアクセスポイント(AP)を増設することで確保できます。イッツコムが提供する「かんたんWi-Fi」は、高性能APを安価にレンタルできるサービスです。
「ハイエンド6」プランのAPは高速・高セキュアなWi-Fi6に対応し、1AP当たり最大100台まで、快適なWi-Fi接続ができます。ゲストWi-Fi機能も完備のため、訪問者向けのフリーWi-Fiも安全に提供でき、業務用Wi-Fiネットワークの安定性確保にも役立ちます。
【関連記事:アクセスポイントとは?LANの仕組みや機器の機能も一挙解説】
「モバイル閉域接続」でリモート環境の生成AI活用も安全に
リモートワーカーなどが生成AIを活用する際、安全性の低いフリーWi-Fiに接続するなど、セキュリティ上の懸念があります。
イッツコムが提供する「モバイル閉域接続」は、法人データSIMと閉域網接続を組み合わせ、社外でのインターネット接続の安全性を高めるソリューションです。
インターネット接続の際は閉域網と社内LANを経由する仕組みで、社外デバイスの通信の事実自体を秘匿でき、さらにオフィス側で通信ログを取得できます。専用SIMカードで経路判別するため、VPNアプリの設定や、利用者ID・パスワードの管理は不要です。
AIに関連する他のトピックが気になる方はこちら!イッツコムが詳しく解説

「クラウドAI」について詳しく知りたい方はこちら
クラウドAIはクラウドの計算資源を活用するため、サーバ管理なしで高度なAIを導入可能です。低コスト・短期間に導入可能であり、需要予測や自動運転、スマート農業、文書メタデータ抽出などで業務を横断的に効率化できます。通信環境や情報漏えい、サービス停止への備えと、信頼できるベンダー選定が重要です。以下の記事では、クラウドAIについても詳しく解説しています。
【関連記事:クラウドAIとは?メリットや導入時の注意点を知り業務に生かす】
「AI翻訳」とは?RBMT・SMT・NMTの違いやサービスの選び方
AI翻訳を活用すれば、誰でも一定水準の翻訳精度を得やすく、多言語対応が可能になります。RBMT・SMT・NMTの3方式があり、現在主流のNMTは文脈を踏まえた自然な訳文を高速かつ低コストで提供できる点が特長です。一方で、専門分野や口語表現への対応状況、翻訳可能な言語数、セキュリティ対策などを確認することが大切です。通訳が必要な場面では音声認識や音声合成を備えたAI通訳機が有効であり、POCKETALKは多言語・高精度で実務に適しております。以下の記事では、AI翻訳についても詳しく解説しています。
【関連記事:AI翻訳とは?RBMT・SMT・NMTの違いやサービスの選び方】
まとめ

著名な生成AIサービスは汎用性が高く、アイデア次第でさまざまな業界・職種の課題解決に役立ちます。企業や自治体の活用事例も参考にしつつ、自社のビジネスにどのように活用できるか、しっかりと分析・検討しましょう。
生成AIの社内利用が活発化すると、ネットワーク帯域の圧迫やリモート環境のセキュリティ対策などが問題になることもあります。生成AIを快適・安全に利用するための通信環境整備をお考えなら、オフィス内のWi-Fi環境強化にもセキュアなモバイル回線整備にも対応できるイッツコムにご相談ください。







