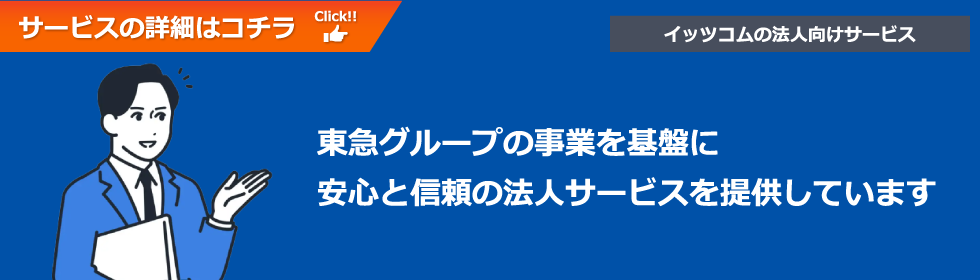アンチパスバックとは?「共連れ」を防ぐセキュリティ強化の方法
目次
オフィスや工場、研究施設などで導入される入退室管理システムには多様な機能があり、その中でも注目されている機能の1つが「アンチパスバック」です。
この記事では、アンチパスバックの利用例や導入時の注意点を分かりやすく解説します。合わせて、アンチパスバック以外のセキュリティ強化策や、入退室管理システムを選ぶ際のポイントも紹介します。導入を検討する際の参考にしてください。
アンチパスバックとは

アンチパスバックとは、入室時の認証記録がない人が、正規の手続きを経ずに退室できないようにするアクセス制御の機能です。入室と退室の記録をセットで管理することで、建物内に不正に侵入した人物が自由に出られないよう制限をかけます。
守衛を常駐させるよりもコストを抑えられる上、共連れによる不正の防止にもつながるため、情報漏えいや内部犯罪への対策としても有効です。
ここでは、アンチパスバックの利用例や、似た機能を持つ「グローバルアンチパスバック」との違いについて解説します。
アンチパスバックの利用例
アンチパスバックの代表的な利用例が「共連れ防止」です。共連れとは、正規の従業員が入室認証を行った直後に、認証を受けていない人が一緒に入り込む不正行為を指します。
例えば、オフィスに従業員Aがカードをかざして入室した直後、社員証を持たない人物Bが後ろからすり抜けて入ってしまったとしましょう。通常の入室管理では、そのまま建物内への侵入を許してしまいます。
しかしアンチパスバックを導入していれば、Bは「入室記録がない」と判断され、退室時にゲートを通過できないよう制御されます。これにより、不審者が施設から出ようとした際に発見されやすくなり、セキュリティ担当者が迅速に対応できる環境を整えることが可能です。
グローバルアンチパスバックとの違い
通常のアンチパスバックは、各扉単位で入退室の記録を管理する仕組みであり、1つの扉で入室した場合、同じ扉での退室を前提とする運用が一般的です。一方、グローバルアンチパスバックは複数の扉をまたいで通行履歴を一元的に管理できるため、Aの扉から入室してBの扉から退室することも可能です。
複数の出入口がある大規模なオフィスや研究施設では、通常のアンチパスバックよりもグローバルアンチパスバックが適しています。
アンチパスバックの導入前に知っておきたいこと

アンチパスバックは不正入室対策として有効ですが、導入にあたってはいくつかの注意点も存在します。運用方法を誤ると、従業員や利用者に不便を与えたり、誤作動を引き起こしたりする可能性があるため、あらかじめデメリットや運用上の留意点を理解しておくことが大切です。
ここでは、そのデメリット・注意点を紹介します。
入室時のミスで退室できなくなる可能性がある
アンチパスバックは、入室記録がない人が退室できない仕組みのため、急いでいてカードをかざさず共連れで入ってしまった場合や、社員証を忘れて他の人と一緒に入ってしまった場合、退室時にゲートで止められてしまうことがあります。結果として、正規の従業員であっても「入室記録がない」と判定され、退室できなくなるケースが起こり得ます。
こうしたトラブルを防ぐには、従業員に対するルールの周知徹底と、管理者による一時的な制御解除機能をあらかじめ用意しておくことが重要です。
共連れを完全に防げるわけではない
アンチパスバックは共連れ防止に効果的ですが、それだけで不正を完全に防げるわけではありません。例えば、退室時に正規の従業員の後ろから一緒に出られてしまうと、システムだけでは不正を検知できないケースもあります。
そのため、アンチパスバックだけでセキュリティを完結させるのではなく、監視カメラの設置や有人管理、物理的なセキュリティゲートとの併用など、多層的な対策を講じることが望ましいでしょう。
アンチパスバック以外のセキュリティ強化方法

強固なセキュリティ環境を構築するには、アンチパスバックの仕組みを基盤としつつ、物理的な障壁や高度な認証技術、監視・検知システムなどのセキュリティ対策を組み合わせることが効果的です。
以下を参考に、アンチパスバックの弱点を補う形で、セキュリティ強化を検討しましょう。
セキュリティゲート
セキュリティゲートとは、入退室を制御するための物理的なゲートのことです。オフィスや研究施設、イベント会場などで利用されており、認証が済んだ人のみが通過できる仕組みになっています。代表的なタイプは、「フラッパー式」と「アーム式(クロス式)」の2種類です。
フラッパー式は、改札口のようにフラップと呼ばれる板が通路をふさぎ、認証に成功すると自動で開きます。スムーズに通過できるため、大人数が利用する環境に適しています。
一方、アーム式はゲートに設置されたバーが回転し、認証後に利用者自身が押して進む仕組みです。1人ずつしか通過できないため、共連れのリスクを大幅に低減できます。
インターロックゲート(二重扉)
インターロックゲートは、二重扉を備えた「1人ずつしか通過できない」構造のゲートです。1つ目の扉が閉じない限り、2つ目の扉が開かない仕組みになっており、内部は小部屋のような空間になっています。利用者は1つ目の認証を行って扉を通過し、その後、小部屋内で次の認証を行うことで、はじめて内部エリアにアクセスできるという流れです。
この方式では2人以上が同時に入室することが構造上できないため、共連れを物理的に防止できます。空港の出入国管理や金融機関、研究施設など、高度なセキュリティが求められる場所に適しています。
監視カメラ
監視カメラは、不正行為の抑止力を高める上で効果的です。カメラを設置するだけでも、「常に見られている」という心理的な圧力が働き、不正行為の抑止につながります。
さらに、カメラの映像をリアルタイムで監視室に送信し、ゲート付近の状況を常に把握できる体制を整えることで、不正な入退室の試みを即座に発見し、警備員や管理者がすぐに駆けつけるといった即応対応も可能になります。
加えて、映像は不正侵入が発生した際の証拠としても活用でき、管理者が状況を迅速に把握する手がかりとなる点も大きなメリットです。
【関連記事:監視用SIMカメラのメリットとは?機種・SIMカードの選び方も紹介】
共連れ検出
共連れ検出機能は、入退室ゲートを通過する際に「複数人が一緒に入っていないか」を監視する仕組みです。監視カメラや赤外線センサーなどを使い、通過人数と認証回数を照合します。例えば、1人分の認証しか行われていないのに2人が同時に通過した場合、システムが異常を検知し、管理者に通知を送ったり、音声アラームを鳴らしたりすることができます。
共連れ検出を活用すれば、共連れを試みた不正者を即座に発見できます。ドア付近で音声警告を発するシステムもあり、利用者のセキュリティ意識を高める効果も期待できます。
2名照合機能(ツーパーソン機能/ダブル認証機能)
2名照合機能は、1人の認証だけでは扉が開かず、2人分の認証が必要になる仕組みです。例えば、入室時に従業員2人がそれぞれのカードをかざすことで、はじめて入室が可能になります。
この機能は、金融機関の金庫や極秘のサーバ室など、1人の従業員による不正操作や情報持ち出しを避けたい場所で効果的です。システムによっては、「部屋にすでに複数人が滞在している場合は、1人分の認証で入室できる」といった設定も可能です。
アクセスレベル設定
アクセスレベル設定とは、利用者の属性(役職・部署・業務内容など)に応じて、入室可能な範囲を制限できる機能です。例えば、一般従業員はオフィスフロアのみ、管理職は会議室やサーバルームも利用可能といった形で、柔軟に設定できます。
この機能を導入すれば、必要以上に機密情報へアクセスされるリスクを減らし、内部不正の抑止にもつなげられます。また、退職者や部署異動者の権限を即時に変更・無効化できるため、運用面でも利便性が高い仕組みです。
生体認証
生体認証は、指紋・顔・虹彩・静脈など、人の身体的特徴を使って本人確認を行う認証方式です。ICカードや暗証番号と違い、紛失・盗難・なりすましのリスクが低いため、より確実な本人確認が可能になります。近年では、顔認証技術の向上により、マスクを着けたままでも認証できるシステムや、高速な認証が可能な製品も登場しています。
生体認証を導入すれば、ICカードを持ち歩いたり、認証パスワードを記憶したりする必要がなくなり、利用者の利便性も向上します。
ルートチェック機能(動線管理)
ルートチェック機能は、あらかじめ設定された経路を通過しなければ入室できない仕組みです。例えば、「エントランスを通過してからでないと研究室に入れない」といったように、利用者の移動経路をシステム上で管理します。
この機能を活用すれば、裏口や制御されていない扉からの侵入を防ぐことができ、不正者の侵入リスクを低減できます。広い工場や研究所、複数の区画に分かれた施設などで効果を発揮するセキュリティ機能といえます。
入退室管理システムを選ぶ視点とポイント

アンチパスバックやその他のセキュリティ機能を知り、本格的に入退室管理システムの導入を検討した企業も多いのではないでしょうか。入退室管理システムは、製品ごとに導入形態や搭載機能が大きく異なるため、自社の環境に適したものを選ばなければ、十分な効果を得ることはできません。
ここでは、入退室管理システムを選定する際に注目したいポイントを解説します。
オンプレミス型orクラウド型
入退室管理システムの導入方法は、大きく分けて「オンプレミス型」と「クラウド型」があります。オンプレミス型は、自社内のサーバやネットワークにシステムを構築する方式で、セキュリティ面において高い安心感が得られるのが特徴です。ただし、初期費用が高くなりやすく、拡張や更新の際には専門知識が求められる場合もあります。
一方、クラウド型はインターネット経由でシステムを利用できるため、導入コストを抑えやすく、リモートワークや複数拠点での利用にも適しています。スマートロック(物理鍵が不要な錠前)と連携する製品も多く、スマートフォンアプリを使って扉を解錠したり、遠隔地からリアルタイムで入退室状況を把握したりできる点も魅力です。
【関連記事:スマートロックとは?導入メリット・注意点やおすすめの選び方を解説】
機能
入退室管理システムには、多彩な機能が搭載されています。「アンチパスバック」や前述した「アクセスレベル設定」「ルートチェック機能(動線管理)」に加え、以下のような機能もあります。
- タイムスケジュール設定:時間帯ごとに認証の有無を切り替えできる機能
- オペレーション操作ログ:管理ソフトを通じて入退室や設定変更の操作履歴を記録する機能
- マルチ認証:「ICカード+暗証番号」などのように複数方式を組み合わせて認証する機能
- 時限ルート:特定の操作により、一定時間だけ特定の扉を開放または制限する機能
- 優先ID:特定人物が在室している場合のみ他の人の入室を許可する機能
これらの機能を組み合わせることで、セキュリティレベルを柔軟に高めることができます。オフィスや工場、研究施設など、利用シーンに応じて必要な機能を洗い出してみてください。
設置方法
入退室管理システムの設置方法は、大きく「後付けタイプ」と「鍵交換タイプ」の2種類に分けられます。既存の扉に後付けできるタイプは、工事が最小限で済み、導入コストを抑えやすい点がメリットです。
一方、鍵交換タイプは扉の錠前自体を電気錠やスマートロック(電子錠)に交換する方式であり、高いセキュリティ性や多機能化が可能です。ただし、相応の工事費用が発生するため、導入に際しては慎重な検討が求められます。
認証方法
入退室管理システムで利用できる認証方法には、暗証番号入力、ICカードや社員証、生体認証(指紋・顔など)、スマートフォンアプリによる認証があります。暗証番号は導入コストが低く手軽ですが、番号が漏れるリスクがあります。
ICカードは管理が容易で、紛失時も再発行が可能ですが、盗難への対策が必要です。生体認証は偽造が困難なため、セキュリティ性が高い認証方式といえます。スマートフォンアプリを使った認証は利便性に優れ、クラウド型システムとの相性も良好です。
利便性とセキュリティのバランスを踏まえて、最適な認証方法を検討してみてください。
他システムとの連携
入退室管理システムは、他のシステムと連携させることで、セキュリティの強化だけでなく、労務管理や業務効率化にも役立ちます。たとえば、勤怠管理システムと連携することで、入退室記録をそのまま勤務時間として反映でき、打刻漏れや不正打刻の防止につながります。
また、火災報知器や非常放送システムと連携すれば、災害時に自動で扉を解放する仕組みを構築することも可能です。
サポート内容
安心して入退室管理システムを運用するためには、導入前後のサポート内容が非常に重要です。「トラブルが発生した際に迅速な対応を受けられるか」「システムのバージョンアップが定期的に提供されるか」といった点を確認しておくことで、長期的に安定した運用が可能になります。
また、導入時に設置工事や初期設定のサポートがあるかどうか、利用者への操作説明やマニュアルの提供があるかも、あらかじめチェックしておきたいポイントです。
カメラやセンサーと連携できるスマートロックの導入ならイッツコム!

オフィスや店舗、レンタルスペースなど、施設のセキュリティと利便性を両立させたい場合には、イッツコムが提供する「Connected Portal(コネクティッドポータル)」や「Connected Space Share(コネクティッドスペースシェア)」の活用がおすすめです。
鍵の受け渡しや予約管理を効率化できるため、施設全体の運営がスムーズになります。ここでは、それぞれのサービスについて紹介します。
特定のユーザーにだけ「時間限定」の入室権限を与える「Connected Portal(コネクティッドポータル)」
「Connected Portal(コネクティッドポータル)」は、スマートロックとゲートウェイを組み合わせて、特定のユーザーに特定の期間だけ有効な「時限キー」を発行できるサービスです。シェアオフィスやコワーキングスペース、貸会議室、ジム、民泊などの施設において、管理者と利用者の間で発生する鍵の受け渡しを不要にします。
専用アプリを通じて、ユーザーごとに曜日や時間帯を細かく設定できるため、管理者は遠隔から柔軟に入退室をコントロール可能です。また、API連携にも対応しており、ホテル管理システム(PMS)と組み合わせることで、予約から時限キーの発行までを自動化することもできます。24時間営業の会員制施設や無人店舗の運営にも対応可能です。
一時利用に適した施設予約サービス「Connected Space Share(コネクティッドスペースシェア)」
「Connected Space Share(コネクティッドスペースシェア)」は、LINE公式アカウントを活用した施設予約サービスです。利用者は専用アプリをインストールする必要がなく、普段使っているLINEアプリ上で、予約から入室、決済までを一貫して行えます。
LINE上で友だち登録するだけで、スペースの予約やスマートロックの解錠が可能になり、クレジットカードやLINE Payによる決済にも対応しています。ドロップイン型のコワーキングスペースや貸会議室の運営に最適なサービスです。
まとめ

アンチパスバックとは、入室時の認証記録がない人を退室させない機能のことで、「共連れ」を防ぐ効果があります。しかし、アンチパスバックだけではセキュリティが不十分な場合もあるため、セキュリティゲートやインターロックゲート、監視カメラなどを併用するとよいでしょう。
また、「鍵の受け渡し業務を効率化したい」「セキュリティと利便性を両立させたい」という場合は、イッツコムが提供する「Connected Portal(コネクティッドポータル)」「Connected Space Share(コネクティッドスペースシェア)」がおすすめです。
「Connected Portal(コネクティッドポータル)」は特定ユーザーに時限的な入室権限を付与できるサービス、「Connected Space Share(コネクティッドスペースシェア)」はLINEだけで予約から入室・決済まで完結できるサービスです。気になった方は、お気軽にお問い合わせください。