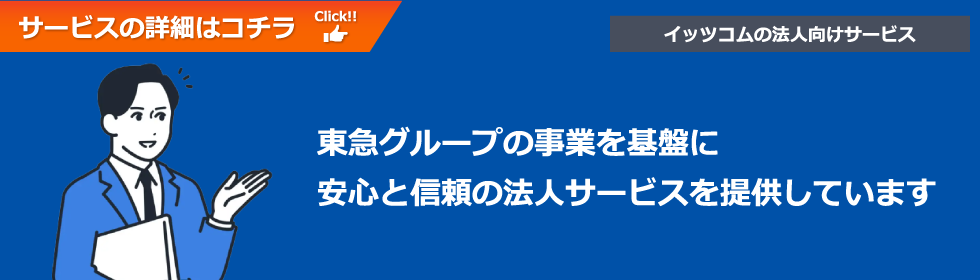介護事業者のBCPは見直し必須?手順やポイントも分かりやすく解説
目次
BCPとは、自然災害や感染症の蔓延など、事業継続を脅かす事態の発生を想定し、重要な事業の継続や早期復旧を目的として策定される方針・体制・手順などを示した計画です。Business Continuity Planの略で、事業継続計画や業務継続計画と訳されます。
介護サービス事業者には、このBCPの策定・運用が義務付けられており、策定後も計画の実効性を高めるためには、定期的な訓練や検証、見直しを行うことが重要です。
この記事では、介護サービス事業者におけるBCPの策定や見直しの必要性、および具体的な手順とポイントについて解説します。
介護サービス事業者が策定必須のBCPとは?

2021年度と2024年度の介護報酬改定により、介護サービス事業者におけるBCP策定は義務化されており、未策定の場合は(一部例外を除いて)基本報酬が減算されます。
BCPは想定するリスクなどによって策定すべき内容が大きく異なり、策定後も実効性を高めるための見直しが必要です。介護サービス事業者においては、地震の発災などを想定した「自然災害BCP」や、新型コロナウイルス感染症の蔓延などを想定した「感染症BCP」の策定・運用が求められます。
策定後の見直しも重要なBCP
介護サービスは、要介護者や家族などの生活を支える上で不可欠なものです。大地震やパンデミックなどが発生した場合でも、利用者が必要とするサービスを継続的に提供することが求められます。
そのためには、事業継続に向けた計画の作成と、緊急時を想定した対策や訓練の実施が重要です。BCPは作成して終わりではなく、継続的な検証と見直しを繰り返すことで、各施設・事業所の状況に即した内容へと発展させていくことが望まれます。
防災計画とBCPの違い
防災計画の目的は、人命の安全確保や物的被害の軽減であり、これはBCPの大前提です。防災計画は災害リスクを把握し、避難などの対応を訓練するものですが、BCPはその後の業務継続を目的とした計画です。
つまりBCPとは、防災計画に加えて重要業務の継続や早期復旧を目指すものです。特に介護事業では、サービスの継続が人命に直結するため、防災計画を前提としたBCPと、その実効性を高めるPDCAサイクルの運用が重視されます。
2021年度の介護報酬改定でBCP策定が義務化
2021年度の介護報酬改定により、全ての介護サービス事業者を対象に、BCPの策定や、それに基づく研修・訓練(シミュレーション)の実施が義務付けられました。当初は努力義務として3年の経過措置期間が設けられていましたが、2024年4月から完全に義務化されています。
新型コロナウイルス感染症は、2023年5月に感染症法上の位置付けが5類感染症へと移行しましたが、移行後も施設内でクラスターが発生するなど、感染症への対応は引き続き必要です。
また、短時間強雨(1時間に50mm以上の雨、「滝のように降る雨」)の年間発生回数と降水量は増加傾向にあり、直下地震は日本全国どこでも起こり得ます。こうした広域的・長期的な被害を想定し、実効性の高いBCPを策定して備えておくことが重要です。
2024年度の介護報酬改定で基本報酬の減算措置が新設
2024年度の介護報酬改定により、介護サービス事業者において感染症BCPまたは自然災害BCPのいずれか、もしくは両方が未策定の場合、基本報酬を減算する新たな措置が設けられました。具体的な内容は以下の通りです。
- 施設・居住系サービス:所定単位数の3/100に相当する単位数を減算
- その他のサービス:所定単位数の1/100に相当する単位数を減算
当該措置の対象は、訪問介護・通所介護(デイサービス)・共同生活介護(グループホーム)など、特定福祉用具販売を除く全ての介護サービス事業者です。その他例外として、居宅療養管理指導については、2024年3月31日までとされている義務付けにかかる経過措置期間は3年間延長されます。
介護サービス事業者がBCPを策定・運用するメリット

BCPは、従業員などの安全を確保することを前提に、緊急時における初動対応や、重要なサービスの継続・早期復旧に向けた計画を定めるものです。介護サービス事業者においては、BCPの策定や平時からの備えが、事態の収束まで入所者・利用者と職員の心身の安全を守ることにつながります。
また、BCPの策定や見直しを進めるにあたっては、政府や自治体による支援制度を活用することも可能です。
入所者・利用者の安全を確保できる
介護サービス事業者がBCPを策定し、感染症の蔓延や自然災害の発生に備えることは、入所者・利用者の安全確保に直結します。
介護保険のサービス利用者は、体力が弱い高齢者や40歳以上の特定疾病のある方です。感染した場合に重症化のリスクが高く、自然災害の発生時には深刻な人的被害が生じる危険性もあります。
これらのリスクに対し、緊急時の避難誘導や医療体制などの対策を事前に講じ、職員に対して適切な教育・訓練を行っておくことが、入所者・利用者の健康や生命を守ることにつながります。
職員の安全を確保できる
BCPの策定は、職員の安全確保の観点からも重要です。感染拡大時や自然災害発生時に事業を継続することは、職員の感染リスクや被災リスクを高めるだけでなく、長期間勤務や精神的打撃など、過酷な労働環境にさらされる懸念もあります。
また、労働契約法第5条(使用者の安全配慮義務)に基づき、適切な措置を講じることは使用者の責務です。
緊急時における業務フローや連絡・協力体制をあらかじめ入念に計画し、施設・事業所全体でシミュレーションを行うことで、職員の心身の安全をより確保しやすくなります。
重要なサービスを継続できる
介護事業者は、入所者や利用者の健康と生命を守るという重大な責任を担っています。BCPは、重要な業務の継続や早期復旧を目的として策定されるものであり、緊急時にもサービスを途切れさせない体制を整えることに大きな意義があります。
特に入所施設では、入所者にとっての生活の場を守るために、被災後も最低限のサービスを提供し続けることが求められます。ライフラインの途絶や物資・人手の不足といったリスクを想定し、自力での継続と避難の両方のケースに備え、十分な検討と準備を進める必要があります。
通所や訪問の事業所においても、業務縮小や閉鎖といった事態を見越し、利用者への影響を最小限に抑えるための対策を講じておくことが重要です。
税制優遇や優遇金利の適用を受けられる
BCPの策定および教育・訓練を行い、政府や自治体が主導する制度を利用すると、税制優遇や優遇金利の適用を受けられる場合があります。
自然災害BCPに関する税制優遇の例は、自然災害への対策強化のために行う設備投資を後押しする「中小企業防災・減災投資促進税制」です。中小企業等経営強化法の事業継続力強化計画または連携事業継続力強化計画の認定を受けると、当該計画で予定された設備導入を行った場合、特別償却16%の税制措置を受けられます。
また、内閣官房国土強靱化推進室がガイドラインを制定する「国土強靱化貢献団体認証(レジリエンス認証)」を取得すると、金融機関で優遇金利の適用などを受けられます。他にも自治体の支援制度などを活用できる可能性があるため、BCPの策定や見直しの際には、制度の有無や条件などを調べてみましょう。
介護サービス事業者がBCPを策定・見直しする流れ

BCPは一度策定して完了するものではありません。PDCAサイクルを回し、定期的な訓練や検証・見直しで実効性を高めることが必要です。介護サービス事業者において、特に以下のようなケースは推進体制から見直す必要があります。
- 感染症BCPは策定していても自然災害BCPは策定していない
- 策定後にBCPを前提とした備蓄や訓練などが行われていない
- 1年以上前に策定したまま見直しがされていない
ここでは、BCPの策定・見直しの流れを解説します。
基本方針や推進体制を決定する
まず、策定するBCPの目的と、平時・緊急時に誰が主導して対応を進めるのかを明確にすることが必要です。以下のような観点から、基本方針を新たに定めるか、既存の内容を見直しましょう。
- 施設・事業所単位か、法人全体か
- 自然災害BCPか感染症BCPか、または両方か
- 自然災害では外部支援までの自立、感染症では長期的被害を想定するか
あわせて、対策本部の体制もあらかじめ決めておきましょう。担当者名・部署・権限・役割を一覧化しておくことが重要です。
被災リスクを把握し対策の指針を得る
リスクの種類や影響度によって、備えや対応の内容は大きく異なります。施設・事業所ごとの被災リスクを洗い出し、その結果を基に対策の指針を得ることが重要です。
自然災害については、立地の影響が大きいため、ハザードマップを活用して地震・水害・土砂崩れ・液状化などのリスクを確認し、必要な対策を検討します。マップの内容は、定期的に見直すようにしましょう。
感染症対策では、「国立健康危機管理研究機構(JIHS)」の情報が有効です。この機関は2025年4月に発足し、科学的根拠に基づいた迅速かつ正確な情報提供が期待されます。
優先して継続・復旧すべき業務を選定する
感染症や自然災害の発生時には、人員不足やインフラ停止が想定され、全ての事業を継続することは困難です。入所系サービスなど、優先的に継続・復旧すべき業務をあらかじめ定めておきましょう。
発災直後から必要となる職員数や出勤可能者をイメージし、役割分担やスケジュールを事前に立てておくことが有効です。
また、業務ごとに継続・追加・削減・休止といった分類を設けて具体的な対応方針を作成することも効果的です。可能であれば、作業手順書なども整備しておくと望ましいです。
設備ごとなどで詳細に緊急時・平時の対応を決める
施設内の設備や備蓄品について、緊急時の対応と平時の確認内容を明確にしておきましょう。
- 建物・設備の安全対策:建物・什器・OA機器・外部設備などの対応策を明文化
- ライフライン停止への対策:必要な設備・備品・代替手段を記載
- 備蓄品リスト:区分・品目・量・保管場所などの一覧を作成し、定期更新
設備によって復旧までにかかる日数は異なります。被災状況の想定や具体的な対応を視覚化するために、自施設で想定される影響を対象ごとに時系列でまとめることも有効です。例えば、電力・エレベーター・飲料水・携帯電話・道路などについて、発災当日から1日ごとに、代替策運用・復旧などのスケジュールを一覧できるようにします。
連絡体制・連携体制を構築する
緊急連絡網や安否確認シートを準備し、避難場所や確認担当者の記録も可能なフォーマットにしておきましょう。
連携先の施設・医療機関・自治会などの連絡先一覧を作成し、連絡方法を明確にしておきます。関係者には平時から周知を行いましょう。
また、人事異動や連絡先の変更を随時反映し、体調管理・出入り記録も含めた体制作りを行います。災害用伝言板やサイネージなどの情報共有手段の整備も検討しましょう。
緊急時を想定した研修・訓練を行う
BCPを策定したら、全関係者が緊急時に適切な行動を取れるよう、研修・訓練を定期的に実施します。以下のような訓練計画が有効です。
- 災害発生から復旧までの流れを机上で確認する
- 発災直後を想定した対策本部の設置訓練を行う
- 夜間・休日・荒天など不利な状況を想定した、参集訓練や避難訓練を行う
- 人員確認・避難・機器操作・安否確認など、初動で確実に行うべき行動の訓練を行う
- 地域住民など連携すべき関係者とともに、一連の流れを確認する
適宜BCPの検証と見直しを行う
BCPを有効に機能させるには、PDCAサイクルによる検証・見直しが欠かせません。以下のような変化があった場合は特に注意が必要です。
- 組織体制や情報システムの大幅な変更
- 想定リスクの変化
- 国や業界のガイドラインの改定
大きな変更がなくても、BCPは年1回以上の見直しが望まれます。連絡先などは変更が生じ次第、即時に更新しましょう。
BCP対策に必須の情報取得・共有を効率化する環境整備ならイッツコム!

策定・見直ししたBCPを形骸化させず、計画や訓練の実効性を高めるためには、情報の取得・共有を効率化する仕組み作りが重要です。イッツコムなら、「テレビ・プッシュ」やクラウド型デジタルサイネージなどのサービスにより、緊急時にも平時にも役立つ環境整備をサポートできます。
「テレビ・プッシュ」で緊急時の防災情報を即時に共有
BCPを円滑に発動するには、防災情報を迅速に取得・共有できる手段が不可欠です。対応が遅れると、関係者が混乱し、初動で重大なミスを引き起こす可能性があります。
イッツコムの「テレビ・プッシュ」を導入することで、自治体から配信される地域の防災情報などを、テレビを通じてプッシュ配信することが可能になります。施設・事業所内のテレビに、内蔵スピーカーを搭載した専用端末を接続するだけで、緊急地震速報や避難情報を即時に共有でき、担当者を介さず全員が同時に行動を開始できます。
さらに、リモコン操作により、周辺の天気・雨雲レーダー・河川カメラの映像なども確認できるため、事前・事後の情報収集にも役立ちます。
クラウド型サイネージで平時の情報共有を円滑に
平時から、防災や感染症対策に関する情報を、対策本部から確実に伝達できる仕組みを整えておくことは、緊急時の迷いのない行動やBCP発動への意識付けにつながります。
イッツコムが提供するクラウド型デジタルサイネージを活用すれば、BCP関連の画像や動画などのコンテンツを、Webブラウザ上で操作し、クラウドを介して施設内の複数端末へ一括配信できます。ディスプレイにはSTB(セットトップボックス)を接続するだけでよく、施設外からの遠隔操作にも対応しています。
スケジュール配信の他、即時のコンテンツ更新も、タッチコンテンツの配信管理も可能です。タッチパネル式の機材を導入すると、利用者や職員がタッチ操作にて、BCP関連の情報をいつでも参照できます。ディスプレイにはPCやタブレットで表示した資料などをミラーリングすることもでき、大画面で情報共有しつつ机上訓練を行う際にも重宝します。
【関連記事:クラウド型デジタルサイネージとは?配信方式別メリットや導入の流れ】
「かんたんWi-Fi」で業務用と来訪者用の通信を安定化
「テレビ・プッシュ」やサイネージの運用には、安定したネット接続が必要です。LAN配線が煩雑になるのを避けるため、業務用Wi-Fiアクセスポイント(AP)の設置が効果的です。
イッツコムの「かんたんWi-Fi」は、高性能APを手間なく導入できるレンタルサービスです。ゲストWi-Fi機能により、職員と利用者のネットワークを分離でき、安全なフリーWi-Fiも提供可能です。
Wi-Fi6に対応した「ハイエンド6」プランを利用すれば、高速かつ高セキュリティな通信環境を維持しながら、多数の端末が同時に接続してもネットワークトラブルを防ぐことができます。加えて、光回線の強化や通信経路の二重化など、BCP対策に必要な通信インフラを包括的に整備することも可能です。
【関連記事:アクセスポイントとは?LANの仕組みや機器の機能も一挙解説】
【関連記事:インターネット回線の冗長化とは?仕組みや具体的な構成例を一挙解説】
まとめ

介護事業者は入所者・利用者の生命の安全に直結するサービスを提供するため、緊急時でも最低限のサービスの継続が求められ、法的にもBCPの策定・運用が必須となっています。感染症だけでなく地震などの自然災害も想定したBCPを策定し、定期的な訓練や検証・見直しによって、計画の実効性を高めることが重要です。
平時には入所者・利用者や職員に対するBCPの意識付け、緊急時には迅速かつ正確な情報取得を行うことも求められます。BCPの実効性を高める環境整備をお考えなら、ニーズに合った情報取得・共有のソリューションを提案できるイッツコムにご相談ください。