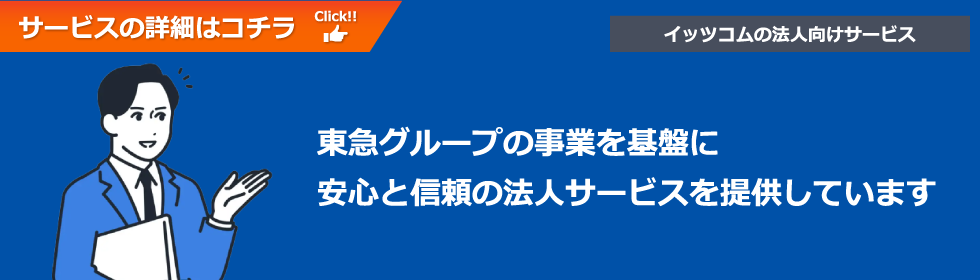オフィス防災対策の必要性は?実施すべき具体的な対策とポイント
オフィスにおける防災対策について理解を深め、実効性の高い計画・対策につなげたい方も多いのではないでしょうか。オフィス家具の転倒防止や避難経路の確保、帰宅困難者向けの備蓄はもちろん、連携体制の構築や平時からの意識付けなども重要です。
この記事では、オフィス防災対策の必要性、具体的な対策とポイントを解説します。起こり得るさまざまなリスクを想定し、対策が有効に機能するための環境を整備しましょう。
オフィス防災対策の必要性

オフィスにおける防災対策は、主に地震・火災や水害といった自然災害への備えです。被災時に従業員の心身の安全を確保しつつ、物的損害を最小化するために、「自助」や「共助」の意識を持って取り組むことが求められます。
従業員の心身の安全を確保する
防災対策は、オフィスで働く従業員の心身の安全を確保するうえで欠かせない取り組みです。地震・火災・水害といった自然災害のリスクは、物件の立地条件だけでなく、発災時を想定したオフィス環境の整備や日常的な備えにも大きく左右されます。
また、防災対策は法的にも義務づけられた重要な取り組みです。労働契約法第5条により、使用者は労働者に対して労働契約上の付随的義務として、安全配慮義務を当然に負うことが定められています。さらに、自社オフィスで発生した火災が他のフロアの従業員や来訪者を危険にさらすケースもあれば、逆に自社が周囲の火災等に巻き込まれる可能性もあります。
このように防災対策は、経営者や防災担当者だけの責任とするのではなく、「自助」の意識を持って従業員自ら取り組むとともに、「共助」の意識を持って周辺企業などとも協力体制を築くことが大切です。
物的損害を最小化する
オフィスの物的損害を最小化するという観点からも、防災対策は欠かせません。たとえ人命を守れたとしても、必要な対策を講じていなければ、OA機器や機械設備といった重要な資産が損失を被る恐れがあります。
特にリモートワークを導入している企業など、出社率が低い職場では、被災時に限られた人員で初動対応を行わなければならない場面が想定されます。火元となり得る機器の安全管理や、オフィス家具の転倒・移動防止などを平時から徹底するとともに、働き方に関係なく防災関連情報を共有できる仕組みを整えておきましょう。被災時に誰もが迅速に行動できる体制を構築しておくことが重要です。
オフィスで実施すべき具体的な防災対策

被災時には、オフィス家具の転倒や避難の遅れ、交通機能の停止による帰宅困難者の発生など、さまざまなリスクが想定されます。平時から被災を想定し、家具類の転倒防止、避難経路の確保、インフラ復旧まで耐え忍べる備蓄の確保といった対策を講じておくことが重要です。
また、連絡・連携体制の構築や、防災教育・防災訓練を定期的に実施することも求められます。
オフィス家具・OA機器類の転倒防止やレイアウトの工夫
地震を想定した防災対策としては、オフィス家具・OA機器の転倒防止や、レイアウトの工夫が挙げられます。地震大国の日本では、全てのオフィスに必要な対策です。高層階では家具の転倒・落下・移動の危険が高まるため、特に注意が必要です。主な対策は以下をご覧ください。
- 出入り口や避難経路の周囲に、転倒・移動しやすい家具を置かない
- 棚は金具で連結し、床・壁・天井に固定する
- 収納物は重いものを下段に収め、重心を下げる
- 引き出しや収納物の飛び出しを防ぐラッチ付きやセーフティロック付きの家具を選ぶ
- ガラスには飛散防止フィルムを貼る
- パーティションはコの字またはH字に組む
- キャスター付き複合機などには移動・転倒防止器具を取り付ける
- デスクや椅子は、背の高い家具や窓ガラスから距離を取る
- デスク上を整理し、PCやディスプレイはストラップや粘着マットで固定する
- 被災時に潜れるよう、デスク下は常にスペースを確保しておく
ペーパーレス化やデータのバックアップ
棚類の収納物やPC関連では、ペーパーレス化とデータのバックアップも欠かせません。蓄積した情報資産が失われれば、被災後の事業継続が困難になる恐れがあります。紙で保存した情報は火災や水害で失われやすく、またPCの破損や水没によってストレージ内のデータが失われるリスクもあります。事業継続の観点からも、ペーパーレス化を推進し、電子化した情報は定期的にバックアップを取りましょう。
ただし、元データとバックアップデータを同じオフィス内に保管していると、災害時に同時に失われる恐れがあります。オンラインストレージサービスを利用し、遠隔地のサーバにデータを保存しておくと、より安全です。
【関連記事:クラウドストレージ「Box」の魅力は?使い方やメリットを徹底解説】
避難経路やライフラインなどの安全確認
地震などが発生した際は、まず生命を守る行動が最優先です。平常時から避難経路の安全確認を行い、緊急時にも落ち着いて行動できるよう備えておくとともに、不注意による発火や二次災害の防止にも努めましょう。主な取り組みは以下の通りです。
- 避難経路は2方向(通常の出入り口と非常口など)を確保する
- 避難経路やハザードマップを確認し、安全な避難方法を周知する
- 出入り口・廊下・階段などの避難経路には、可能な限り障害物を置かない
- 灯油や塗料・薬品の容器が転倒・落下しないよう対策を講じる
- 火を使用する機器・設備の安全確認を行う
- 消火器を準備し、設置場所と使用方法を共有する
- 寿命が近い照明器具やコード類は、異常がなくても早めに交換する
- たこ足配線を避け、コンセント周辺の密閉やほこりの蓄積を防ぐ
- 施設の防災担当者や管理会社に、防災設備とライフラインの復旧方法を確認しておく
- 電気・水道・ガスなどが停止した場合に備え、使えるもの・使えなくなるものを把握しておく
被災直後に必要な防災グッズの常備
オフィスの被災時には、建物の倒壊や家具の転倒による避難経路の封鎖、従業員のけがや体調不良などが発生する可能性もあります。安全を確保しつつ避難するための備えとして、以下のような防災グッズを常備しておきましょう。
- ヘルメットや防煙マスク(従業員数分)
- 脱出・救助用工具セット(クラッシュハンマーやバールなど)
- 軍手・ロープ・担架
- 消化砂・吸水材・スコップ・バケツ
- 救急箱(包帯・消毒液・解熱剤・胃腸薬など)
- 三角巾やAED
- 非常用発電機や投光器
- 笛・拡声器・トランシーバー
- 地図やコンパス
帰宅困難者がオフィス内で耐えるための備蓄
地震や台風などの影響により交通機能が停止し、帰宅困難者が出る恐れがあります。近隣店舗で生活必需品の供給が一時的に止まったり、入荷後すぐに売り切れたりすることも考えられます。停電や断水も想定される中で、オフィス内でインフラ復旧まで耐えるために、以下のような備蓄が重要です。
- 飲料水(1日3L、3日分を従業員数分)
- 非常食(1日3食、3日分を従業員数分)
- 毛布や寝袋を従業員数分
- カセットコンロや燃料
- 救急用品・医薬品や生理用品
- 紙皿、割り箸、ラップ
- 簡易トイレ、トイレットペーパー、ティッシュペーパー
- マスク、ウェットシート、水不要の歯磨き、消毒液
- 大型のビニール袋・ごみ袋やブルーシート
- テレビやラジオ
- モバイルバッテリーや充電器
- 懐中電灯やLEDランタン
- ポータブル発電機と燃料
- 暑さ対策用品(冷却スプレー・冷却ジェルシート・扇子など)
- 寒さ対策用品(携帯カイロ・ダウンジャケット・防水ウェアなど)
停電時にクレジットカードや電子マネーが使えるとは限らないため、ある程度の現金も持ち歩くことを周知しましょう。
日頃と被災時の役割分担や連絡・連携体制の構築
地震・火災・水害などさまざまな災害リスクに備え、連絡・連携体制を構築することも重要です。「誰が何をするのか」を明確化するために、日頃の防災と被災時について、組織内で役割分担を決めておきましょう。
- 日頃の防災:防災・火元の責任者、施設設備・消火器・防災訓練の担当者など
- 被災時:リーダー・初期消火・情報連絡・避難誘導、救出・救護の担当者など
被災時には正確な情報の入手と、関係者を混乱させない情報伝達が求められます。信頼できる情報の提供元・入手方法を定めておき、連絡網や伝達方法、安否確認方法を周知しましょう。大規模な災害の発生時には電話回線の混雑も予想されます。衛星回線・無線・トランシーバーなどを準備し、使用方法に慣れておくことも大切です。大勢で一斉に状況を確認・報告・共有したい場合、スマホでも狭帯域でも使えるWeb会議システムが役立ちます。
また、被害が広範囲に及ぶ場合、周辺企業や地域住民との連携も求められます。従業員による「自助」だけでなく、「共助」も意識し、日頃から関係者と協力体制について話し合っておきましょう。
【関連記事:Zoomの使い方を解説!基礎から応用まで覚えてフル活用しよう】
定期的な防災教育・防災訓練の実施
より確実な防災対策のために、防災教育や防災訓練を行いましょう。防災教育は企業の対策計画や従業員の行動基準などについての研修で、その研修で得た知識を実践できるか試すのが防災訓練です。防災訓練は年に1回など定期的に行い、以下のような内容を実践します。
- 初期消火の手順:周囲への警告、119番通報、消火器や屋内消火栓の使い方、消火と避難の判断基準
- 避難・誘導の方法:建物内への発災周知、避難経路の利用、避難器具の使い方
- 応急手当の方法:意識がない人への対応、止血ややけどの応急処置、重傷者の搬送方法
その他、身を守る行動や情報収集の訓練、災害シナリオに基づく図上訓練なども有効です。防災訓練に加えて、日頃から社内で防災情報を共有し、防災マニュアルを整備することで、対策の実効性を高めましょう。
防災対策を前提とした情報取得・共有の仕組み作りならイッツコム!

被災時には災害関連情報の取得・共有の混乱が予想されます。防災対策の実効性を高めるには、平時から意識付けを行うことも大切です。イッツコムなら、「テレビ・プッシュ」やクラウド型デジタルサイネージなどのサービスにより、防災対策を前提とした情報取得・共有の仕組み作りを総合的にサポートできます。
「テレビ・プッシュ」で信頼できる災害情報をいち早く取得
生命を脅かすような災害が起こった場合、従業員は状況が飲み込めず混乱し、事前に想定していた避難行動などを取れない恐れがあります。被災時には信頼できる災害情報を迅速に取得・共有し、冷静に状況を判断して、全社一丸となって行動を開始することが必要です。
イッツコムが提供する「テレビ・プッシュ」を導入すると、自治体などによる確かな災害情報を、オフィス内のテレビからいち早く取得できるようになります。基本的な設定は、テレビに専用端末を接続するだけです。緊急時にはテレビが自動起動し、音声と画面で緊急地震速報や避難情報を伝えます。
速報の前後には、リモコン操作で付近の雨雲レーダーや河川カメラの映像、電車の運行情報や自治体情報なども確認可能です。被災時に慌てず確実に生命を守る行動が取りやすくなる他、オフィスにとどまるべきか否かといった判断にも役立ちます。
クラウド型デジタルサイネージで日頃から全従業員の防災意識を高く保つ
被災時に適切な行動を取るためには、日頃から全従業員が防災意識を高く保っておくことも重要です。定期的に防災教育を行うこともできますが、いずれ記憶が薄れ、思いがけず被災してパニックに陥る恐れがあります。
イッツコムが提供するクラウド型デジタルサイネージは、防災意識を高めるための情報共有の仕組み作りに最適です。任意のディスプレイにSTB(セットトップボックス)を接続すると、インターネット経由でオリジナルの画像や動画を配信できるようになります。リモートワーク中の従業員が、多台数を一括で管理・更新することも可能です。
ディスプレイはスタンド設置だけでなく、遠くからも視認しやすい位置に壁掛けや天吊りもでき、メールなどに比べてはるかに高い視聴率とインパクトを期待できます。従業員にとって興味のあるコンテンツも挟むことで、画面を見ることを習慣化させやすく、防災対策の意識付けをしやすくなるでしょう。
会議室などで図上訓練を行う際にも、PCやタブレットで表示した資料を大画面にミラーリングでき、情報伝達の抜け漏れを防止しやすくなります。
【関連記事:クラウド型デジタルサイネージとは?配信方式別メリットや導入の流れ】
「かんたんWi-Fi」で平時の安全管理にも緊急時の情報取得・共有にも役立つWi-Fi環境を整備
PCやSTBなどを有線接続して社内LANを構築すると、LANケーブルの配線が複雑になります。コネクタ部分からの発火やケーブルに足を引っかけることによる転倒などのリスクも増すため、防災対策上、Wi-Fi接続で運用するのが有利です。Wi-Fiルーター1台だと同時接続台数や電波の死角などの懸念もありますが、業務用Wi-Fiアクセスポイント(AP)を要所に設置すれば、懸念点を解消できます。
イッツコムが提供する「かんたんWi-Fi」は、高性能APを低コストでレンタルできる法人向けサービスです。「ハイエンド6」プランのAPは高速・高セキュアなWi-Fi6対応で、オフィス内のWi-Fi環境を総合的にアップグレードできます。業務用と来訪者用のWi-Fiネットワークを分離するゲストWi-Fi機能も完備し、拡張性の高さも魅力です。
インターネット回線さえ生きていれば、従業員が帰宅困難になった際にも、混雑する電話回線を回避して各自のスマホから情報の取得・共有ができます。被災時にはインターネット回線の途絶も懸念されますが、イッツコムは回線の二重化に最適な法人向け光回線もセットで提供でき、防災対策を前提とした通信環境を総合的にサポートできます。
【関連記事:アクセスポイントとは?LANの仕組みや機器の機能も一挙解説】
【関連記事:インターネット回線の冗長化とは?仕組みや具体的な構成例を一挙解説】
まとめ

オフィスの防災対策は、被災時に起こり得るさまざまなリスクを想定し、自助や共助の意識を持って取り組むことが求められます。オフィス家具の転倒防止や避難経路の確保、帰宅困難者が出た場合の備蓄はもちろん、連絡・連携対策の構築や防災教育・防災訓練などの備えも重要です。
平時から従業員の防災意識を高く保ち、被災時に迷いなく行動を開始できるように、適切な情報取得・共有の仕組みも持ちましょう。防災対策の実効性を高めるための環境整備をお考えなら、平時にも被災時にも役立つサービスを提案できるイッツコムにご相談ください。